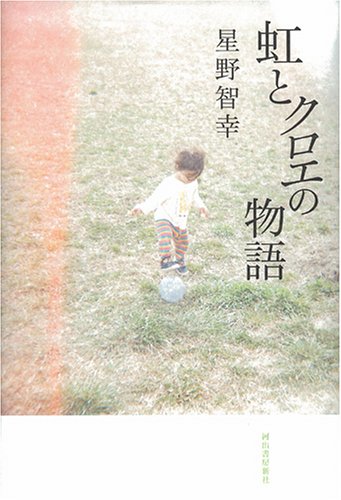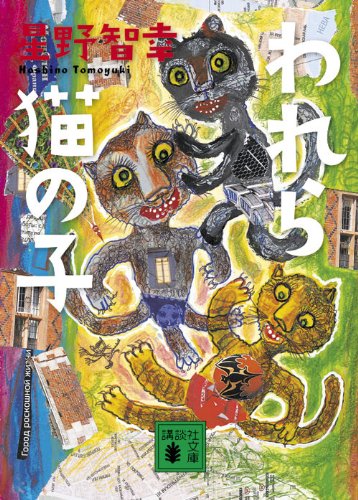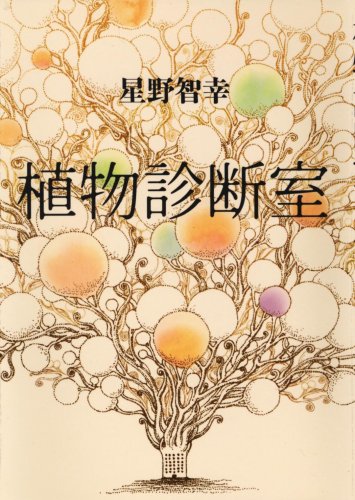政治にアレルギーを持てば持つほど、逆に文学は政治に弱くなって取り込まれてしまう
――今の時代の政治を反映した作品を書く時、たとえば100年後には社会が変わっているだろうから、どう読まれるか分かりませんよね。ご自身の作品がどう読み継がれていくかは意識されていますか。
星野 『赤と黒』は革命期のフランスを描いた、政治と切り離せない作品ですよね。『悪霊』だって、ロシア革命前夜の政治の話ですよね。近代文学はみんな、普通にその時代の政治の話を書いている。それを書くことは問題がないどころか、文学の重要なジャンルであり、重要な一テーマであって、政治を書くと普遍性がなくなるのではなく、むしろ政治を書かないと普遍性がなくなるとさえ、僕は思っているんです。それはラテンアメリカの小説もみんなそうですよね。『百年の孤独』も内戦の歴史だし。だから、そういう極端に大きなレベルの政治から小さな政治の話まで、それは日常の生活を大きく左右する、市井の人々の日常と地続きなこととしてとらえるべきだと思うんです。
ただ、日本の文学の場合には、政治に挫折した人が文学に行って、文学は政治から距離を置いて、しかも個人の生を突き詰めて、だんだん私小説になって、という歴史もある。どこかで政治に触れると普遍性がなくなるという、ある種の警戒感が今も根深くありますよね。で、戦後の文学は、そのアレルギーを一時期脱したと思うんですけれども、また70年代後半くらいから捕らわれていったと思うんです。
だけど、政治にアレルギーを持てば持つほど、逆に文学は政治に弱くなって取り込まれてしまう。普通の人が日常のレベルで政治を考えないで、政治は特殊な人がすることというふうに思っていると、政治に対してすごくウブな状態になってしまい、何か政治的に強い行動が起こると、すぐにそれになびいてしまう、ということを僕は実感しています。文学も同じ。だから文学も政治を普通に扱うべきだと思っている。
今は逆に、極端に寓話的に政治を扱おうとする向きが広がっていますけれどね。そういう小説があってもいいと思うし、もっと普通のレベルでいろいろ政治を扱う小説が出てきたほうがいいんじゃないかなということは、ずっと感じています。そういう意識があったから、あえて自分で「政治小説」と称していたんですね。
――『虹とクロエの物語』(2006年河出書房新社刊)は40代女性二人の友情とそれぞれの生き方の話ですよね。胎児の視点が出てきたりと、幻想的な場面もあって。
星野 これはたぶん、自分が40代になって、なのに20代の頃に想像していたような成熟が全然ないということと(笑)、そもそも成熟している大人っていうこと自体が幻想であると痛感したことが発端でしょうね。若い時にイメージしていた40代を考えると、現実の自分があまりにも子どもっぽくて嫌になってしまう。その成熟とか、成熟しなささを考えながら、自分でも現状を肯定したかったんですよね。
――同窓会で再会する女性2人が旧交をあたためる。一人は主婦で、一人は独身で。
星野 40代の成熟の標準というのがそもそも、女性だったら結婚していて、いくつぐらいの子どもがいて、というのを基準に見てしまうこと自体がおかしいわけですよね。主人公の2人は「そうじゃない」と言い切るほど強い批判の言葉は持っていないけれど、漠然とした違和感を抱えながら、その少しだけマイナーな、世のイメージの「成熟」から外れた自分たちの生き方を肯定していこうとする物語ですね。そういう道を積極的に選んでいけるのは、信頼しあう女性同士であることのほうが圧倒的にリアルなんですよね。そこに、世の「成熟」から外れた男性も何とか混ぜてあげようとしたら、胎児にするしかなかったという(笑)
――長年にわたって書いた短篇を集めた作品集『われら猫の子』(06年講談社刊)を経て、次の『植物診断室』(2007年文藝春秋刊)も、現代人の生き方の問題が扱われているといえます。植物診断に通う男性が、シングルマザーから、「父親でもなく夫でもなく、一人の大人の男性として」子どもに接してほしいと頼まれる。
星野 これ、実話なんです。昔の友達がシングルマザーで、男の子がいたんです。息子が思春期に入っていくにあたって、男のことは自分には分からないからどうしたらいいか困っている、でも別れた夫のような男にはなってほしくない。なかなかいい男性のモデルケースがいない、と相談を受けたことがあったんです。それで、確かに、なるほどと思って、小説で考えてみることにしたんです。
だから男らしくない男を出したんですね。彼のほうも自分が世の男の標準像から脱落しちゃっているので、どうしても自分を男としても人間としても、うまく肯定できずにいる。それで植物診断室なるところに通っているわけです。それがシングルマザーとその息子と触れあうことによって、彼のほうも自分を肯定できるようになっていく。恋愛には絶対にならないようにしてね。自分たちがそのような生き方をすることが、空虚に形式化する社会を変える実例になるんだってことを書きたかったんです。
ただ、あまりにも分かりやすく書こうとしたら、当時の文學界編集者の中本さんに、「これでは星野さんらしさが失われています」と指摘されたんですよ。自分でも無理していると感じていたのではっとして、それでたいぶ書き直しました。「もっと星野さんらしくしていていいと思います」と言ってくれて、それで自分もちょっと楽になったんですよね。