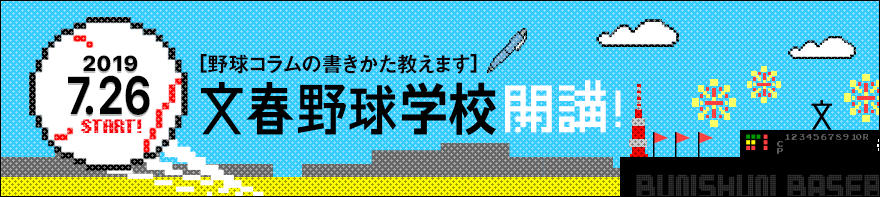初めてのナゴヤドームの、その大きな電光掲示板に、あの人の名はなかった。
「え? 子ども置いてひとりで野球? ゴールデンウィークに?」
ママ友からの責めるようなLINEが思ったより心に重く圧し掛かっていた。行楽地に向かう家族づれで満席の東海道新幹線。眠たいのにうまく眠れないのだろう、2歳くらいの男の子がママの膝で時折グズる。そのたびにママは慌てて男の子を抱っこしては、デッキに消えていった。私はひとり、コーヒーを買って窓の外を眺める。あのママはもうひとつの世界の私だ。休みの日には親子で旅行に出かけて、大変だけど楽しい時間を過ごす。幸せは数えられないけど、家族の思い出なら数えられる。ふと虚しくなる気持ちを増えていくアルバムがなだめてくれた。
でも私は、今ひとりでナゴヤドームに向かっているのだ。何も考えずに沖縄へと飛び立ったときにはない罪悪感をおぼえていた。名古屋のほうがずっとずっと近いのに。開幕から倉本はなかなか調子が上がらなかった。凡退して1塁からベンチに下がっていく後ろ姿をただテレビで観ることしかできない自分がもどかしかった。夫が家にいる連休中しか、球場で倉本を応援するチャンスはない。それがこの4月最後のナゴヤドームだったのだ。
「家族で行けばいいじゃないか」と夫は言った。「うん……でも」。そのとき私ははっきりと「ひとりで行きたい」と思っていた。それは上手に言葉にはならない気持ち。家族で行くのが嫌なのではなくて、なんだろう、なんて言えば分かってもらえるのだろうか……。下を向いて黙ってると、夫は「いいよ、行ってくれば」とそっけなく言った。冷たい空気が流れていた。
男の人には分からないかもしれない。飲みに行くのもゴルフも釣りも、「仕事」の延長で何とでもなるあなたには。簡単に「ひとり」になれるあなたには。野球を観に行くことが、倉本を応援することが、家族の娯楽ではないことを私は分かっていた。夫の冷たい返事と、ママ友からのLINEと、新幹線の子どもの泣き声が私のワガママを非難しているようで、たまらなくなってコーヒーを飲み干した。すっかり冷えてしまったホットコーヒーを。
初めての「倉本のいないベイスターズ」
ハマスタ以外の球場は初めてで、もちろんドームで野球を観るのも初めてだった。名古屋の空は魔法陣みたいな天井に閉ざされていて、どこか魔物を召喚するような雰囲気があった。3塁側の内野席で「どうか倉本が活躍しますように……」と、魔法陣を見上げて願う。そのときふと私の耳に届いた。「9番、セカンド、宮本」という、聞き慣れないアナウンスが。
初めてのナゴヤドームで、私は初めての「倉本のいないベイスターズ」を目の当たりにしていた。石田投手と小笠原投手、開幕ピッチャー同士の投げ合いは投手戦の様相。ルーキーの宮本選手は、この少ないチャンスを何とかものにしようと懸命にプレーしていた。しかし小笠原投手のキレのある変化球に、宮本選手のバットは何度も空を切る。「ああ倉本……」と反射的に考えてしまった私を、チームの勝利を願う私が責めた。混乱していた。テレビで偶然倉本を観て、それまで全く知らなかった野球という世界が目の前に開けた。倉本を好きになるのと同じスピードで、ベイスターズが好きになった。私にとって、倉本とベイスターズは一体だった。だから、混乱していた。
息苦しさから逃れるように、周囲に視線を移す。私と同じように倉本のユニフォームを着た女性が、少し前の座席でまんじりともせず試合の行方を見守っている。その隣には石川選手のユニフォームを着た人が、田中投手の人も、白崎選手の人もいた。ファンになったときから倉本はいつもスタメンで、ハマスタに行けばいつでもその姿を観ることができた。だから私は気づかなかったんだ。一軍にいない、今試合に出ていない選手のユニフォームで応援している人がこれほどたくさんいることに。その純粋で透明な、やるせない想いに、泣きたくなっていた。