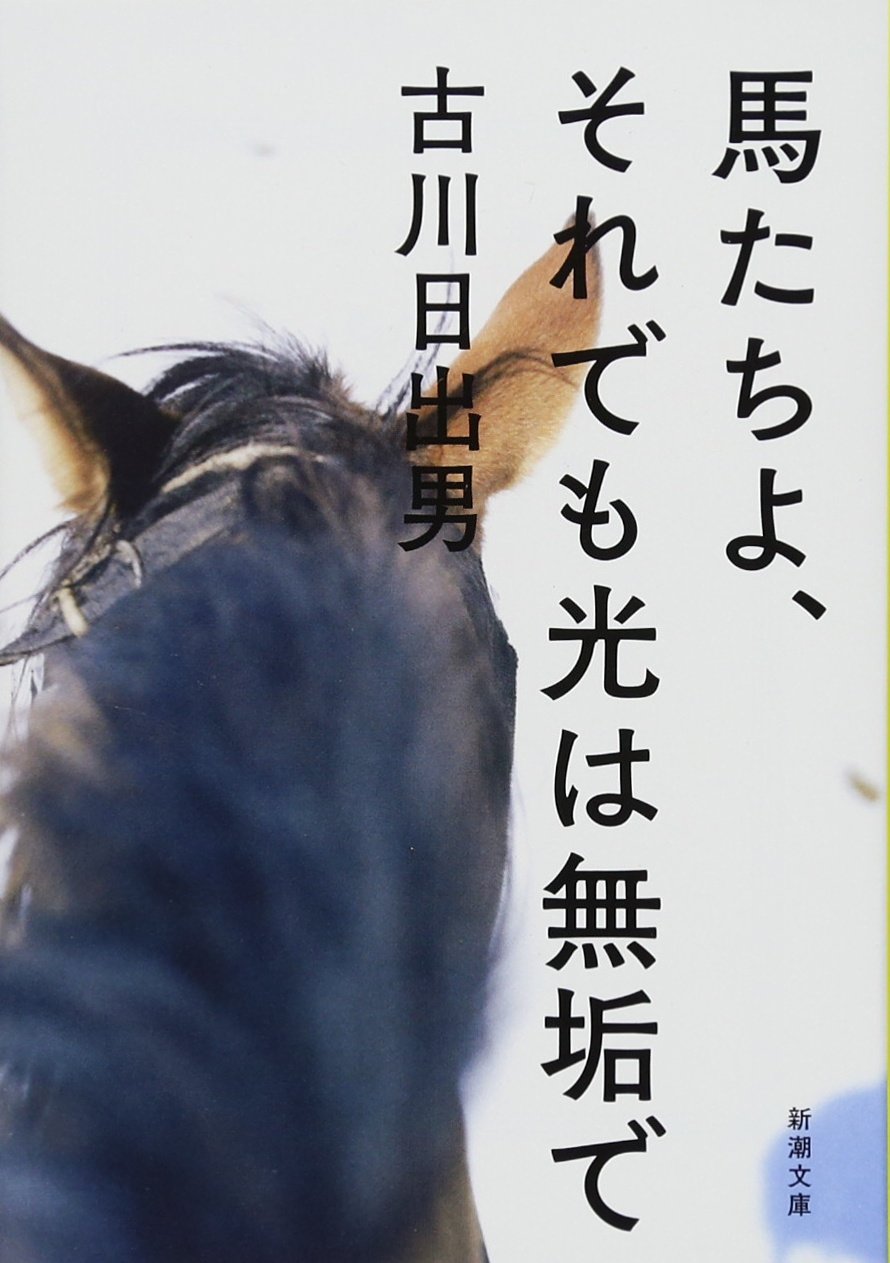音楽だって、いい音楽を作る人は1000曲どころか1000枚のアルバムを聴いている
――これまでは『ロックンロール七部作』(05年集英社刊)や『南無ロックンロール二十一部経』(13年河出書房新社刊)といったロックがモチーフの小説を書かれていますよね。今回はヒップホップだ、と思ったわけですか。彼らは自分たちの音楽を「ニップノップ」と名付けますが。
古川 ものを作っていると、オリジナリティってこだわっちゃうじゃないですか。でも自分がオリジナルだと本人が言うのは、すごく傲慢。だっていい本が書ける理由は、過去にいい本をいっぱい読んできたからでしょう。音楽だって、いい音楽を作る人は1000曲どころか1000枚のアルバムを聴いている。ゼロから、あるいは1から音楽を作っている人はいないのに、「これはオリジナルの音楽だ」って言ってるような風潮にアンチを唱えたのが、そこらへんのレコードから部分部分を引き出してサンプリングしてくっつけて、勝手に人の曲で自分の曲を作るヒップホップという文化なんですよ。それってものすごく正直だなと思って。いいものがいっぱいあって幸せだったんで、それらを盗んで自分もいいものを作ります、みたいな率直な態度が感動的でした。1980年代以降にこれが出てきて、日本にも影響を与えてという流れを、僕は同時代で見てきたんです。それはもう、本当に強烈だった。音楽とかライフスタイルとかじゃなくて、方法論のところにすごくリスペクトをおぼえました。あの在り方を自分の小説の中に入れてみたかったんですよね。自分たちが聴いてきた音楽にリスペクトを表明して1曲や1枚を作っている君たちを心底リスペクトして小説家の自分が本を1冊作る、というのは面白いと思いました。
――そんなニップノップグループの一員が誘拐され、犯人グループに「日本の核武装」が要求される。彼らをそう追い詰めたのはどうしてですか。
古川 それは僕が自分自身のことを追い詰めているんでしょうね。真剣に真剣に日本の歴史とか、今の地球上の状況とかを考え抜いて出てきた設定です。この現実の世界で生きている1人の人間として僕自身が悩んで頭をぶつけているから、登場人物たちにも一緒にそういう難題に向かって頭をぶつけてもらう。彼らを苦しい目に遭わせるならば、それ以上に自分が苦しみながら、必死に希望を探って、この先の展開をどうしたらいいんだろうと考えて考えて考えて考え続ける。それが『ミライミライ』という小説の世界と一緒に執筆期間を生きていくということでした。
――答えのないまま。
古川 答えのないまま。答えはきっちり考え考えはしているけれど、正解が1個だけじゃないのかもしれないし。とにかくみんなが読んで、この中には本当のことがある、この中に現実があると思ってしまう小説にしたかった。『ミライミライ』を読み終えてポンと本を閉じた時に、フィクションの世界からではなくて、もうひとつの本物の世界から、自分が生きているまた別の本物の世界に戻ってきたんだって思ってもらえたらいいなって。『ミライミライ』の中に出てきた連中と同じように生きていこうと思ってくれたらって。ひとり、読んでくれた人が手紙をくれて、「私は産土たちにまた会う気がします。どこかで」と書いてくれていて。それはすごく感動的でした。やっぱり自分が考えていることとか、自分が小説書きながら望んでいたことが、読者に伝わっているなと思ったし。
読書を通して信頼とか愛とか、もしかしたら正義とか、そういうものが回ったらいい
――ニップノップ・チーム「最新」(新に゛をふって読みは「サイジン」)のメンバーは、MCの梶友希、高良准市(ジュンチ)、澤太伊知またの名を野狐、DJの三田村真またの名を産土の4人。彼らの出自もさまざまですが、古川さんは産土に自分が近いとおっしゃっていましたよね。
古川 DJであるという側面は、自分のものの作り方とすごく似ているんです。バンドのフロントになってスポットライト浴びる人よりも、曲を作ったり演出をしたり、振り付けをしている人を一緒にしたような存在が、僕なんだろうし。
40代の半ばを過ぎるまで、自分のことを一切考えないようにしてきたし、過去のことなどあんまり喋らないできたんですけれど、震災があって故郷の福島のこととか喋らなくちゃいけなくなってきた頃から、考えるようになってきました。そういうことはあまり書かないんだけれど、『ミライミライ』に本当のこと、真実のことをいっぱい入れていくために、気が付いたら産土に筆を費やして、ああいうふうになっていました。それは、言ってみれば小さかった頃の自分を救おうとしていたのかもしれません。
『馬たちよ、それでも光は無垢で』(11年刊/のち新潮文庫)でも相当正直に書いたけれど、生まれ育った環境とか、助けてくれる人たちの存在とか、正直に書いたんですよね。15歳離れた姪とか、17歳離れた甥とかがいなかったら、おそらく自分は長く生きてられなかったと思う時がいっぱいある。彼らに生かしてもらったみたいな気持ちが、産土の異父妹の花梨みたいな登場人物や挿話の形で出てきたんでしょうね。
それと、ちょうど産土の章を雑誌に発表した頃に、相模原の障害者施設の殺傷事件があったじゃないですか。たまたま産土は花梨とか音楽というものがあったから、人に希望を与える側に行けたけれど、もしそれがなかったら産土も暴力的な、世界を否定するような態度のままでいたかもしれない。でも、自分が愛情を注ぐから相手も愛情を注いでくれて、それで救われていくところはある。現実にある。そのことを信じているんです。自分が小説を書いていても、この世界を愛して読者に届けて、その作品世界を読者が読んで愛してくれると、それが僕に返ってくるんですよ。そういうことを、この世の中でぐるぐる回していきたい。たとえば読書を通して信頼とか愛とか、もしかしたら正義とか、そういうものが回ったらいいんじゃないかって思っていて。それを実践するために、ちょっとずつちょっとずつ、自分の小説も変わってきていますね。