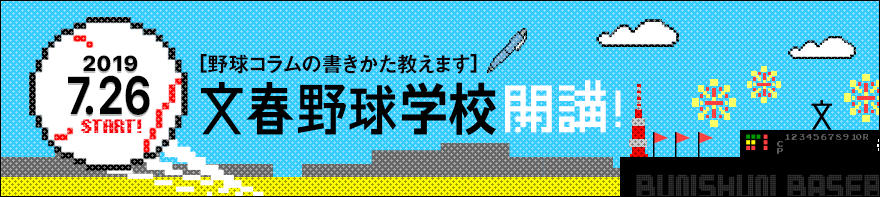現役時代に投手だったドラゴンズのOBが、こう話しかけてきた。
「ヘンリーさん、僕たちは昭和の人間なんだよ。今は平成だけど、来年からは年号も変わって2世代前の人間になってしまう。もう僕たちの時代のやり方は通用しないよ」
日大の悪質タックル問題を話題にしていた時のことである。私は記者として、その投手はチームの主力リリーバーとして、かつては星野仙一監督の下でまさに闘っていた。
一介の記者が「闘う」は違和感があるかもしれない。だが星野監督には「担当記者も戦闘集団の一員」という確固としたポリシーがあった。チーム状況や采配に批判的な記事を書くときは、どのような反論にも対抗できる野球観、知識、論理で臨む覚悟が必要だった。それを怠れば気迫のないプレーをした選手に対してと同様の厳しい叱責が待っていた。緊張感は常にピークだった。
話を戻そう。その元投手の言葉に、恥ずかしながら私は何も言い返すことはできなかった。日大の守備選手は、パスを投げ終えて無防備な関学大QBに背後からタックルをした。その背景に、監督の意を酌んだコーチによる「試合に出たければ相手QBをつぶせ」の言葉があったと知ったとき、私の脳裏には当時のドラゴンズがフラッシュバックした。恐らくは、その元投手にも同じ記憶がよみがえったのだと思う。
星野軍団の掟「やられたら、やり返せ」
1987年に39歳の若さで就任した星野監督が真っ先に着手したのは、前年まで2年連続5位だったチームの沈滞ムードを一掃し、戦闘集団によみがえらせることだった。特に投手に対しては逃げの投球をすることを許さず、常に攻撃的であることを強いた。その要求は言葉にすれば「ぶつけてもいいから内角の厳しいところを攻めろ」であり、「やられたら、やり返せ」だった。
この方針に反すれば、選手によっては鉄拳を含む叱責が待つか、最悪なら2軍落ち。ベンチ内のピリピリしたムードを象徴した出来事が、同年6月の“クロマティ殴打事件”だ。熊本・藤崎台球場での巨人戦で宮下昌己の投球がクロマティの右脇腹を直撃。マウンドに突進したクロマティは宮下の顔面に右パンチを見舞い、さらにヘッドロックしたままグラウンドを引きずり回した。
現在は東京の調布で実家の米屋を継ぐ宮下は後に、それまでクロマティが日本人投手をなめたような発言をしていたこと、巨人の桑田真澄が中日の主力打者の内角をえぐる投球をしていたことなどから、ベンチ内に「いったれ!」の空気がまん延し、あえて厳しい投球をしたことを述懐している。
フラッシュバックは、それだけではない。日大アメフト部は有望な選手を厳しい指導で追い込み、精神面で殻を破らせて成長させる方針であったことも明るみに出た。部内ではピックアップされた選手のことを「はまった」と表現していたというが、この指導方針も星野監督の下ではよく見られた。
それを象徴するのは、やはり当時の中村武志捕手だろう。監督就任時に解雇寸前だった中村の強肩に目をつけ、徹底的に鍛え上げるようコーチに命じた。捕手は重労働であることなどお構いなしに、試合直前まで近距離からノックの雨を降らせ、ユニホームはいつも泥だらけだった。見かねた私は星野監督に「やりすぎでは?」と言ったことがある。返ってきたのは「下手くそが練習するのは当たり前だろうが!」の怒声だった。
捕逸などのミスをすれば、翌日にはノックの数も倍増する。それでも中村は試合で使われ続けた。最初のうちは粗削りのリードとキャッチングに不安を漏らしていた投手陣も「あれだけ毎日しごかれても我慢している」と一目置き、エース捕手として認めるようになっていった。「自分が今あるのは星野監督のおかげ」。中村は現在も、そう語っている。