news zeroメインキャスターの有働さんが“時代を作った人たち”の本音に迫る対談企画「有働由美子のマイフェアパーソン」。今回のゲストは建築家の重松象平さんです。
<この記事のポイント>
●重松氏はいま世界で注目の建築家。CCTV(中国中央電視台)とフェイスブックの新オフィス建設計画という現代を象徴する“両極”の仕事をやっている
●コロナ後は、「都市の自由」を演出する建物が求められるようになる
●都市の形骸化を防ぐために重松氏が注目しているのは「食」。食と都市を繋げたいと語る
「不況の申し子」が語る新しい都市の姿
有働 初めてお会いしたのは、私が10年前にNHK特派員としてニューヨークに赴任していた時でした。共通の知人のパーティでしたが、重松さんはお偉いさんに喰ってかかっていましたよね?
重松 いやいや。オジサンが同じ話を繰り返しているのに、有働さんが「うん、うん」と頷いて終わらないから、僕がオジサンにツッコんだんですよ(笑)。
有働 そういう時って、日本人は空気を読んで黙ってるじゃないですか。でも、重松さんは「同じ話をしています」ときっぱりと言って、ひどい怒られ方をしていたよね。
重松 「この若造が」って(笑)。
有働 すごくインパクトのある出会いでした。誰に対しても嘘や忖度がない人だなと思って。
重松 海外に出て15年ほど経っていて、有働さんのこともよく知らなかったから。お酒も入って、僕の天然が出た可能性はありますね。今はもっと空気を読めますよ(笑)。

有働キャスター(左)と重松氏
CCTVとフェイスブック
有働 重松さんは世界7都市に事務所を構える建築設計事務所OMAのニューヨーク代表として世界を舞台に活躍しています。でも、その実績にくらべて、日本ではあまり知られていないことが不思議で。海外では、「ショー」って呼ばれているのに。本人に聞くのも失礼な話ですけど、どうしてでしょう?
重松 知られてないですか(笑)。
僕は九州大学を卒業してすぐオランダに渡り、そのまま25年間、海外にいるからですかね。ヨーロッパに住んだ10年間で、ヨーロッパをはじめ、中国や中東の仕事に数多く関わり、その後アメリカに移って15年です。日本のプロジェクトに携わるようになったのは8年ほど前で、皮肉にも日本が最後なんです。
有働 海外で評価されて、日本に逆輸入されたみたい。日本では「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」(仮称、2023年竣工)や、「天神ビジネスセンター」(仮称、2021年竣工)のプロジェクトが進行中です。
重松 都市計画からアーティストとコラボした展覧会まで、建築に留まらず、様々なスケールの案件を手がけてきました。現在は美術館や公園、住宅、寺院など約20のプロジェクトを指揮しています。

ニューヨークに建設される予定の「ニュー・ミュージアム」
有働 重松さんの経歴で面白いのは、2012年に竣工したCCTV(中国中央電視台)とフェイスブックの新オフィス建設計画(進行中)という、現代を象徴する“両極”の仕事をやっているところだと思うんです。東洋と西洋、社会主義と資本主義、そして管理と自由。まず、CCTVの仕事は、これまでの歩みの中でどんな位置づけですか。
重松 90年代後半に初めて中国に行ったとき、「これが近代化の高揚感か」と驚きました。僕はオイルショックが起きた1973年に生まれ、大学に入学した92年はバブル崩壊期、2006年にOMAニューヨーク代表になって間もなく、リーマンショックがありました。僕の人生は、不況とともにあるんです。親は団塊の世代で右肩上がりの経済成長を経験してきましたが、第2次ベビーブームに生まれた僕は、右肩下がりの経済が当たり前。ずっと世代間ギャップを感じて生きてきました。ですから、CCTVの案件は、国じゅうの人が「明日は必ず今日よりもよくなる」と信じるエネルギーに満ちた社会を初めて追体験できた仕事です。今は建築家としてあの建築に携わったことよりも、その経験こそが重要だったと思っています。
有働 ピサの斜塔じゃないですけど、傾いた2つのビルが絶妙な均衡で支え合っているようなデザインですね。
重松 アイコニックな建築が求められている時代でしたし、社会主義の中国が資本主義を取り込んでいく過程において象徴的な建物が必要だったのだと思います。今は習近平が規制をかけているので、ああいう奇抜な建築は絶対に選ばれません。北京五輪を控え、近代化を進めていたあの瞬間だったからこそ可能だったデザインだと思います。「この建築を建てようとするのも建てられるのも中国だけだろう」と思いました。

代表作のCCTV(2012年竣工)
有働 シリコンバレーで進行中のフェイスブックの新オフィスは、どんなものになるんですか。
重松 オフィスというか、フェイスブックが新しく作ろうとしている都市計画です。既存のオフィスはメンローパークという小さな街の外れにあるので緻密な計画はあまり必要なかったのですが、新オフィスは市街に接した広大なエリアなので、地域との連続性を意識した新しい街全体をデザインする必要があったわけです。
有働 エッ。フェイスブックが街ごと作る?
重松 はい。新たなオフィスビル群、公園や学校、文化施設、そして店舗や住宅、ホテルなど、多様な機能を持つ街を作ります。街で使う分のエネルギーは街で作る「エネルギー消費量ゼロ」の街で、かつ車が通らない「カーフリー」を取り入れるなど、新たな試みにも挑戦しました。
有働 なぜフェイスブックが街づくりまで手掛けるんですか。
重松 いまシリコンバレーには、たくさんの企業が集中し、交通渋滞、住宅不足や家賃高騰など多くの問題を抱え、IT企業と行政の緊張が高まっています。ですから今までのように一企業に利するオフィスではなく、地域に暮らす人々と交流し、地元に還元するような新しいオフィスが求められている。アップルは3年前に新社屋を作りましたが、地域との交流を生まない要塞のようなオフィスだと批判されました。そういう先例にならないように、都市とIT企業の新たな関係性を築くことができる街にしたいですね。ニューヨークが変わった
有働 アメリカでは新型コロナウイルスの死者数が22万人を越え、再び感染者数が増えています。私たちの暮らしも在宅勤務や外出自粛など様々な変化が起こっていますが、新型コロナウイルスが都市や建築の在り方をどう変えるのか。じっくりお伺いさせてください。
重松 僕は2006年からアメリカにいるのですが、いまニューヨークを歩いていて面白いのは、感染症予防のため、レストランのテラス席が増えたり、店が売り場を歩道に広げたりしているんです。それだけで都市の体験が変わって、すごく楽しいんですよ。「やっとヨーロッパみたいな街並みになった」と喜ぶアメリカ人もいます(笑)。
有働 道の果たす役割が、コロナで変わってきたのですね。
重松 建築って、あんまり進化するイメージがないじゃないですか。例えば図書館や美術館は既にできあがったイメージがありますよね。でも、コロナで急に歩道が活用されるようになったように、テクノロジーや人々の振る舞いの変化で少しずつ進化している。僕は大学でのリサーチなどを通して、日頃から世の中を多角的に、そして仔細に観察し、建築が進化できる瞬間を見逃したくないと思っていますが、コロナは建築や都市にも「突然変異」を引き起こし、大きな進化を促しそうです。
世界が同時にパンデミックという体験を共有していることの意味も大きいと思います。例えばオイルショックは、産油国の中東にとっては「オイルブーム」。一つの事象をとっても、住む国や地域でそれだけ受け止め方が異なる。コロナほど、世界が同時に同じ課題を抱えた例はありません。コロナ禍で生まれた新たな価値観や方向性は、国境を越えて共有できるはずです。

フェイスブック新社屋のデザイン(進行中)
コロナ後の都市のキーワード
有働 不況だと建築需要は冷え込むと思うのですが、むしろコロナ禍は建築が進化するチャンス?
有料会員になると、この記事の続きをお読みいただけます。
記事もオンライン番組もすべて見放題
新規登録は「月あたり450円」から
-
1カ月プラン
新規登録は50%オフ
初月は1,200円
600円 / 月(税込)
※2カ月目以降は通常価格1,200円(税込)で自動更新となります。
-
オススメ
1年プラン
新規登録は50%オフ
900円 / 月
450円 / 月(税込)
初回特別価格5,400円 / 年(税込)
※1年分一括のお支払いとなります。2年目以降は通常価格10,800円(税込)で自動更新となります。

有料会員になると…
日本を代表する各界の著名人がホンネを語る
創刊100年の雑誌「文藝春秋」の全記事、全オンライン番組が見放題!
- 最新記事が発売前に読める
- 毎月10本配信のオンライン番組が視聴可能
- 編集長による記事解説ニュースレターを配信
- 過去10年6,000本以上の記事アーカイブが読み放題
- 電子版オリジナル記事が読める
source : 文藝春秋 2020年12月号







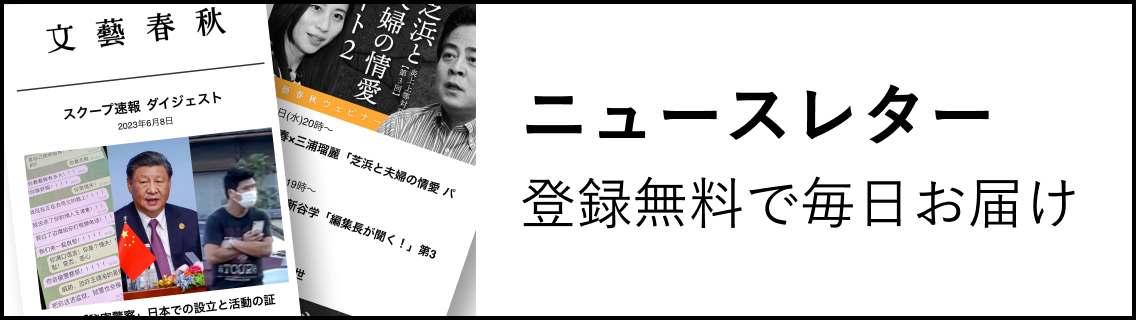
 トップページ
トップページ 後で読む・閲覧履歴
後で読む・閲覧履歴 マイページ
マイページ