
■開催趣旨
2019年以降「働き方改革関連法」の施行に基づく「時間外労働の上限規制」により、様々な産業で労働環境の整備や条件の改善が進展した。一方で、適用まで5年間の猶予が与えられている「物流業界」「建設業界」では、改善への動きが加速しているものの、長時間労働と休日労働からの脱却が不完全な状態が続いており、猶予期間が終わる2024年4月1日に向け、環境整備が急務となっている。
弊社ではこれまで「物流の2024年問題」「建設の2024年問題」をテーマに、カンファレンスを企画し、それぞれの業界における課題について多様な視点から考察をしてきた。
物流業界では「トラックドライバーの時間外労働の制限」により「担い手の不足」「労務管理によるコスト増」「事業継続」に対しデジタルを活用した業務効率化、勤務間インターバルの導入による働き方改革の徹底、人材育成、給与水準の向上など多くのチャレンジが示された。
また、建設業界においても同様に、「深刻な人材不足」が指摘され、建設技能労働者の大量退職も控えており、既存の人材に長時間労働という負荷が重くのしかかっている。また、二つ目として職場環境の課題も存在し、夏場や冬場など気候に左右される部分が多く、体調面でのケアも不可欠となっていることが指摘され、デジタル化、意識改革、政策面での整備など多くのインサイトが共有された。
そこで本カンファレンスでは、いよいよ施行まで1年半と迫った「上限規制」に向け、改めてどのようなロードマップを描き、持続可能な体制を築くかについて、2日間にわたり、それぞれの業界に焦点を当て考察をした。
■基調講演
『物流危機』を終わらせるために、克服すべき課題
~ 長時間労働是正の処方箋 ~

立教大学 経済学部
教授
首藤 若菜氏
1973年東京都生まれ。日本女子大大学院人間生活学研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。山形大人文学部助教授、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス労使関係学部各員研究員、日本女子大学家政学部准教授などを経て、現在は立教大学経済学部教授。専攻は労使関係論、女性労働論。
◎物流危機とは何か/なぜ起きたのか
運送業界は深刻な人手不足である。職業別の有効求人倍率(2022年7月時点)の「自動車運転の職業」は2.46%。職業計(平均)の1.23%よりかなり厳しい状況だ。有効求職数は、01年を1とした場合0.29つまり「なり手がいない」のである。また、21年時点での平均年齢は高齢化社会もあって大型トラック分野が49.9歳、中小型トラックが47.4歳と高く、労災のリスクも高い。物流は経済・社会インフラであるため、物流は止められない。
※本講演の各データは主に厚生労働省と国土交通省の資料より
日本では、1990年の法改正、規制緩和以降、新規参入事業者が3~4倍に増えた。その後バブル崩壊後の2000年代後半から売上高の減少と運賃の低下により退出事業者が増え、トラックドライバーの賃金水準も停滞・低下。21年現在、男性労働者の平均年収が546.4万円であるのに対し、トラックドライバーは大型が463.2万円、中小型が430.6万円であり残業が他業種に比べ多いという実態がある。
かつては「キツいが、稼げる仕事」と言われていたが、賃金水準の低下や労働時間の長さ、共働き世帯の増加による人で不足で、若年層が入ってこなくなった。特に月間の超過労働時間については、男性労働者平均が14時間であるのに対し、トラックドライバーは35時間というデータがある。労災の請求件数と支給決定件数も、「運輸業・郵便業/道路貨物運送業」は突出して多い。産業構造の変化やジャストインタイムに代表される日本的経営により積載率が低下し、高速代金や荷待ち時間料金の未払いなど荷主都合が優先される慣行も広がった。
◎物流危機への対応の特徴/2024年問題に備える
こうした状況を踏まえ、13年に国交省が発表した『総合物流施策大綱2013-2017』をきっかけに持続可能な物流を目指し、物流に携わる人材を育成する取り組みが本格化してきた。政(行政)、労(労働組合)、使(運送が記者・トラック協会)に加え、“荷主”を巻き込み、商慣行や労働時間、運賃、手待ち(荷待ち)時間の見直しなどが推進されている。
16年から「働き方改革実現会議」が開始され、17年には罰則つき時間外労働の上限規制も導入された。ただし、トラック業界については、改正労基法施行から5年後=24年に適用開始/一般則(年720時間)よりも緩い上限(年960時間)の容認、という例外が適用されている。そして、1年の拘束時間が現行の3516時間から原則3300時間となるなどの改善基準告示の見直しがある年が24年、すなわち「2024年問題」の発露である。
24年にはさまざまな見直しがあり、例えば1日の拘束時間は、「13時間を超えないものとし、最大15時間」となる。休息期間を9時間以上取り、6時間以上睡眠を取って労災を起こさないようにする配慮が求められるだろう。長時間の荷待ちをさせるなど、悪質な行為がみられる場合、荷主企業(発荷主・着荷主とも)に対し厚生労働省管轄の労働基準監督署から配慮を要請し、厚生労働省と国土交通省が情報を共有して法に基づく勧告や働きかけなどを行う。

2024年問題のインパクトとして、不足する運送能力の割合は14.2%、不足する営業用トラックの輸送トン数は4億トンと推計されている(ただし、既に約7割のドライバーと約5割の事業所は通常期は改正基準内で稼働している)。また、30年までの物流受給ギャップとして、ドライバー不足により30年には輸送能力の19.5%(5.4億トン)が不足/24年問題の影響と合わせると輸送能力の34.1%以上(9.4億トン)が不足、という推計値もある。
また、労働時間の短縮(残業の減少)が賃金の低下につながり、離職を促しより深刻な人手不足を招く可能性があることにも注意。よって賃金単価の上昇、標準的な運賃の獲得、そして24年で終わらない労働時間の短縮が求められる。2024年問題を好機と捉え、変えていけるかどうかが問われる。例えば中継輸送、共同配送、積載率上昇、パレットの利用などで、ドライバーの労働時間を短縮し、運賃を上げ、賃金を上げる──効率化と生産性の向上が必要だ。
荷主に協力願いたいこと
・パレット利用、パレットの標準化
・リードタイムの延長
・予約システムの導入
・積込先、荷下ろし先の集約
・標準的な運賃への理解……など
物流を持続させるために、荷主ができることが多数ある。
■課題解決講演(1)
物流業界が抜け出せない“ヒト“への依存
~ 「属人化した現場業務」を解消するための最善策とは? ~

株式会社スタディスト
営業部インサイドセールスG マネージャー
諸根 直史氏
新卒で国内大手物流会社に入社し、転職のベンチャー企業を含め、約9年間新規獲得セールスを経験。その後、株式会社バイブドビッツにてインサイドセールス部門の立ち上げに従事。2019年には主要5支店のインサイドセールス部リーダーを務め、約3年間で2500件を超える商談創出に貢献。20年6月より、現職である株式会社スタディストに参画。
スタディストが提供する「Teachme Biz」とは、画像と動画を用いたマニュアルを“かんたんに”作成・共有・管理できるシステム。物流を始め、小売り、飲食、宿泊、金融関連の企業2000社以上に導入いただいている。
物流業の環境は厳しい。配送ニーズの増加でドライバーにとどまらない人手不足に拍車がかかり、コスト競争は激しさを増している。物流業務の“標準化”と“省人化”、DXによる生産性の向上が必要となっており、課題として「業務の属人化」「現場の教育負担」がまずある。
組織において、ある業務のやり方や内容が特定の担当者にしかわからない状態になっていること=属人化は、業務の生産性に大きく影響する。また、現場業務が属人化していると、おのずと現場の教育負担も増大する。新人や人材が定着せず、配属や配置転換後の業務開始にも時間がかかるなど、様々な教育シーンにおいて非効率となる。特に作業種類・手順が複雑な物流業務こそ、現場業務の“属人化”は避けて通れない。解決を進めたい。

また、「標準化が困難」という課題もある。標準化にはマニュアルが有効だが、単に物流業務をマニュアル化しても標準化はできない。また、作成が追いつかない(作成時間がかかりすぎる)、更新されない(陳腐化)、現場で活用されない(誰も見ない)という現実問題もある。
画像・動画でわかりやすい/更新も共有もボタン1つ/タブレットやスマホでの利用可能、という特徴を持つクラウドサービス「Teachme Biz」を使用してマニュアルを作ると、上記の課題を解決することができる(動画あり)。文字+画像・動画+QRコード活用で、分かりやすく、業務再現性が高く、活用しやすいマニュアルが簡単に作成・更新できる。
株式会社トワードは、統一されたマニュアルで業務の標準化/現場主導で700ものマニュアルを作成&整備/現場の作業に則したマニュアルで標準化された教育、を。株式会社インテンツは、クラウド上の更新で常に最新の状態に業務を標準化/教育内容の個人差を解消し研修期間も7日間に短縮/新人スタッフの不安解消、入社後1年以内の離職率が大幅に低下、を。日本航空株式会社は、遠隔・リモートでのシステム構築にも対応/新システム操作のレクチャー時間が半減/未経験でも作業ができる、属人化が生じない環境、を、それぞれ実現した。
マニュアルは、技術伝承・教育に活用できる。教育を変えるのではなく、現場での“実践”を効率化するために、物流業の省人化・属人化を解消するとっておきのサービス「Teachme Biz」を活用して欲しい。
■特別講演(1)
物流の諸課題の解決に向けたF-LINEの取り組み
~価値ある物流品質を、ずっと。~

F-LINE株式会社
代表取締役社長
本山 浩氏
1983年 早稲田大学 商学部卒業後、味の素株式会社入社。2005年 ギフト部長。09年 味の素冷凍食品株式会社 執行役員 家庭用部長、12年 味の素株式会社 大阪支社長を歴任し、13年執行役員就任。15年 加工用調味料部長、18年ソリューション&イングリディエンツ事業部長 兼 生活者解析・事業創造部長を経て、19年常務執行役員就任。21年6月 F-LINE株式会社 代表取締役社長 就任、現在に至る。
F-LINEは味の素(筆頭株主・出資比率45%)、ハウス、カゴメ、日清製粉ウェルナ、日清オイリオグループが出資し2019年に新たに設立された物流会社。2022年4月現在、全国に11支店・69センターを持ち、「安全」と「品質」への取り組みを重視して事業を行っている。
新型コロナ流行による社会の劇的な変化もあいまって、我が国の物流が直面する課題は先鋭化・鮮明化した。今は、EC市場の急成長/新しい生活様式(非接触・非対面物流)/物流の社会的価値の再認識(エッセンシャルワーカー)を踏まえ、進展が思わしくなかった物流のデジタル化や構造改革を加速度的に促進するチャンスである。

大きな目標である持続可能な加工食品物流、スマート物流の構築に向け、“標準化”の取り組みによる物流業界の協業体制を牽引する努力を行っている。具体的には(1)納品伝票電子化 (2)外装サイズ標準化 (3)コード体系標準化 (4)外装表示の標準化。また、物流従業者の労働環境改善へ向けた足元課題=納品リードタイム延長/長時間待機撲滅/付帯作業撲滅など、の解決・地ならしや物流費マネジメント、物流オペレーションの効率化・強靱化にも着手している。
「2024年問題」が物流業界に迫っている。厚生労働省「改善基準告示」の制限(例・最大拘束時間16時間)と労働基準法上の制限(例・時間外労働の上限 年間960時間)この両方の基準を満たした、ドライバーの労働時間管理が必要となる。ポイントは(1)1日の拘束時間が11時間30分を超えない (2)納品先までの距離が150kmを超えない 、の2点と考えている。ちなみに当社のドライバーは平均月間時間外労働時間がすでに500時間を切っている。
F-LINEは「競争は商品で、物流は共同で」という基本理念を掲げ、持続可能な食品物流の基盤構築を目指す。より効率的で安定した物流力の確保と、食品業界全体の物流インフラの社会的・経済的合理性を追求する。“価値ある物流品質を、ずっと”のブランドメッセージの下、持続可能なネットワークの構築/高品質なサービスを提供する強い現場作り/人材の確保と定着/コーポレートガバナンスの強化、に取り組む。

具体例としては、北海道エリアでの共同配送(配送拠点は2カ所に集約)によりCO2排出量15%減、1日の配車台数18%減、稼働率11%増 などの実績がすでにある。九州エリアでは配送センターを福岡の1カ所に集約し、同様に3項目の数値を15%減、22%減、8%増とし、伝票も一本化した。今後も共同配送比率を極力高め、物流ネットワークを極力簡素に、効率のよいものにしていきたい。
■課題解決講演(2)
迫る「2024年問題」、転換期を迎える物流業界のリアルを紐解く
~物流業界M&Aの将来予測と再編展望~

株式会社fundbook
取締役
谷口 慎太郎氏
明治大学経営学部卒。三菱UFJ銀行を経て、ヘルスケア投資ファンドでの投融資業務、ハンズオンでの再生業務に従事。2009年に日本M&Aセンターへ入社。医療・介護・保育を中心としたヘルスケア関連企業をメインに、運送、製造、食品、ビルメンテナンス・警備、人材派遣業と多岐に渡ってM&Aを支援。17年に同社の執行役員に就任。21年にfundbookへ参画。同年6月、同社取締役に就任。
◎転換期を迎える運送業界
運送業界の課題として、(1)2024年問題 (2)ドライバー不足(高齢化) (3)後継者不在 (4)燃料費高騰 (5)事故等の偶発リスク、が顕在化している。
これらを運送業界のM&Aという観点から見てみる。運送業界のM&Aは規制緩和もあって急増しており、2009年から約10年間で年間のM&A件数が約3倍になった。ここまでは商圏進出型のミドルM&A(“地方の雄”たる運送会社の買収)が目立ち、今後も継続するだろう。また、今後は比較的小規模な運送会社の譲受(スモールM&A)が増加すると予測する。
業界の再編展望として、(1)地場の有力企業をグループに迎え入れ商圏を拡大 (2)“スモールM&A”により小回りの利く運送サービスを強化 (3)大手同士の合併による市場の寡占化、を予測する。(1)~(3)の波に乗れなかった会社は、残念ながらより厳しい経営環境の中、競争にさらされることになるだろう。
M&Aのニーズは今まさにピークを迎えており譲渡企業優位の期間は27年頃までに終わってその後は譲受企業優位となる、と我々は考える。多くの中小運送会社にとっては、今が再編のピークである。2021年の市場規模は約19兆円で、上位10社のシェアは31%。市場規模が同じ19兆円と仮定すると、スモールM&Aや大手同士の統合により2030年には上位10社のシェアは50%に達すると予測する。譲渡機会は毎年約40~50社のみの狭き門だ。
では、単独で大手と勝負することは可能なのか? (1)ドライバー確保のコスト (2)燃料費の高騰 (3)価格転嫁の困難さ、が重くのしかかる。とくに(3)は大きな課題で、価格交渉力が今後非常に重要になるだろう。つまり、単独での勝負は実際には極めて難しい。大手にグループインすると、売上高1000億円の大手運送会社と同20億円の中小運送会社でのシミュレーション例で、大手運送会社へのグループインにより年間2500万円の利益改善に繋がる、という試算がある。課題を解決し価格交渉力をつけるには強いところと組むしかない。あるいは合従連衡し大きなグループを自分たちで作り出していくしかない、と考える。
◎まとめ
運送業界の現実は
(1) 大手による運送業界の再編は急速に進行
(2) 近い将来に中小運送会社を待ち受ける厳しい市場環境
(3) 大手へのグループインは有力な選択肢のひとつ
子供、親族を含む、経営能力や胆力のある後継者がいるかどうかも熟慮したい。
中小企業のM&A成長戦略としては、
(1) 地場圏域内での合従連衡策を真剣に考える
(2) 中間地点・発着地点での買収戦略をマイクロに考える
(3) バリュエーションは頑張って欲しい、それが難しければスピード!
PMI※は丁寧に。噂はあっという間に広がる
※PMI=Post Merger Integration、M&A後に行われる統合プロセス

fundbookは、アドバイザーと独自開発のfundbook cloud(M&Aプラットフォーム)を掛け合わせた独自のサービスモデル。アドバイザーの能力に左右されがちな属人的なM&Aの世界を変え、透明性の高いフェアなM&Aを実現する。M&Aに興味のある方はご連絡・登録をいただきたい。
■課題解決講演(3)
人材不足時代の健康管理の始め方
~過重労働による従業員の健康リスクを防ぐ~

メディフォン株式会社
産業看護師/第一種衛生管理者
政門 那美氏
看護師として大学病院の内科混合病棟にて心疾患や糖尿病、膠原病などの患者対応業務に従事。その後、看護師問診や海外赴任向けの予防接種を行っている医療機関に転職し、日々の生活の中で疾患と付き合いながら仕事を続けている方、コロナ禍において不安や緊張・不眠などに悩んでいる方などと接する。これらの経験を通して、予防医療やグローバルな医療提供の重要性を感じ、メディフォンに入社。現在は、産業看護師として健康管理システム「mediment」のオペレーション業務やコンテンツ企画を担当
◎運輸業界の現状/運輸業界のドライバーの健康リスク
運輸業界の総就業者数は330万人。日本国内の輸送荷物の9割はトラック輸送だ。就業者は40歳以上がほとんどを占め、労働時間は全産業の平均より約2割長い。これが現状であり、2024年から労働時間の上限規制が始まる。
※本講演の各データは主に厚生労働省と国土交通省、農林水産省の資料より
人材不足も問題。道路貨物運送業の運転従事者は、1995年からの20年間で21.3万人減少し、2030年までの15年間ではさらに24.8万に減少するという日本ロジスティクスシステム協会の予測もある。また、2021年度の「道路貨物運送業」の労災請求/支給決定件数は、脳・心臓疾患関連が155件/59件で全産業最多である。
健康問題に積極的に取り組むことが急務だ。リスクが高い従業員への対策と、様々な事故防止への、企業・業界全体での取り組みが求められる。疲労の蓄積による、脳・心臓疾患/精神障害・自殺/その他の過労性の健康障害/事故・ケガ、いずれも防がなければならない。健康診断結果/ストレスチェック結果/勤怠情報/各種産業医面談記録、といった情報を把握・保存することが大切だ。

ドライバーは、脳・心臓疾患発症のリスク要因となる高血圧、脂質異常症の有所見が多い。実際に心臓疾患や脳疾患および意識障害は重大事故の要因となっている。例えば糖尿病のドライバーは、低血糖による意識消失の危険/高血糖による昏睡の危険/合併症の神経障害によるアクセルやブレーキの操作感覚の鈍麻⇒交通事故のリスクがある。
SAS=睡眠時無呼吸症候群も、同様に交通事故リスクが高い(健常者の約7倍)。経営者は従業員と共にメタボリックシンドローム/糖尿病/心臓疾患/睡眠障害などを把握し、回避しなければならない。
◎重大な健康問題の発生を防ぐための検診結果の活用方法
従業員の健康診断の事後処置/リスク管理/健康観察/健康管理対策、は経営者にとって必須。例えば、運転中に体調不良になった際のマニュアルを整備したり、日々や出勤時の血圧管理、健康診断結果の経年変化の確認、要治療者(ハイリスク者)の発見などに注力したい。

労災のリスクを予見するために、特に先述の脳・心臓疾患のリスクの確認が重要だ。脳梗塞・心筋梗塞のリスク診断に有効な「LOX」は実施をお勧めする。また、直近の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する4項目=血圧/血中脂質/血糖/肥満について以上の所見があると診断された時に必要な精密検査や特定保険指導を受けることができる「労災二次検診」(全額公費負担)を利用し、従業員負担を減らしたい。
ドライバーに対し要再検査や要治療の判定があったり、持病・治療中の疾患がある場合は、産業医に乗務の可否・業務時の配慮事項を確認することも大切だ。健康に起因した事故を防止するための対策(トラック協会の各種マニュアルのダウンロードなど)、助成金(ドライバー等安全教育訓練促進助成制度など)の活用、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度利用も推奨する。
◎まとめ
・運輸業の労災は多く、その原因である長時間労働や不規則勤務は問題視されている
・健康障害は労災の原因でもある、脳・心臓疾患が多く、検診の有所見率でも血圧や脂質異常症での有所見率は高い
・健康管理は、業務開始時のアルコールチェックと一緒に体調チェックも必須
・ハイリスク者から二次検診や通院フォローをしていく
■特別講演(2)
SEINO LIMIT ~限界からの解放~
~ 新スマート物流による社会課題解決型ラストワンマイルへの挑戦 ~

セイノーホールディングス株式会社
執行役員 ラストワンマイル推進チーム
河合 秀治氏
西濃運輸株式会社に入社後、トラックドライバーとしてキャリアをスタートし、トラック輸送の現場を経験。業務改善等各種プロジェクトを経て、社内ベンチャー、ココネット株式会社を2011年に設立し、後に社長に就任。同社は「買い物弱者対策」として、食料品のお届けなどのラストワンマイルサービスを全国展開。現在は、セイノーHD執行役員ラストワンマイル推進チーム担当、複数の事業会社の役員を兼務し、社会課題解決型ラストワンマイルの構築を推進。直近では、狭商圏オンデマンド配送サービス「スパイダーデリバリー」、処方薬即時配送サービス「ARUU」、ドローン配送サービス「SkyHub」をローンチ。
ビジネスのアプローチとして「業界課題+社会課題」×オープンイノベーション、O.P.P.(オープン・パブリック・プラットフォーム)を掲げている。O.P.P.とは「同業他社や地域と連携し、開放的で公共性の高い物流プラットフォームを構築することで、利用者それぞれの効率化や価値向上、さらには社会インフラとして産業・環境・生活への貢献と、効率向上の実現を目指す構想」である。

トラック運送業は、事業者数が多い上に中小企業率が99.9%と、IT導入やDXが進みづらい環境にある。また、本日の今までの講演にあったように、業界や運転従事者の数・平均年齢には課題が山積している。貨物自動車の積載率はいまだに40%を切っており“空気を多く運ぶ”状況は改善されていない。その一方で、EC市場の拡大により宅配便取り扱い実績は2021年までの5年間で23.1%増加し、再配達率も11%台に高止まりしている。
※データは主に経済産業省、国土交通省、農林水産省の資料より
ドライバーの数が減り荷物が増え、働き方改革も進めなければならないという環境においては、運送事業者およびドライバーの生産性を高める必要がある。そこで、社会課題解決型ラストワンマイル『新スマート物流SkyHub®』を考案・推進している。先端テクノロジ×デジタル基盤⇒地域の社会課題解決、を目指す。
過疎地域を含む市町村の割合は、51.5%に達している(東京23区を除く全国1718市町村のうち885が過疎地域)。過疎地域は既にマジョリティであり、増加傾向にもある。課題は、買物/医療/物流3つの“難民”救済と自然災害対策。迅速に解決しなければ地域コミュニティの存続自体が危うい、地方消滅待ったなしの状況だ。
共同配送・貨客混載のサービスの実装実験を山梨県小菅村で行っている。西濃運輸ほか物流業界全体でのO.P.P.構築により、大月駅からの路線バスや、ドローンも活用して荷物の集約・混載を促進、トラック台数・配送距離・移動距離の減少により二酸化炭素排出削減にも貢献している。「ドローンデポ®(倉庫)」「ドローンスタンド®(離発着設備)」を整備し、実際にサービスを提供している。
「SkyHub®」と名付けたアプリを小菅村を皮切りに複数地域で導入。ドローン配送により家から出ずにスーパーで買い物ができたり、病院に行かずに処方薬を入手できるようになっている。全国規模でのドローン配送の社会実装に向け、2021年度は神奈川県、北海道、福井県など各地合計で国内トップの飛行回数466回、飛行距離1730kmを実現した(動画あり)。小菅村ではドローン配送がすでに日常になりつつある。なお、内閣府が推進する「デジタル田園都市国家構想」参考事例にも採用された。

冒頭に述べた「業界課題+社会課題」×オープンイノベーションに、我々が推進するこの新スマート物流をなぞらえると「環境負荷低減+過疎地域」×エアロネクスト社(ドローンスタートアップ)/自治体、というアプローチになっている。課題解決のためのオープンイノベーションであり、現地の人や事業者との協業・連携により課題解決のスピードを上げていきたい。
その他のラストワンマイル対策。ココネット社での買い物弱者に向けたサービスを提供したり、LOCCO(ロッコ)社でアプリ利用による非接触、安心・確実のwithコロナ時代の宅配・置き配を実施したり、処方薬即時配送サービス ARUU(アルー)を実現している。モノの移動とヒトの移動双方を精査し、総合的な生産性や環境負荷を鑑みてモノが動くかヒトが動くかを判断していく必要があると考える。各自治体や地域、同業社や技術を持つ多方面の事業者とオープンに連携して、さまざまなラストワンマイル物流への取り組み、過疎地域対策を進めたい。
2022年12月6日(火) オンラインにて開催・配信
source : 文藝春秋 メディア事業局







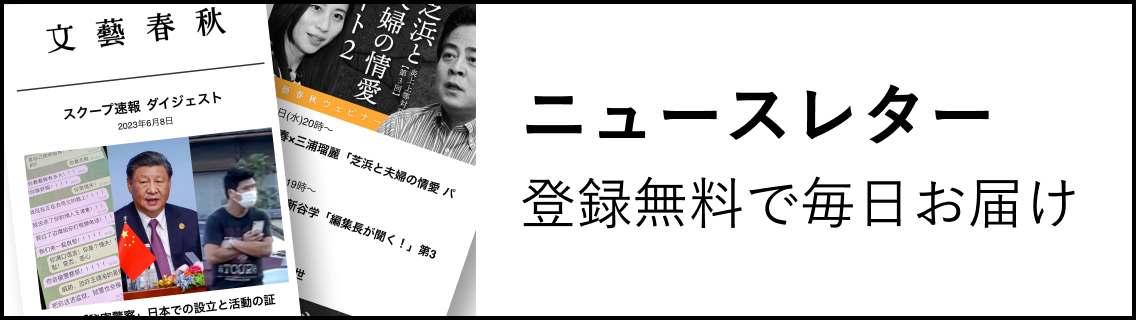
 トップページ
トップページ 後で読む・閲覧履歴
後で読む・閲覧履歴 マイページ
マイページ