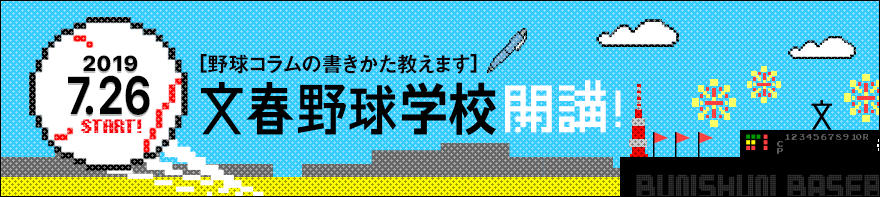(来年もユニフォームを着続けることは難しいのかな……)
初めて、そんな思いを抱いたのは2018(平成30)年夏のことだった。この年から監督は変わり、首脳陣も一新された。シーズン前半こそ一軍にいたけれど、若手の台頭やチーム事情もあって、なかなか一軍に呼ばれることのないまま時間だけが過ぎていった。
「チームが2位に躍進し、クライマックスシリーズ進出を決めた時点でも、やっぱり一軍からは声がかかりませんでした。僕は足が速いわけでもなく、守備がうまいわけでもなく、チームに貢献できるとしたら、《右の代打》という役割でした。年齢から考えても、本来ならば代打の一番手でなければいけないのに、僕には声がかからない。その時点ですでに、“今年限りだな”と覚悟はしていました……」
目の前にはスーツ姿の鵜久森淳志が座っている。朝早くからラッシュアワーの満員電車に揺られ、終電近くまで仕事に忙殺される日々を過ごしているという。尋ねたのは、「現役引退を決めた経緯」、そして「戦力外通告を受けた経緯」だった。
「球団から連絡が来たのは10月に入ってすぐでした。自分の置かれている状況はわかっていましたから、“あぁ、やっぱり呼ばれたか……”というのが最初の感想でした。この時点では、“まだやりたいな”と思っていました。プロ14年目でしたから、“15年間はプレーしたい”と思っていたんです。でも、ヤクルトではもうプレーはできない。だから、他球団でのプレーを考えていました。いろいろな考え方があると思うけど、僕はNPBで現役の最後を終えたかったんです」
もしも独身だったら、独立リーグや海外でのプレーも考えたかもしれない。しかし、家族を支える大黒柱としては、どこかで区切りをつけねばならない。鵜久森は合同トライアウトにすべてをかけることにした。……いや、すぐに「トライアウト受験」を決意するに至ったわけではなかった。
「現役続行を望んではいたものの、実はトライアウトを受験するつもりはありませんでした。というのも、各球団の編成の方々だって、常に他球団の動向をチェックしていますよね。当然、僕の実力や現状だって、きちんと把握されているはずです。だから、トライアウトは受験せずに、他球団からの連絡を待とうと思っていたんです。でも、嫁さんに、“どうして受けないの?”と言われました。僕自身はSNSはやっていないんですけど、妻のSNSの下に、ファンの方から“ぜひトライアウトを受けてほしい”というメッセージが寄せられていたようです」
悩んだ末に鵜久森は、「自分のために」ではなく、「ファンのために」トライアウトを受験することを決意する。
「家族のために、ファンのために」トライアウトを受験
14年間のプロ野球人生を振り返ったとき、「自分はたいした成績も残していない」という思いが強くある。近年では「とらえた」と思った打球がフェンス際で失速する現実にも気がついていた。それでも、自分に声援を送り続けてくれた熱心なファンの存在もきちんと理解していた。本心では「もう、どこのチームも拾ってはくれないだろう」と思いつつも、「ファンの方が納得できるような最後を見せたい」という思いが、彼の胸の内に芽生えていた。
ここ数年は代打起用がほとんどで、常に「1打席勝負」だった。しかし、トライアウトならば誰もが平等に4打席バッターボックスに立つことができる。鵜久森は決意する。「最後に4打席立つ姿をファンの方に見ていただいて、これを最後としよう」、と。こうして迎えたのが、18年11月13日、タマホームスタジアム筑後で開催された合同トライアウトだった。若干の緊張とともに迎えた第1打席、マウンドに立っていたのはDeNAから戦力外通告を受けていた須田幸太だった。
「甲子園で対戦したのも須田投手で、ヤクルトでサヨナラ満塁ホームランを打ったのも彼からでした。そんな因縁を感じながら打った打球はセンターに飛んでいきました。あの打球を打ったときに、完全に吹っ切れました。今までなら、あの打球はさらに伸びていたんです。自分の中では会心の当たりでしたから。でも実際は失速したセンターフライ。“あぁ、オレはもうこういう打球しか打てないんだ……”と思ったときに、覚悟を決めました」
第2打席は三振、第3打席、第4打席はともにフォアボールに終わった。これが鵜久森にとってのトライアウトのすべてだった。すべてが終わった瞬間、「他球団から声がかかることはないだろうな」と自覚していた。奥さまは「まだまだ続けてほしい」と願っていることは理解していたけれど、この瞬間にはすでに、「次の人生、何をしたらいいのかな……」と、鵜久森は考えていた。