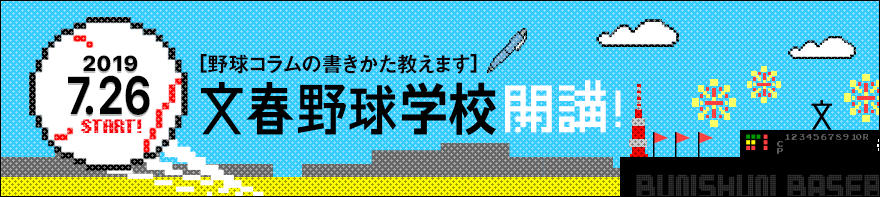試合中に東京ドームのベンチ裏通路を通ると、ビジターチームのリリーフ投手が軽く体を動かしていることがある。バランスボールに乗ったり、マットを敷いてストレッチをしたり……。狭いブルペンの中ではやりにくい運動をしながら、出番を待っているのだ。あるとき、ゲーム中に通路を通りがかったら顔見知りの投手と目が合ったので、少しだけ立ち話をした。その投手はひと月ほど前に1軍に昇格すると、勝ち試合でも負け試合でもマウンドに送られ、ものすごいペースで登板を重ねていた。
「疲れてるみたいだけど大丈夫? きょう投げるの?」
「いやエグイ。人使い荒いわ。きょう投げるか? って中(継ぎ)なんだから分かるわけないやろ(笑)」
僕の間抜けな質問に口ではもううんざり、みたいなことを言っていたが、その表情は明らかに誇らしげだった。プロ野球選手は使われてナンボ。周囲が酷使を心配しているようなときでも、選手本人は喜びを感じていることが多いように思う。
ちなみに、TT兄弟や和泉元彌のモノマネネタで大ブレーク中のお笑いコンビ、チョコレートプラネットの長田庄平は7月上旬まで171連勤だったらしい。さすが吉本興業……ということが言いたいのではない。一般の企業でも、仕事のできる人間にいろんな案件が集中して大きな負担をかける、ということは日常茶飯事だ。旬の時期に酷使する、というのはどの世界でも似たようなものなのだろう。ただ、あまりの負担に心のバランスを崩す、ということはあるにせよ、会社員やお笑い芸人はいくら酷使されても職業人生を絶たれるような致命的なダメージを負うことはそうそうあることではない。だが、プロ野球の特に投手に関しては、酷使と選手生命は密接に関係している。
オールスターを挟んでいたが……田口の“10連投”について考える
快調に首位を独走してきた巨人は5年ぶりのV奪回に向けて、踏ん張りどころを迎えている。前回の監督時代はバランスの取れた巨大戦力にのびのびとプレーをさせる「馬なり采配」も目立った原監督だが、今季は復帰初年度という気負いもあるのか、ムチをふるいまくりという感じで、ゲーム差ほどの余裕はないように思える。象徴的なのが中継ぎに回った田口の“10連投事件”だ。リーグトップタイ、球団史上初の10戦連続登板。田口自身も「まだ23歳なのでこれぐらい投げないと」と気丈に話しているそうだし、オールスターを挟んでいたので数字ほどの負担がかかっているとは言えないかもしれないが、なかなか見ないレベルの酷使ぶりであることは間違いない。
これ以上使ったら壊れてしまうんじゃないか、なんで毎年のように故障者が出ているのにこんな偏った起用をするんだよ……。ファンの立場からはいろいろ言いたくなるのは当たり前だが、流行語にもなった王監督の「ピッチャー鹿取」の時代から、リリーフピッチャーは酷使されがちである。そして、先発完投がかなりのレアケースになった現代野球では、リリーフ陣の質と量が以前にもましてペナントのカギを握る。
だからリリーバーの酷使は信頼と依存の証なのだ。信頼していなかったら使わない。そして信頼できる投手がたくさんいることはほとんどないので、一部に負担が集中する。
酷使してくる監督とまったく使ってくれない監督。選手にとってありがたいのは圧倒的に前者だ。だからある種の共犯関係が成立する。
選手は体がきつくなっていても、行けと言われれば投げてしまう。使う側もけなげに頑張る選手に甘えて使ってしまう。
使う側だって元プロ。酷使が故障のリスクを増やし、選手生命を縮める可能性を認識している。それでも、少しでも勝てる可能性がある試合ならば、最善手を打ちたい。多少無理して勝ちに行かないと、目の前の1勝を勝ち取ることができないというのが残酷なまでにレベルが高まってしまったプロ野球の世界だ。だからいいピッチャーであればあるほど、その投手への依存度は高まる、という構造がある。