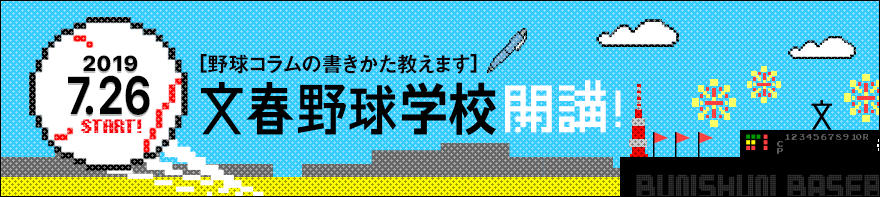もしも、ハフとマクガフがいなかったら……
それにしても、ハフとマクガフがいなかったら、今年のヤクルトは一体、どうなっていたことだろう? 現在、二ケタ台の借金にあえぎ続けるヤクルトだが、たとえ16連敗を喫しようとも、「他球団も団子状態だ。まだCSを狙える位置にいるぞ!」と、半ば妄信的な希望という名の願望を持つことができているのは、中継ぎ投手陣の懸命な奮闘のおかげである。
その中でも、特に2年目のハフと今季からスワローズの一員となったマクガフには頭が上がらないし、足を向けて寝ることができない。冒頭に掲げた「ハフとマクガフがいなかったら?」と考えるだけで恐ろしい。だから、あまり考えないようにしているのだけれど、ついつい「ハフさん、マクガフさん、くれぐれもご自愛ください」と祈る気持ちを止めることができないでいる。
何しろ、7月24日、91試合消化時点でハフの登板は47試合、一方のマクガフは46試合。開幕当初、両者は主に勝ちパターンでの「勝利の方程式」に登場していたものの、5月中旬からの泥沼の連敗以降は、少々のビハインドの場面でも登場することが多くなってきた。守護神・石山泰稚の離脱以降、マクガフがクローザーを務めることにもなった。ハフとマクガフの獅子奮迅の活躍に、いくら感謝してもし足りない。そんな日々が続いている。
古い話で恐縮だけれど、ヤクルトにおける「助っ人投手陣の系譜」を振り返ってみると、あまりいい思い出がない。僕の頭に真っ先に浮かぶのが、1989(平成元)年に在籍していたホアン・アイケルバーガー。クローザーとして期待されながら、開幕第2戦目の巨人戦でのサヨナラ暴投は80年代低迷期の象徴的な出来事として、今も脳裏に焼き付いている。彼はその後も満足な投球を披露することなく、早くも5月には解雇された。
アイケルバーガーに代わって入団したのがロン・デービスだった。彼もまたピリッとしないまま、この年限りで自由契約となった。蛇足ではあるけれど、彼の背番号は、まさかの《27》。ヤクルトにおける「正捕手の正統番号」をつけた唯一の投手であり、この翌年から背番号《27》を背負うのが、かの古田敦也なのである。
また、この時期に在籍していた助っ人投手が郭建成だった。それまで、中日の郭源治、西武の郭泰源と、「台湾出身の郭」と言えば、超優良助っ人ばかりだったので、僕は大いに期待したものだが、まったく結果を残せず、0勝のまま3年で故郷に帰ることになる。またまた蛇足だけれど、その後、郭建成は台湾球界で野球賭博にかかわり、実刑判決を受けることになる。
アイケルバーガー、ロン・デービス、郭建成以外にも、「残念助っ人投手」はまだまだいる。「中日の小松崎善久と乱闘した男」、ティム・バートサス(91年)、シーズン途中に解雇されたフロイド・バニスター(90年)、「呂明賜に初ホームランを打たれた男」としてしか記憶されていないボブ・ギブソン(88年)、独特なフォームでフォアボールを連発するアンディ・ビーン(85年)など、ヤクルトにはろくな投手がいなかった。
それからかなりの時間が経ち、チームの優勝に貢献したテリー・ブロス(95~97年)や、ケビン・ホッジス(01~03年)、「ブラピに似ている」と話題になったジェイソン・ハッカミー(99~00年)、最多勝を獲得したセス・グライシンガー(07年)、先日のドリームゲームにも登場した林昌勇(08~12年)らが登場するまでは、「ヤクルトの助っ人投手」というのは、パッとしない顔ぶればかりだったのだ。