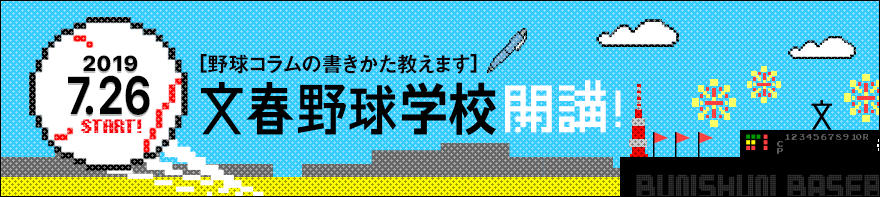今もなお記憶に残る池山の引退試合
今でも忘れられない光景がある――。2002(平成14)年10月17日、前日の観衆は公称5000人だったが、この日は4万5000人が神宮球場に詰めかけていた。その多くがプロ19年目を迎えていた池山隆寛の引退試合を見るためだった。観衆のほとんどは彼の最後の雄姿を目に焼きつけるために集まっていたのだ。
長年、神宮球場に通い続けているけれど、この日ほど人でごった返していたことはなかった。コンコースはもちろん、スタンド通路にまで人があふれ、ビールの売り子も自由に行き来するすることができず、売店では弁当類も早々に売り切れていた。通路に座り込んだ人々を避け、ようやくたどり着いたライトスタンドの最後方。二重三重に折り重なる頭と頭の間から、わずかに広がるグラウンドに目をやる。僕らはみな、池山の最後の姿を目に焼きつけようと、固唾を呑んでいた。
試合中から彼は泣いていた。そして、観客もまた泣いていた。8回の第四打席で放った左中間を破るツーベース。一塁を回るときから右脚をひきずり、ようやくたどり着いたセカンドベース上で膝をさする姿。あるいは、延長10回表、広島・新井貴浩の打球を身を挺して好捕する姿。それは、脚が万全の状態なら、正面に回りこんで難なく捕れた当たりだった。こうした彼の最後の雄姿に、観客はますます胸を熱くする。
広島の1点リードで迎えた延長10回裏。ランナーが一人出ればもう一度、彼に回る。一死後、飯田哲也はセーフティバントを試みると、気迫溢れるヘッドスライディングでファーストに生きた。続くバッターは稲葉篤紀。観客の誰もが思っていたはずだ。「ゲッツーにはなるなよ。とにかく池山に回せ!」と。そして、こうも思っていたはずだ。「サヨナラホームランなんて打つなよ」、とも。
このとき、稲葉の選んだ策が飯田に続くセーフティバントだった。ボールを転がしさえすれば、最悪でも犠牲バントになる。必死になって一塁を目指す稲葉。彼もまたヘッドスライディングを試みる。セーフにはならなかったものの、何とか一塁に生きようとするその心意気は4万5000の観客の胸にしっかりと届いた。こうして迎えた、池山の現役最終打席。球場の盛り上がりは最高潮を迎えていた。
一球目は空振り。続く二球目。もう右脚の踏ん張りが利かないのか、態勢を崩して倒れこむ渾身の空振り。そして、最後の一球。堂々と直球を投じる広島・長谷川昌幸。同じく渾身の、そして豪快なスイングを繰り出す池山。三球勝負、スイング・アウト。通算1440個目の三振。これは、世界の王貞治をも上回る記録だ。かつての代名詞「ブンブン丸」。その名に恥じない見事なスイングだった。
懐かしの「池山メッセージCD」を引っ張り出す
ときは流れて今年の7月――。ヤクルト球団50周年の節目の年に行われた「ドリームゲーム」に「ブンブン丸」こと池山隆寛が神宮球場に戻ってきた。試合開始前から小雨が降り注ぐあいにくの空模様ではあったが、ユニフォーム姿の池山には天性の華があった。彼が登場するだけで、一気に周囲がパッと明るくなるようなスターのオーラは健在だった。
この日の池山はとても元気だった。打席に立っても、ショートを守っていても、観客の視線を一瞬で惹きつける天性の華は健在だった。彼の姿を見ていた小川淳司監督が、心の底から感嘆するように「池山のスター性は相変わらずですね」とつぶやいたことが、今でも印象に残っている。また、先輩である八重樫幸雄氏は、池山を評して、こんなことを言っていた。
「イケの場合は、若い頃の《ブンブン丸》のイメージが強いから、どうしても豪快だけど脆いバッターって印象が強いかもしれないけど、中堅からベテランになる頃には、野村ID野球をしっかりと身につけた理論派バッターなんだよ」
この言葉を聞いて、僕は嬉しかった。と同時に、雨の降るレフトスタンドから池山の姿を見ていて、「またヤクルトに戻ってこないかな……」と僕は思っていた。そして、まさかこんなに早く古巣に戻ってくるとは思いもしなかった。天性の華を持った生え抜きのスターがヤクルトに帰ってくる。こんなに嬉しいことはない。池山の二軍監督復帰が決まるやいなや、僕は書庫に行き、一枚のCDを引っ張り出す。
目的のモノはすぐに見つかった。僕の手元にあるのは、『3冠のうちの1つは必ず取る! ツバメ軍団の主砲 池山隆寛』と題されたメッセージCDだ。説明書きによると、ユマキャンプに旅立つ前日の92年1月30日、神宮球場のクラブハウスで収録が行われたという。当時、26歳になったばかりでプロ9年目を迎えようとしていた、まさに脂の乗り切った時期にあった。懐かしい思いを抱いたまま、CDをセットする。聞こえてきたのは、若き日の池山の声だった……。