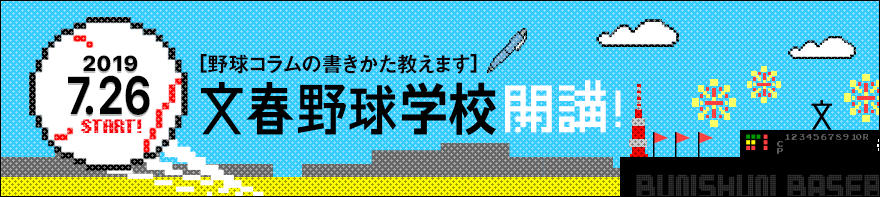高津監督が選んだ「回跨ぎ」という作戦
高津臣吾監督が選んだのは「回跨ぎ」という起用法だった。6月26日、神宮球場で行われた対巨人戦。5対4とヤクルトの1点リードで迎えた8回表二死2塁。この場面で、高津監督はクローザーの石山泰稚を投入する。本来ならば9回に登場するはずの石山を早めに登板させることを選択したのだ。
ここで石山は八番・大城卓三を三振に打ちとり、巨人の反撃の芽を摘んだ。必死の継投策が功を奏したのだ。そして注目の9回表、ヤクルトのマウンドには再び石山が上がる。8回に引き続いての、いわゆる「回跨ぎ」だった。
かつてはリリーフ投手が複数イニングを投げることは、まったく珍しいことではなかったが、完全分業制が徹底されている現代野球において、リードしている終盤での「回跨ぎ」は圧倒的に少なくなった。ピンチを切り抜けた後、新たに気持ちを作り直して再びマウンドに上がることはとても難しいのだという。
しかし、高津監督は石山に「回跨ぎ」を命じた。これが、野手出身監督ならば、「投手心理を理解していない」との批判が起こる選択だったかもしれない。しかし、現役時代には盤石のクローザーとしてヤクルト黄金時代の立役者となり、日本のみならず、アメリカ、韓国、台湾でも活躍した高津が採った作戦だ。投手心理、クローザーの難しさを誰よりも熟知している指揮官の選択だ。「回跨ぎ」の難しさを重々理解した上で、「石山なら大丈夫だ」と判断したのだ。
しかし、結果的に石山は打たれた。チームはまさかの逆転負けを喫した。先発で好投していた石川雅規の今シーズン初白星も消えた。当初の目論見では「8回・マクガフ、9回・石山」だったのだろう。ところが、8回から登板したマクガフの投球は本調子にはほど遠かった。そこで、指揮官はこの回途中で石山にスイッチした。1点差だからこそ、もっとも信頼できる投手を選択したのだろう。それでも結果は出なかった。それが、厳然たるこの日の現実だった――。
誰よりもクローザーの重責を知る男
2003(平成15)年4月23日、当時現役だった高津は佐々木主浩の持つ日本記録を更新する230個目のセーブを挙げた。試合後のインタビューで、彼はこんな言葉を残している。
「抑えをやっていて辛いことばかりでした」
この言葉について、後に本人が補足する。
「クローザーというのは本当に辛いんです。辛さを表に出せないのも苦しいんです。もちろん、その分抑えたときの喜びは大きいんですけど、やっぱり辛いポジションなんです」
かつて、高津は自著『ナンバー2の男』(ぴあ)において、こんな発言を残している。
「プロ野球の世界は普通の精神状態では戦えないし、特にリリーフピッチャーは精神力が要求されます。日本では、クローザーは3年くらいで通用しなくなるんですけど、故障やケガだけじゃなくて、精神状態をキープするのは大変なんですよ。あっけらかんとした性格でもダメだし、考え込む人には向いていない。自分の精神状態を微妙に調整しながら戦うこと、日々の感情をコントロールすることが難しい」
このように解説した上で、高津は「抑えがもたらしてくれたもの」を語る。
「ただ、そういうつらさがあったからこそ、人間的な部分が成長していったんだと思う。だから、抑えのポジションに抜擢してくれた野村さんには本当に感謝してます。野村さんには『人間的に成長しなさい』『社会人として自立しなさい』とずっと言われてましたけど、それに対する答えは出せたと思う」
「本当に辛い」ポジションであり、「精神状態をキープするのは大変」ではあるものの、だからこそ、「人間的な部分が成長」できるのが、抑えというポジションなのだ。その重責を誰よりも知る男が、2020(令和2)年のクローザーに指名したのが石山泰稚だった。