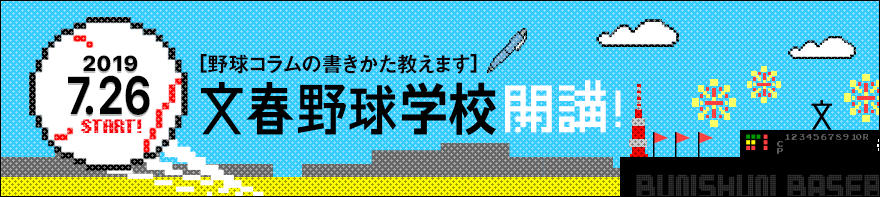25年前の5月、20歳の僕は初舞台に臨んでいました。「ビビる」というコンビを組んで、所属事務所のお笑いライブに出たのです。いやー最初の舞台はウケなかったですねぇ。先生役と生徒役に分かれて学校コントみたいなものをやった気がするのですが、まだオリジナリティも何もない。お客さんからの投票が3票しか入らなかったのをよく覚えています。
当時のナベプロはまだお笑いセクションの黎明期。ネプチューンさんが世に出ていく直前という感じで、ホンジャマカさんぐらいしかちゃんとご飯を食べられているタレントがいなかった。だから入ってきた新人はどんなやつでもすぐに舞台に立たせていました。プロとしてこの世界でやっていこうと思うなら、まずは金を払って見に来てくれるお客さんの洗礼を浴びろ、という方針だったんですね。その結果、ほとんど全員が滑るので、次回からごそっといなくなる。僕たちはなんとなく通い続けて、なんとか自分の居場所を見つけていったという感じでした。
僕が初舞台を踏んだ5カ月後、東京ドームで引退試合に臨んだのが原辰徳監督です。広島の紀藤真琴投手から現役最後のホームラン。さらに、最終打席では長年しのぎを削った大野豊投手が登板するカープの粋な計らいもありました。
自分がデビューした年に子どものころから応援してきた原さんが引退するということで、何とも言えない気持ちになったものです。持ちネタである「こんばんみ!」が生まれたのもちょうどこのころ。ライブの告知コーナーなんかで「こんばんみ! ちょっとお知らせでーす」みたいにやっていたのがいつの間にか定着していきました。
原さんを見て学んだ「プロ」の厳しさ
現役時代の原さんはONと比べられ、上の世代から厳しい目を向けられ続けるという宿命を背負っていました。巨人ファンだったうちの親父もよく原さんに対する物足りなさを愚痴っていたものです。「原は勝ってる時にしか打たない」「こういう時に長嶋は打った、王は打った」……etc。僕はONの現役時代を見ていないからそう言われてもわからない。それに、成績を見ると原さんは3割30本を何回もやってる。子ども心に「原さんの何がダメなんだ」と憤慨していたのを思い出します。
僕からしたら、なんといっても4番を1000試合以上打った大スター。中畑清さんも「大木ちゃん、俺は辰ちゃんが来たおかげで三塁から一塁に行かされたんだ」なんていまだに言ってますからね。僕が「でも清さん、そのおかげで何回もファーストでゴールデン・グラブ賞取ったじゃないですか(※1982年 - 1988年に7年連続受賞)」とフォローしたら「大木ちゃんいいこと言うね! そういうことなんだよ!」と笑ってましたけど。「そういうこと」ってどういうことなんだというね。
原さんは当時レコードも出してて、A面が「どこまでも愛」、B面が「サム」ですよ。サムっていうのは愛犬の名前(!)。いま野球選手が愛犬の歌を歌ってもだれも聞いてくれないでしょう! それぐらいあのころの巨人の4番、原辰徳のパワーはすごかった。
そんな原さんを見て「プロ」というものの厳しさを学んだところもあります。原さんの現役生活の晩年、「代打・原」のコールで東京ドームがすごく沸いたことがありました。そのとき、解説の江本孟紀さんがこんなことを言いました。
「ベンチスタートが当たり前になって苦しんでいる原を応援するというファンの気持ちはわかる。でも、本当はバリバリのころから出てきただけでこれぐらいの歓声をもらわないといけない。それがプロなんだ」
まあバリバリのころも「4番サード原」のコールで球場は沸いていたような気がしますが、「同情の拍手より期待の拍手をもらえ」というエモヤンの言葉にはハッとさせられました。駆け出しだった僕は、プロってそういうことかと感じましたよね。
このころには「代打カズシゲ事件」というのもありました。チャンスの場面で原さんに代打長嶋一茂。見ている側からすると、「代打一茂ってあるの?」とびっくりです。「俺よりも調子が良いから」とプロらしく気丈に振舞っていた原さんですが、胸にはいろんな思いがあったでしょう。現役時代の原さんには白い歯がきらりと光る笑顔と、苦しんだ4番という二つのイメージがあります。