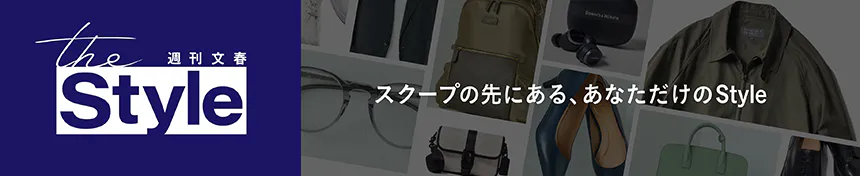なにもユネスコが無理難題を突きつけているわけではない。こうして地域全体の景観を規制し保全することは、日本ではごく一部の地域で局所的に行われているにすぎないが、たとえば欧米では、ごく常識的に行われている。ユネスコはグローバルな視点を提示しているにすぎない。
イタリアを例に挙げよう。イタリアでは1939年に施行された文化財保護法、自然美保護法で、歴史や伝統および自然美の観点から景観を保護すべく定めたが、対象外の地域では景観を損ねる開発も行われた。そこで国土全体の景観を保護するために、1984年に告示されたのがガラッソ省令だった。
なぜイタリアの景観は美しいのか
一例を挙げれば、すべての海岸線や湖沼岸の水際線から300メートル以内の地域は、開発が規制された。そのうえで1985年、この省令を立法化する案が国会に提出され、ガラッソ法が成立した。
法によって省令で定められた規制地域がさらに拡大され、景観上重要な地域内に、建築などを一時的に禁止できる区域を定める権限が州にあたえられた。また、すべての州に風景計画の策定が義務づけられた。
とくに歴史的市街地は保存の対象にできると定められ、多くの自治体が文化的および都市計画的な側面から、歴史的市街地における建築工事を厳重に規制している。その規制は看板や照明等にいたるまでかなり細かい。それが不動産の私権を制限するとして、たびたび裁判で争われもしたが、景観保全を目的とした私権制限は当然だ、というのが判例のほとんどだった。
その結果、イタリアでは、それこそセットを設営しなくてもNHK大河ドラマが撮影できるような場所が、都市にも郊外にも農村にもそこかしこにある。それでは不便ではないかと思うかもしれないが、たとえば古い建物の内部をリノベーションする技術などは日本よりはるかに進んでおり、美しい景観が現代的な快適性と両立している。
審議会委員たちの後悔
ひるがえって松江市も、市の景観審議会の委員たちも、住民団体から「城下町の景観が損なわれる」と指摘されるまで、マンションの建設が景観破壊につながるという認識を、まるでもっていなかったらしい。着工直前の2024年1月、住民団体は建設予定地の購入を求める要望書を市に提出。2月には、審議会委員12人中9人が「街並みとの調和も一体として審議すべきだった」として、審議のやり直しを求める意見書を市に出した。(読売新聞2024年12月21日など)