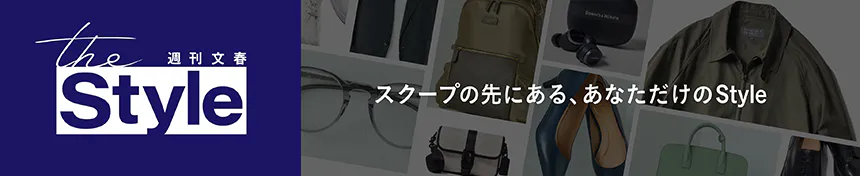松江城天守の国宝指定に向けては市を挙げて取り組み、さらに世界遺産登録をめざしている松江市が、みずからの努力を相殺してしまうような計画を、十分な検討もないままに簡単に承認してしまったという事実には、驚きを隠せない。
もっとも、松江市もいまさらながらに建設計画を変更させるべく動いてはいる。景観基準を見直し、建物の高さを法的に規制できる高度地区に指定することが検討されているが、すでに着工されたマンションには適用できないという。
そこで上定昭仁市長は、事業主体である京阪電鉄不動産(大阪市)に、高さを引き下げてくれないかと直談判したが、採算を理由に断られている。では、住民団体がいうように、市が当該の土地を購入できないのか。それについても、「事業目的がない土地を買い取ることはできない」というのが市の回答だという。
住民の利益と施主の利益どちらが大事か
しかし、高層マンションを建てさせないというのは、立派な事業目的ではないのか。世界遺産登録をめざすのが市の「事業」であるなら、それに適うが、もっと広い視野でこの問題を眺めれば、なおさら「事業」と呼べるはずだ。
ユネスコによる、バッファーゾーンを設置して景観を守るという条件は、じつは「グローバルな視点」だと先に述べた。世界中の多くの都市が、歴史的景観や美観を守ることを、いわば事業化して取り組んできたし、いまも取り組んでいるという意味である。
冒頭で述べたように松江という都市は、空襲を経験した日本においては希少な、普遍的な価値をもつ城下町であり、その中央に国宝の天守を戴く稀有な歴史都市である。したがって、その景観自体が地域の宝であり、日本人の宝である。
こうした問題は拙著『お城の値打ち』(新潮新書)でも述べているが、地域の利益という観点から、もう少し具体化して述べてみよう。
いま守られようとしているのは、事業主体である京阪電鉄不動産が当該の土地から利潤を生み出す権利だが、その「私権」を守ることで、まず、周囲の多くの住人が快適に暮らす権利が奪われていいのか、ということを考えなければならない。