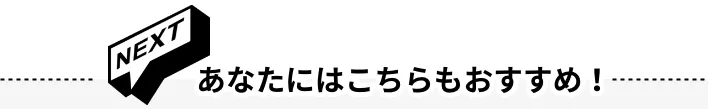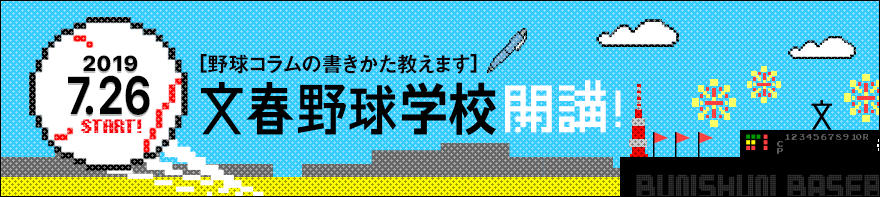「前田智徳さんはありますか?」
彼の目が少し変わった気がした。
「前田智徳さんはありますか?」
同じ左打者として期するものがあるのだろうか。私は4冊目を差し出した。
「前田さんは無骨な方なので自著はないんですが、この『引退記念グラフ』の中で、涙の抱擁をしていた入団時の打撃コーチ・水谷実雄さんは、こんな想い出を語っていましたね」
前田は自分を追い込み過ぎると体が動かなくなる。やろうとしているけど動かなくなるタイプ。他の選手には「やらんかい!」って怒鳴るんだが、前田には気持ちを切り替えさせることが大事やった。理詰めじゃなく対象物で教える。体で覚えさせる。前田はスランプになると体が開く。そういう時は開かんように意識するんじゃなくて逆方向に打たせる。それも流し打ちじゃなくて引っ張る気持ちで。バランスよく打てるまで1時間でも2時間でもレフトへ打たせた。左打者の軸足の左足をコマの軸のようにしっかり使えとね。
「とても勉強になります。やはりどんな名選手にもスランプはあったんですね」
「そうですね。そしてそこから見えてくるのは、スランプに陥った選手が見せる無垢なチームへの献身や人間性だったりするんですよね」
私はそっと1984年『V奪回!! 輝けカープ新時代』に載っていたミスター赤ヘル山本浩二さんの記事を見せた。
1984年8月8日。不動の4番だったミスター赤ヘルは6番降格を告げられた。当初はスタメンからも外される予定だったが、監督の自宅を訪れ「出させてください!」と直談判しての出場だった。しかし3試合後の大洋戦、ついに浩二はスタメンを外された。身体は万全、打撃不振によるスタメン落ちはミスターのプライドを傷つけた。しかし、浩二は過去の栄光とプライドをかなぐり捨てた。「代打でもいい。指令がくれば出るぞ」と、ベンチ裏の大鏡の前で若い代打陣とスイングを繰り返し、先発投手がベンチに戻るたびに「頑張れよ」と声を掛けるベンチウォーマーに徹したのである。そんなミスターの姿を見たナインは奮い立った。高橋慶彦は「浩二さんの姿を見て、どんな事があっても勝とうと思った」と当時の感動を振り返った。翌日のグラウンドには、体のキレを取り戻すためにアメリカンノックを要求する37才のミスターの姿があった。結果この年、浩二は8年連続の30本台の本塁打を放った。その記録が生まれたのも“あの忘れ得ぬ日”があったからに違いない。
しばらく黙って目を閉じていた彼は「有難うございました。今日は帰りますね、やりたいことがあるんで」と言い残し、足早に店を後にした。
最後に見せた笑顔は、あの優勝パレードで見た、ワタシの大好きな笑顔だった。きっと私のような本屋風情が見せた本など、プロである彼にとっては釈迦に説法だっただろう。「申し訳なかった……」そう思いながら、街灯に照らされた彼の背中を「頑張れ」と押した。満員電車の乗客の背中を押す駅員のように。
写真提供/桝本壮志
◆ ◆ ◆
※「文春野球コラム ペナントレース2019」実施中。コラムがおもしろいと思ったらオリジナルサイト http://bunshun.jp/articles/11677 でHITボタンを押してください。
この記事を応援したい方は上のボールをクリック。詳細はこちらから。