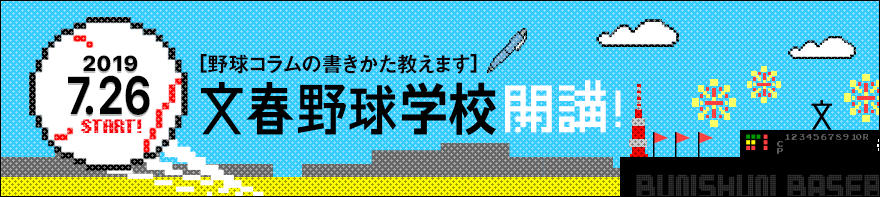いま10歳。小学5年生のタイガースファンいしいひとひ。
持っている応援タオルは、鳥谷選手、梅野捕手、そして「0点で抑えることができてよかったです。」と書かれている、岩崎投手の3枚。野球カードは阪神の選手だけでファイル1冊におさまらない。
それらをぜんぶ詰めこんだリュックを、持って帰ってきたランドセルのかわりに玄関で背負い、ひとひは一路、憧れの聖地めざして出発した。京阪、JR、阪神と乗りつぎ、西宮の駅を過ぎてしばらく、海側の窓におなじみの威容が見えてくる。
憧れの聖地、阪神甲子園球場に初めて行った日
9月9日、木曜だった。台風が東へ過ぎ、暮れなずむ夕空の高みに、ふたつ、みっつの雲。おとなの僕も、改札を出て思わず深々と深呼吸した。まったく、泣けてくるくらいのナイター日和だ。まわりには、関西圏から結集したタテジマ、黄色、オールドスタイルと、とりどりのレプリカユニフォームに身をつつんだおっちゃん、おばちゃん、少年少女、おじいちゃんおばあちゃんらの群れ。
対ヤクルト戦。阪神甲子園球場はいま試合開始15分前だ。
グッズショップ内を駆けめぐり、佐藤輝明のタオルをゲット。ゲート前で荷物チェックを受け、僕にとってはなつかしい狭さの階段を駆けあがる。と、一気に、雲の上につきぬけたように視界が広がる。ひとひは僕の前で立ちつくし、秋空と一体化した真みどりの窪地をみわたしている。
横顔をのぞくと、意外というか、納得というか、「海をはじめて見た子ども」のような表情ではない。テレビで見知っていることに加え、ここ2年の毎週土日、自分でもグローブをもってグラウンドで土にまみれている。甲子園球場の、その野球場としてのかたち、広さを、ひとひは一野球少年として、その瞳におさめようと、大きく目を見開いて立っていた。
一塁側アルプス席のほぼまんなかあたり。席についてスコアボードを見あげ、ひとひは顔をぱっと輝かせ、
「おとーさん、きょう先発、はるとやで!」
控えではあるけれど、しばしばマウンドにあがる左投手として、ひとひは以前から髙橋遥人に憧れに近い仲間意識をもっている。長い調整期間を経て、今年はこの日が初マウンドだ。
アナウンスが流れ、グラウンドに現れた選手たちが定位置に散っていく。マルテが、近本が、糸原が、中野が、大山が。
「おとーさん、サトテルや、ほら、サトテルがキャッチボールしてるって!」
と、ここではもう一選手でなく、一少年ファンとなったひとひが興奮して席で跳ねている。アルプスから見おろすとちょうど目の前がライトの定位置だ。
髙橋遥人がマウンドにのぼる。
「キャッチャー、梅ちゃんやないんやね」
たしかに。ボードには坂本の名が。審判の声が遠くひびき、遥人は第一球を投じた。
「ああ、夢みたい、てこれかあ」
ここからがもう、夢の坂を転げ落ちていくようだった。長い1回表だった。ぽろぽろと自在に動くボールを、阪神の野手陣がつかまえきれず、気がつけば、掲示板には大きく「5」の数字が刻まれていた。
夢はまだつづいた。2回に1点を追加されての4回裏、チャンスからヒットを重ね、これで3対6。5回表にマウンドにあがった藤浪晋太郎が圧巻の、今年最高といってよい投球を見せ、球場は黄色い海原のようにうねり盛りあがった。
「ふじなみ、めっちゃでかいなあ!」
その同じ藤浪が、6回表、3人にドッジボールみたいな四球。黄色い海原はしーんと平らかに。交替した岩貞も球道が定まらない。僕たちから少し離れた応援席から、派手なユニフォーム姿のおっちゃんが、
「こっらぁ、ストライクはいれへんのんかあ!」
ひとひは小声で、な、おとーさん、あれってヤジ? 僕も小声で、うん。ヤジのなかのヤジ。おっちゃんの声で、僕のなかで夢の幕が落ちた。そのまま9回裏まで長々とつづいた野球的現実を、僕たち阪神ファンはスタンドからえんえん直視するほかなかった。
スコアは3対13。
「めっちゃ負けたなあ」
帰りの新幹線で、しかし、ひとひは終始にこやかだった。
「めっちゃ負けたのに、めっちゃ楽しかったなあ、すぐそこに近本とか、サトテルとか、ほんまにいはんねんで。打ったり、捕ったりしたはんねんで。それだけでも楽しいやん。ああ、夢みたい、てこれかあ」
小5の野球少年は試合中もずっといい夢をみつづけていたのだ。