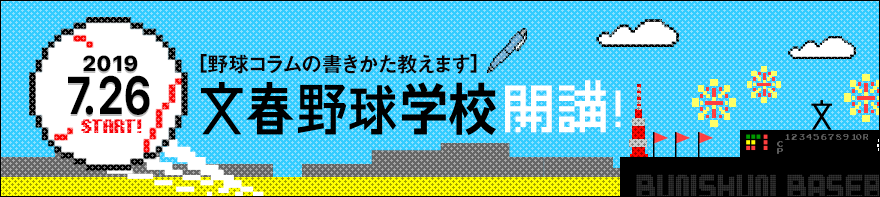ノムさんへの最後のインタビュー
野村克也氏に最後にインタビューをしたのは2018(平成30)年9月のことだった。それまでに、ノムさんには何度かお話を伺っていたが、そのたびに多くの発見と示唆を与えてくれる刺激的な時間を過ごすこととなった。最後のインタビューのテーマは「1992年、93年日本シリーズ」だった。この2年間の激闘を余すところなく描くべく、僕はヤクルトと西武の関係者に片っ端から会い、話を聞いていたのだ。
もちろん、この名勝負の立役者であるノムさんのインタビューは必須だった。満を持してオファーを出し、ついに実現したのがこの日だった。取材会場であるホテルニューオータニに登場したノムさんは車椅子姿だった。身体は弱っていたけれど、頭の速さと口は健在で、「そんな昔のこと、忘れちゃったよ(笑)」というボヤキからインタビューは始まった。
森祇晶監督率いる常勝西武ライオンズと、野村監督率いるヤクルトスワローズが激突した2年間の激闘。92年は死闘の末に西武が4勝3敗でヤクルトを下し、翌93年はヤクルトが4勝3敗で西武を撃破して見事なリベンジ劇を演じて見せた。2年間の両チームによる戦いは計14試合を行って7勝7敗で、ともに日本一には一度ずつ輝いた。果たして両者はどちらが強かったのか? 本当に両者の決着は着いたのだろうか? そんなことを探るインタビューだった。
このときもやはり、刺激的な発言は続いた。「西武に0勝4敗で負けると思っていた」「監督が内心で、“これは勝てないぞ”と思っていたら、いくら口では強気な発言をしても、それは選手たちに伝わる」「伊東(勤)より、古田(敦也)の方がキャッチャーとしては上」などなど、話を聞きながら、気づけば前のめりになっているのが自分でもよくわかった。この2年間を振り返って、ノムさんは言った。
「もう一回、西武とは戦いたかったよね。やっぱり決着は着けたかったですよ。《勝負》という字を考えてごらん。《勝負》とは、《勝ち》と《負け》って書くんだよ。《分け》なんて文字はないんだから……」
この言葉を聞きながら、「もう両者の対戦を見ることはないのだな……」と寂しく思ったものだった。しかし、ノムさんは笑顔で言った。
「決着がつかないまま終わっちゃったけど、それでいいのかもしれないね。今度はオレと森とどちらが長生きできるかで勝負だ(笑)」
もしも、野村ヤクルトと森西武の三度目の対決が実現したとしたら、結果はどうなったのだろう? 「歴史のif」に思いを馳せながら、僕はノムさんの言葉を聞いていた。
自軍には頼られ、敵軍からは恐れられる指揮官
2020(令和2)年2月11日、野村克也氏が亡くなった。突然の訃報に球界は悲しみに暮れている。「一人の人間の死は図書館一つ分の知識や情報の消失に匹敵する」ということを聞いたことがあるが、ノムさんに限って言えば、その損失は「図書館一つ分」ではまったく済まないことだろう。
球界にさまざまな改革をもたらしたことは、すでに多くの人が指摘しているが、ヤクルトファンの一人としては、ただただノムさんには感謝しかない。1990年にヤクルトの監督に就任するとともに、ID野球(import Data)を掲げてチーム改革に着手。「1年目で種をまき、2年目で水をやり、3年目で花を咲かす」の言葉通り、就任3年目の92年にリーグ優勝、93年に見事に日本一に輝いた。
子どもの頃から現在に至るまで、大のヤクルトファンだけど、この2年間の激闘こそ、ヤクルトヒストリーのクライマックスに位置する出来事だと、僕は思っている。だからこそ、当時のヤクルトと西武の選手たちに「あの2年間」について話を聞いて回り、それを一冊にまとめるべく奮闘しているのだ。野球史に残る名勝負の立役者であり、生みの親となったのが稀代の名将・野村克也だった。
当時、圧倒的な実力を誇っていた西武ナインに対して、ヤクルトナインは戦々恐々していたという。チームリーダーだった広澤克実は当時の心境を次のように吐露した。
「野村さんは僕らの後ろにデンと控えて、見守っていてくれるような監督なんです。僕らには知恵はないけど、野村監督が後ろから常に知恵を授けてくれる。僕らは、その知恵を実践していけばいい。西武との日本シリーズでも、“やっぱり、あのオッサンは大したもんなんだな。この人の言うことをオレたちが実践できれば、意外とやれるかもしれない”って思っていましたから」
広澤の言う通り、西武ナインは経験も実力も勝っていたにもかかわらず、「対ヤクルトナイン」ではなく、「対野村克也」に恐れを抱いていたことは取材を通じてよくわかった。たとえば、西武の司令塔・伊東勤(現中日ヘッドコーチ)は次のように語った。
「ヤクルトの選手がどうこうというよりも、野村さんのイメージが強かったし、あの一連の日本シリーズは野村さんとの戦いだったと思います」
また、現在はソフトバンクを率いる工藤公康はこんなことを言っている。
「僕は野村さんと一緒に野球をしたことがないから、野村さんの野球がどういうものなのかを知りません。だから、“自分たちの気づいていない弱点を丸裸にされているのかもしれない”ということはずっと気にしていました。常に野村さんの存在を意識しながら戦わなきゃいけなかったシリーズ、それがあの2年間だったと思います」
自軍はもちろん、敵にも多大な影響力を誇った名将。それが野村克也だった。