
2020年に入社し、小誌編集部に配属されてから約3年半が経ちました。入社早々に直面した新型コロナの感染拡大も落ち着いて、最近では取材相手の方に直接お会いできる機会が増えています。
まだまだ未熟な私ですが、取材の際に耳にするとガッツポーズしたくなる言葉があります。「お腹、空いていませんか」?……いえいえ、そんなにがめつくはありません。
正解は、“その人だけの言葉”。出来過ぎた答えに聞こえるかもしれませんが、切実です。なぜなら、取材後数日間の“帰宅時間”にかかわってくるから。
私たち編集部員にとって、著者の方から原稿をいただくことと同じくらい機会が多いのが、取材相手の方に話を聞き、自分で原稿にまとめる作業。
入社から今日まで、Sデスク(現編集長)には「原稿にするときは、聞いた言葉を“丸め”すぎてはいけない。勝手に整えてしまうのではなく、相手の言葉をできる限りそのまま残し、『ゴツゴツした具材がたっぷりのカレー』みたいな原稿を目指すんだよ」と口を酸っぱくして言われてきました。はじめて聞いたときには、カレーかーい!と心の中で叫びましたが、少しずつその意味がわかるようになってきたような気がします。
日頃お話を聞かせていただく方々はみなさん、ご自分だけの言葉を持っています。それは長年の人生経験による信条かもしれませんし、強烈な体験から出た切実な心情かもしれない。「これだ!」というキーワードをお持ちなのです。
取材中にその“強い言葉”を引き出せれば、おのずと原稿はスムーズにまとめられて、そのぶん早く帰宅できる(はず)。
とはいえ、つい最近、やはりご本人の“生”の言葉以上にカレーを美味しくする具材はないと痛感した体験がありました。
瀬戸内寂聴さんの三回忌に寄せ、10年間秘書を務められた瀬尾まなほさんに12月号へ掲載する原稿をいただいたときのこと。
8月にはじめてお願いのメールをお送りしたときには、ご快諾とともに「字数が多いため不安もあります」とお返事をくださいましたが(約1万字、原稿用紙にして25枚ほどとお願いをしていました)、約2ヶ月後、メールに添付されたファイルを開いた私は思わず、「あぁ……」と息を洩らしました。そこには、寂聴さんをそばで見ていた瀬尾さんにしか綴ることのできない、強い言葉の数々が並んでいたからです。

校了直前、打ち合わせと、何よりこの原稿を書かれた瀬尾さんという方に直接お目にかかってみたいとの想いから、京都市嵯峨野の寂庵を訪れました。1974年に寂聴さんが開いた寂庵には、いまも週に2日ほど瀬尾さんが通い、お手入れをされているそう。
少し緊張しながらインターホンを押すと、しばらくしてサンダルが石段を摺る音が聞こえてきます。
「お待たせしました~」
鮮やかなブルーのワンピースに身を包んだ瀬尾さんが迎えてくださいました。
「こんなに長い文章は書いたことがなかったので、書けなかったらどうしようかと思って。2ヶ月間、先生への手紙形式にしようか、それとも……とずっと頭の中で考えていました」
そうおっしゃいますが、実際には2時間ほどで一気に書き上げたと伺い、驚くばかりです。
「書きながら涙は出るし、読み返しても涙は出るしで、先生を思い出すと感情の管理が大変でした……」
原稿や誌面にはただ文字が並んでいるだけだけど、こんなにも人の心を動かしてしまう。瀬尾さんの言葉を聞き、その重みに改めて思い至りました。
「『僧侶の仕事は義務だけれど、「書く」ことは快楽』とよく口にしていて、文字通り、命を削りながら書いていました」

亡くなられる直前の寂聴さんの様子について、そう話してくれた瀬尾さん。お二人の愛情深くあたたかな結びつきが生まれた寂庵に、今度は「書く」ことへの強い想いの輪が広がっている。
インタビューで耳にした相手の方の言葉を“美味しく”届けるための訓練は怠らず、しかし同時に、この仕事をしながら、そんな輪があちこちで広がっていく様子をずっと見ていたいと思いました。
(編集部・神山未月)
source : 文藝春秋 電子版オリジナル












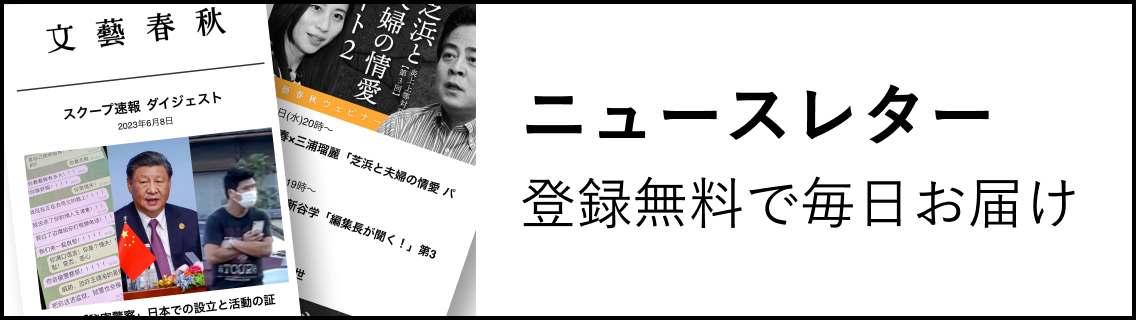
 トップページ
トップページ 後で読む・閲覧履歴
後で読む・閲覧履歴 マイページ
マイページ