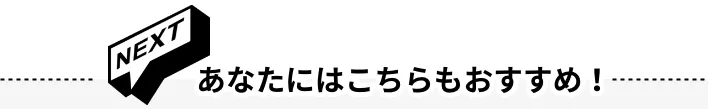星新一賞への再挑戦 ――「人狼知能能力測定テスト」解説
佐藤理史
我々の研究室(名古屋大学大学院工学研究科佐藤・松崎研究室)は、「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」のメンバーとして2013年より小説の自動生成に関する研究を開始し、2015年9月末締切の第3回星新一賞に、コンピュータを用いて制作した作品を初めて応募しました。この年の制作方法については、それまでの経緯を含め、『コンピュータが小説を書く日』(日本経済新聞出版社刊)に詳しく書きました。続く2016年の第4回星新一賞には、第3回応募作品の制作にも携わった松山諒平君が作品を制作し、応募にこぎつけました。それが、「人狼知能能力測定テスト」です。今回の目玉は、プロット生成と文章生成の両方を機械化し、小説生成の最初から最後までを通して、機械化したことです。
作品制作に使用したプロットは、「人狼知能プロジェクト」提供の人狼ゲームのログです。これは、人間がプレイするパーティーゲームの「人狼」を、10個のコンピュータプログラムがプレイした記録(実行結果)です。ですから、これを「コンピュータが作った」と捉えることに反対する人はほとんどいないでしょう。松山君は、このゲームログを文章化するプログラムの作成に取り組みました。
人狼ゲームのログをそのまま文章化しても、小説にはなりません。なぜなら、ログに記述されている情報は多すぎるからです。小説では、詳細情報をばっさりカットしてゲームのハイライトに焦点を当てる必要があります。
それとは逆に、ゲームログには不足している情報もあります。たとえば、プレイヤーがどんな人(プログラム)か、なぜそのような発言・行動をしたのかについては、提供されたログには何の記述もありません。このような部分は、ログから離れて、話を膨らませる必要があります。
人狼ゲームのログは、ゲームマスター(つまり、ゲームの進行に関するすべての情報を知りうる神)の視点で記述されています。人狼ゲームの場合、「だます・見破る・説得する」ところがおもしろいわけですから、神の視点から書くよりも、不完全な情報しか知り得ない、それぞれのプレイヤーの視点で書く方が、おもしろいに決まっています。そのためには、ログの情報を、書き手(一人称)となるプレイヤーの視点に立って再構成するとともに、ログには書かれていないプレイヤーの思考、葛藤、心情を追加する必要があります。
応募作品の主要部は、「人狼」となったF恵から見た最終会議までのゲームの進行と、「占い師」となったC子から見た最終会議までのゲームの進行から構成されています。これは、視点を変えることによって、一つのゲームログから複数のお話を作ることができることのデモンストレーションを意図しています。
ノンフィクションの場合、事実(ゲームログに記述されている情報)をねじ曲げることは反則です。しかし、フィクションの場合は、それもアリです。つまり、話を作るのに都合がいいところだけを残し、それ以外のところを変えてしまってもいいわけです。今回の作品でも、ハイライトとなる最終会議の場面はログを無視して話を作っています。そういう意味では、「ゲームログを文章化した」というよりは、「ゲームログを素材として小説を作った」という方が正確かもしれません。
今回の作品制作で、機械が作ったプロットを機械が文章化するというところまでは、おおよそ達成できたと考えていますが、まだまだ多くの課題が残されています。我々の研究室は、これらの課題の解決に取り組みつつ、今後も星新一賞に挑戦する予定です。
佐藤理史(さとうさとし)
1988年京都大学大学院工学研究科博士後期課程研究指導認定退学。京都大学工学部助手、北陸先端科学技術大学院大学助教授、京都大学情報学研究科助教授を経て、2005年より名古屋大学大学院工学研究科教授。京都大学博士(工学)。専門は、自然言語処理、人工知能。近著に『Rubyで数独』『コンピュータが小説を書く日』『言語処理システムをつくる』がある。現在、言語処理学会副会長。
松山諒平(まつやまりょうへい)
2012年名古屋大学工学部電気電子・情報工学科入学。2016年同学科卒業。現在、名古屋大学大学院工学研究科電子情報システム専攻在学中。