デジタル教科書が2030年を目途に“正式な教科書”に格上げされる。これまで「週刊文春」は小中学生へのデジタル教育の問題点を報じてきた。果たして拙速な導入は子どもたちに何をもたらすのか。気鋭の研究者の緊急提言。
デジタル機器を使った小中学生への教育は、間違いなく格差を広げるでしょう。デジタル教育の成果の差は指数関数的に広がります。つまり、使いこなせる子は飛躍的に伸び、不得意な子はどんどんおいて行かれるという特徴があるのです。
こう警鐘を鳴らすのは筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター長・准教授の落合陽一氏(37)だ。昨年までレギュラー出演していたニュース番組「news zero」(日テレ系)でもパソコンを目の前においてコメントする姿でおなじみだった彼が、デジタル教育に危機感を覚えているという。
日本政府は、2020年から初年度予算2300億円を投入して、小中学生に1人1台ずつタブレット端末を支給するGIGAスクール構想を推進してきた。
さらに文科省は2月14日、2030年を目途にデジタル教科書を正式な教科書として使用することを検討すると発表した。
「週刊文春」では、昨年、4回にわたってそのデジタル教科書などの懸念点を指摘するキャンペーン報道(「デジタル教育で日本人がバカになる!」)を行い、大きな反響を呼んだ。欧州には、すでに弊害に気づいて脱デジタル教育を進める国も出てくる中、日本は半歩遅れてデジタル教育に傾斜しているようにも見える。デジタルに精通する気鋭の研究者が語る問題点とは――。

デジタル教育には2種類あります。一つは、AI(人工知能)を駆使して、コーディングタスク(プログラミング)を行うような教育。もう一つが、教科書やノートにあたるものをタブレットに置き換える教育です。多くの人にとってなじみがあり、関心が高いのは、後者でしょう。
いまや小中学校のほぼ全生徒に1台ずつタブレットやPCが配られています。教科書として利用され、調べ物をしたり、宿題の提出などにも利用されている。また、学校からの連絡もそれらの機器で行われています。
2024年の文科省の資料によると、小5〜中3に配布される英語の教科書は、100%がデジタル化(同時に紙の教科書も配布)されている。さらに2028年度には「デジタル教科書を実践的に活用している学校の割合」が100%となることを目指すという。
もちろん、世界の潮流を考えれば、デジタル教育をある程度行うことに異存はありません。デジタル機器は、紙に比べて写真や動画などが使いやすく、視覚に訴える力が強い。また、より多くの情報が扱えて、スピード感もあります。
初回登録は初月300円で
この続きが読めます。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2025年3月6日号






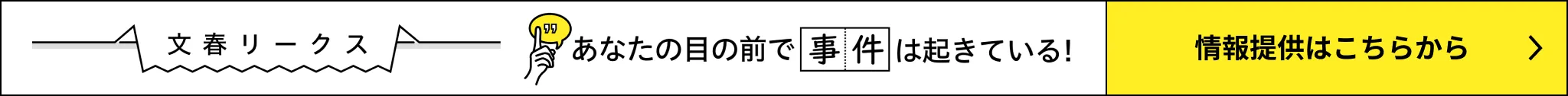
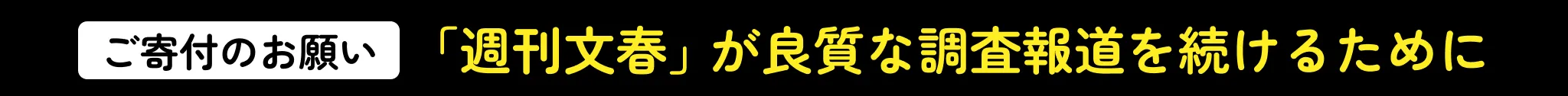
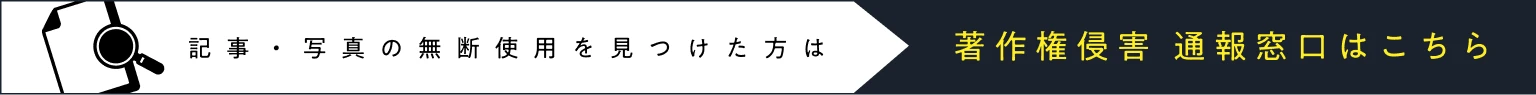
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ