「恥ずかしながら、コロナが始まった当初は『発熱患者お断り』の看板を立てていたんです。大病院も他の小さなクリニックも、風邪の症状がある患者は受け入れていませんでしたからね。我々もそれに倣っていたのです。
しかしある時、高校生が発熱して病院をたらい回しにされていることを知りました。『誰か助けてください』という声を聞き、『町医者が発熱患者を受け入れないのはアカンやろ』と思い直したのです。そして2020年10月、この地域のクリニックでは最初となる発熱外来を立ち上げました。それ以来ずっとコロナ患者を治療しています」
大阪府南東部に位置する河内長野市。和歌山県と隣接する自然豊かなこの街の一角に佇む「水野クリニック」の水野宅郎院長(43)はこう語る。
水野クリニックは、医師1名、看護師4名、ケアマネージャー1名で運営されている“小さな町の病院”だ。水野院長の専門も感染症ではなく循環器内科。水野院長によると、コロナ以前は「1日に20〜30人患者を診て、夜には自宅に帰る生活を送っていた」という。
そんな“普通の町医者”は、一昨年10月の「発熱外来」開設以降、コロナ治療の最前線に立っている。
しかも、水野院長はクリニックで発熱患者を受け入れているだけではない。大阪府南部を中心に、1日も欠かすことなく、自宅など病院外で療養中のコロナ患者への往診を続けているのだ。

1月22日、東京都では新型コロナウイルスの1日当たり陽性者数が過去最高の1万人を突破。大阪府でも同日、最多となる約7000人を数えた。感染拡大に歯止めがかからず、医療逼迫を懸念する声も出ている。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題

キャンペーン終了まで
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 電子版オリジナル






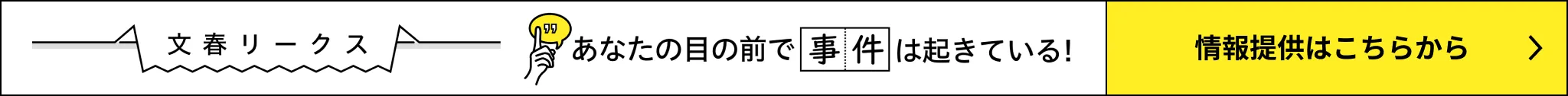
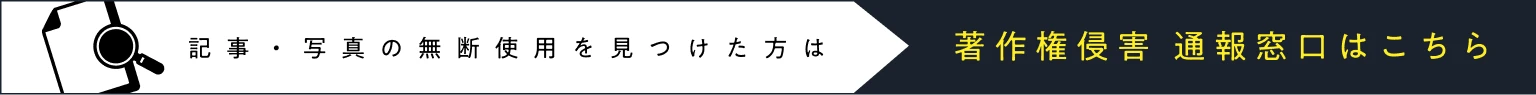
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ