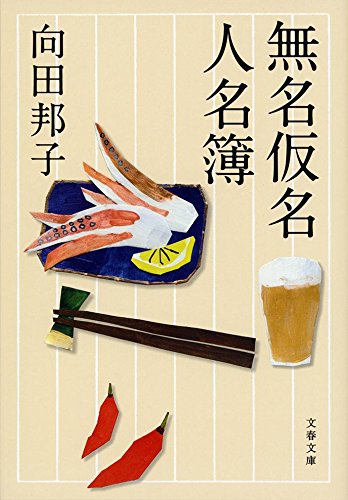向田さんの視線は優しいだけでなく、鋭い観察力で人の見栄や体裁を見抜いてしまう。でもそれが底意地の悪さで終わらないのは、「みんな同じですよ、立派そうに見える人でもあなたと変わらない、小さなことでくよくよしたり格好をつけたりして気張っているだけなんですよ」と背中を叩いてくれるような温かさに裏打ちされているからである。
そしてその観察眼が、極上のおかしみを生み出す。
ヘンテコなものわからないものをそうと言えない人間心理を突いた「なんだ・こりゃ」。猫のおしっこのにおいが染みついていると知らずに粗大ごみに出したマットレスをかついで帰った人が、においに気付いて再び捨てに来る「拾う人」。到来物の中身をすぐに見ずにはいられない性質の人が、来客後にさっそく戴きもののブラウスを着たところで客が引き返して来てしまい身の置き場に困る「スグミル種」。
ことさらに凝った台詞や突飛な行動で笑わせるのではなく、人間の本質をついたユーモアでくすりとさせる。さらに向田さんの笑いはしばしば、哀愁を伴う。自分の一番いいところ・こうありたいと思うものを精一杯広げる「孔雀」のように、人間のおかしみが、せつなさに変わる。
私事で恐縮だが、物語を創る上でのわたしの嗜好のルーツの一つは、大阪に住んでいた子供時代、日曜の昼にテレビ放送していた藤山寛美さんの松竹新喜劇である。阿呆の役に扮した寛美さんが阿呆なことばかり言ってみんなの笑いものになる。それでも寛美さんは愚直に阿呆な発言を繰り返す。阿呆なりのまっすぐな理屈、一途さが徐々に聞く者の心を打ち始め、次第に笑いがやみ、やがて涙に変わる。たまらなく好きなこの瞬間が、向田作品にも通じるようにわたしには思えて、心が震える。
余談だが、白黒つけずに絶妙な余韻をもたせて終わった小説『胡桃の部屋』に、わたしは後日談を付け加えてしまった。小説とテレビドラマの違いもあってのことではあったが、蛇足だったかもしれないという迷いは今なお心に残る。
向田さんのような人間ドラマを書きたいと願い続けながら、おそらく願いのままで終わるだろうと漠然と予感している。それでもやはりわたしは、わたしなりの手袋を探し続けようと思う。愚かで滑稽な奮闘がいつかささやかな真実に変わり、誰かの心に届くかもしれないと信じて。