
制服の少女が二人、手をつないでマンションの階段をのぼってゆく。
七階と八階の間の踊り場で立ち止まると、一人ずつ、胸の高さの手すりによじのぼってまたがる。
点滅する蛍光灯のせいで、薄暗い踊り場はまるで遠い稲妻に照らされているように見える。夏の終わりの夜風が二人の汗ばんだ肌を冷やし、おくれ毛をなぶる。
後ろの少女が、前の少女の腰にしっかりと腕を回す。前の少女がその手首をきつく握りしめる。
そして二人ともが、こちらをふり向く。咎めるような目だ。
――やめて。
――待って、お願い。
次の瞬間、世界がゆるやかに傾いてゆく。これはいったい誰の視界なのか、身体は宙に浮き、逆さになった夜空の高みに星が瞬いている。
悲鳴をあげるのに、声が出ない。手をのばすのに、誰にも届かない。
ややあって、おそろしい破裂音が響く。
汗だくで飛び起きると、心臓が早鐘を打っている。
今夜も、また、間に合わなかった。
いつもだ。
いつもきまって、遅すぎる。
1
権力を監視するのがジャーナリズムの役割だとするならば、この国にジャーナリズムなど存在しない。逆に権力から監視され、忖度まで求められる始末だ。
にもかかわらず、会社から支給される鷲尾粧子の名刺には、大宝テレビ『フラッシュ11』との番組名とともに、「キャスター/ジャーナリスト」と二つの肩書きが並んで印刷されている。
〈ジャーナリストとか、自分で名乗っちゃうんだ。いいじゃん、なんか賢そうに見えるし〉
同期入社の杉山博道は、粧子が番組のメインキャスターを張ることが決まった当初、にやにやしながら言った。〈賢そう〉〈に見える〉という二段構えで侮ってよこすあたり、前時代の遺物のごときハラスメントぶりだが、しかしそういう人物がごく当たり前に生き延びてプロデューサーにまで出世するのがこの業界だ。最近はもう腹も立たない。
「失礼します」
音声の男性スタッフが粧子のスーツの衿にピンマイクをつけ、ウエストの後ろにトランスミッターのクリップを留める。
「あと、お願いします」
「はい。ありがと」
自分でコードを服の中にうまく隠し、進行台本を手に、スポットの当たる放送席中央に向かう。左隣が社会学者でレギュラー・コメンテーターの有馬誠二、右隣はサブキャスターの局アナ、浅井マリリンだ。
フランス人の母親を持つだけあって目鼻立ちのくっきりしたマリリンに対して、昔から「着物の似合う顔だね」と言われ続けてきた自分。若い頃なら引け目を感じていたかもしれないが、さすがに齢五十ともなればつまらないコンプレックスからは解放される。年を重ねるのも悪くないと思うのはこんな時だ。
降り注ぐ強いライトのせいで顔が火照る。
「入ります」
メイクのスタッフが演者の額や鼻のあたまをパフで押さえると同時に、
「そろそろCM明けまーす」
女性ADの声が飛んだ。
メイクがさっと捌けてゆき、ADがこちらに向けた両手の指十本からカウントダウンが始まる。
「九、八、七、六、五、四、」
残りは無言で指のみだ。三、二、一、キュー、のサインとともにオープニングテーマが流れだし、モニターには今日のハイライト映像をバックに番組スポンサーが表示され、クレーンカメラによる俯瞰でのスタジオショットからぐっと寄って正面のカメラへ、そして再びの、キュー。
「こんばんは」
こんばんは、と両隣の二人も頭を下げる。
「九月十二日、金曜日のフラッシュ・イレヴン。今夜はまず、豪雨による土砂災害のニュースからお伝えしてまいります」
二十三時から五十六分間のニュース番組を、月曜から金曜まで。
入り時間はだいたい二十時で、どのニュースをトップに据え、その次に何を持ってくるか、ほかに特集コーナーの内容、誰にコメントを振り、どこを掘り下げるか、あるいはまたスポンサーや時流に配慮したNGワードなどについて打ち合わせ、スタイリストとその日の服を選び、ヘアメイクと、そして最終打ち合わせを経て本番となる。毎日のことだけに慣れてはいても、その週の放送を終えると気が緩むのか、金曜の夜は誘い合わせて飲みに行く者が多い。
「鷲尾さんもどうスか」
番組ディレクターの加藤大地に声をかけられ、粧子は微笑みを返した。
「ん、今日はごめん、遠慮しとく」
「そんなこと言って、ここんとこずっとじゃないですか。たまには付き合ってくれたって」
今どきのシュッとした顔立ちに人なつこい笑顔。いや、今どきといってもすでに三十代半ばだが、いずれにせよ加藤が社交辞令を超えてこちらを慕ってくれているのは伝わってくる。
「ごめんごめん、どうしても読んでおきたい本があってさ。また今度誘って」
「フラれちゃったね、加藤クン」
横合いから割りこんできたのは杉山Pだ。
「勉強熱心なんだよ、ショーコさんは。俺らとは目指すところが違うんだから諦めな」
うんざりして舌打ちが漏れそうになった時、
「やですよ、諦めませんよオレは」加藤が、冗談めかして口を尖らせた。「すいません鷲尾さん、また次の機会にお願いします。しつこく誘わせてもらいますんで!」
「うん、お疲れ。また来週ね」

他のスタッフらにもひらひらと手を振り、控え室に戻る。私服のカットソーとデニムに着替え、脱いだスーツをスタイリストに返し、テレビ用のメイクを一旦すべて落とすと、ようやく自分に戻った心地がした。薄付きのファンデで肌を調え、眉と目もとを軽く補い、リップを塗る。こんな夜中でも、さすがにスッピンで表を歩く勇気はない。
局を出てすぐにタクシーを拾った。ふだんからこのあたりを流しているのだろう、運転手はバックミラー越しにこちらの顔を見ても驚く様子はなく、「あ、ども、お疲れさまです」とねぎらってくれる。
「ありがとうございます」
答える声にあえて疲れをにじませた甲斐あってか、それ以上は話しかけられずに済んだ。家までのルートを簡単に伝え、背もたれに深く沈み込む。
いつものことながら、車窓を流れてゆく光が美しかった。この時間、見上げる高層ビルの窓明かりは半分ほどに減っているが、それでもまだ眩しい。もう何年も前、特集で番組に招いたマサイ族の戦士たちのことを思い出す。生まれて初めてナイロビから飛行機に乗って来日した彼らは、通訳とともに夜の六本木を歩くのにサングラスを手放さなかったそうだ。
あの頃、粧子はまだサブキャスターだった。メインの席に座っていたのは辺見鷹文――大宝テレビの大先輩であり各国特派員や支局長を歴任してきた叩き上げで、たとえば永田町を相手にする時などは強面なのに、ゲストやスタッフに対しては柔和で面倒見が良く、粧子のこともまるで娘のように可愛がってくれた。互いの名前から、〈鷲〉と〈鷹〉は喧嘩したらどっちが勝つのかなどとよくからかわれたものだが、深刻な対立など一度もなかった。この世の誰より、粧子は辺見を敬愛していた。
忙しい日々の合間にも芝居やコンサートや美術展に足を運び、話題の書に目を配り、これは面白いと思えば番組で積極的に紹介する。そうして年に二度は、皆で都合しあって長めの休みを取る。それらはどれも、辺見から受け継いだ遺伝子だ。
彼がメインを張る『フラッシュ11』は、十五年ほども続いた。子どもを持たなかった辺見が、年々認知症の重くなる妻を自ら介護したいとの理由で第一線を退いた時は、周りの誰も止められなかった。どれだけ仲の良い夫婦か、知らない者はなかったからだ。
以来、サブキャスターやコメンテーターの入れ替わりはあっても、メインはずっと粧子が務めている。ストレスの多い完全夜型の生活だが、大きく体調を崩したことはない。生まれつき頑丈なのは、こちらは両親の遺伝子だろう。
と、バッグの中でスマートフォンが震えた。
取り出して見ると、クマのスタンプがビールのジョッキを掲げている。
〈オツカレ! どのへん?〉
我知らず口もとがほころんだ。
〈お疲れさま、今タクシーです。あと十分くらいかな〉
〈りょ〉
運転手に電話での会話を聞かれていたわけでもないのに、華やいだ気分が伝わってしまった気がして、意味もなく咳払いなどしてみる。窓の外へ目をやれば、光の輪郭がさっきまでよりゆるゆると和らいで見える。
けれど、暗い窓に映る自分の顔に焦点が合い、澱のように積もった疲労の痕に気づいたとたん、すっと胃袋の縮こまる心地がした。現実は、いつも容赦がない。
ほんの半年ばかり前までは、この期に及んで自分にこんな季節が訪れようとは思ってもいなかった。異性から、まだ女性として扱われるなんて。ましてやその相手がひとまわり以上も年下だなんて。
誰にも打ち明けていないし、お互いマンションの出入りには用心もしているけれども、もしこの関係が知られたならどうなるだろう。今や大宝テレビの〈顔〉ともいえる五十歳の女性ニュースキャスターと、十四歳下のひな壇芸人の組み合わせは、世間からどんなふうに受け止められるだろう……。
再びスマホが振動した。
〈腹、へってる?〉
もちろん! と打ち返す。
〈おけ。今夜はラザニア・ボロネーゼです〉
やったね! と返し、飛び跳ねて喜ぶウサギのスタンプも送る。若ぶっているわけではない。彼の前では気持ちが少女に戻るだけだ。
スマホをバッグにしまうと、粧子は握り込んだ指の関節を両耳の下に押しあて、ぐりぐりとリンパマッサージを始めた。こんな疲れた顔を彼に見せるわけにはいかない。
* * *
紀尾井町の会社から四谷まで全速力で自転車を漕ぎ、速水理央は汗だくで店に飛び込んだ。カウンターのいちばん奥の席で、綾香がにこりと片手を挙げる。
「ごめんね、待たせて」
「大丈夫。お先に始めてたし」
女二人、並んで座り、まずは生ビールだ。綾香も同じものをもう一杯頼む。
「やれやれだよ。たいした距離でもないのに、ふくらはぎがぱんぱん」
「年なんじゃないの」
「あ、それ綾香さんが言う?」
笑い出した彼女が、枝豆を口に運ぶ。食事の時だけ後ろで束ねる髪がちょこんと跳ねている。先月三十六歳になったのにせいぜい二十代後半にしか見えないのが綾香のコンプレックスで、二つ下の理央のほうがいつも年上に見られる。嬉しいことだ。
互いの会社から遠くなく、料理は何を頼んでも美味しいので、この居酒屋はよく待ち合わせの場所になる。今夜は理央の仕事が押したせいで待たせてしまったが、そこは同業のよしみ、逆の場合もあるからどちらも怒らない。
高木綾香の勤める『大宝パブリッシング』はおもに実用書や芸能関係のムックなどを出版していて、先月まで彼女が手がけていたのは、何度か日本代表にもなったサッカー選手のエッセイ本だった。
いっぽう、理央の勤め先は『文藝春秋』――「週刊文春」の特集班だ。殺人事件の取材、芸能人の秘密の恋愛、議員の不倫現場の張り込み。何かとカドが立つことも多いので、所属はよほどの必要がない限り人には言わないようにしている。
二杯目の生ビールで火照った身体が冷えてくると、今度は熱々の揚げ物、生姜のきいた豚の角煮、脂ののった焼き魚なども欲しくなる。好きなものを少しずつ食べられるのが嬉しい。自分で作るとこうはいかない。
大好物の蛸の唐揚げが目の前に置かれるなりハフハフと頬張った理央は、ふと、隣からの視線に気づいて顔を振り向けた。
「う? どした?」
すると綾香は首を横にふり、はにかむように小声で言った。
「なんかこう……今がいちばん幸せだなあ、なんて思って」
ろくに噛んでいない蛸を呑み込む。
「早く食べて帰ろっか」
こくん、と綾香が頷いた。
夜風にあたりながら、自転車を押して歩く。チキチキチキ……と金属音がついてくる。
四谷三丁目の裏路地にあるマンションの部屋を、二人でシェアして暮らし始めたのは去年のことだ。建物自体は築四十年という古さだが、内装や設備は新調されていて不便はないし、家賃を折半することで広めの2DKが借りられる。
玄関を入り、明かりをつけ、靴を脱ごうとした綾香を後ろから抱きすくめる。小柄な彼女の身体は、理央の腕の中にすっぽりおさまる。
「だめだよ。汗くさいよ、私……」
「それを言うならあたしでしょ」
それぞれ仕事があるので部屋は分けているけれど、ほとんどの夜、寝る時は一つのベッドだった。
(つづく)
イラストレーション いしいのりえ
第2回以降は、毎週木曜7時に配信予定です。
source : 週刊文春 2025年9月11日号








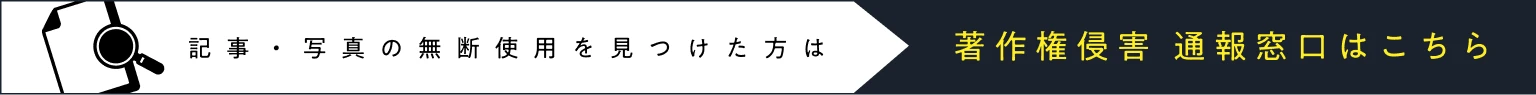
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ