今週号で、1人の記者が、「書き」としてデビューしました。「週刊文春」に入って、初めて自分で原稿を書いたのです。以前もご説明した通り、小誌では、原稿を書く人を「書き」と呼び、そのサポートをする記者を「アシ」と呼びます。私も、憧れだった「週刊文春」に異動し、初めて原稿を書いた日のことは今でも忘れることはできません。
遠山敦子さんという民間から文部科学大臣に就任した女性を、ワイド(1ページほどの記事)で取り上げました。「これで失敗すると二度と書かせてもらえないのではないか」と不安が爆発し、また週刊文春の原稿を書き上げるためには、どれくらい取材すればいいかも、皆目わからない。とにかく、いろんな人に取材を申し込みまくったのを覚えています。その時、電話取材を受けてくれたのが、文科副大臣だった岸田文雄氏でした。
校了の日に、編集長から「よく取材してあった。面白かった」とかけられた言葉は、その場面とともに鮮明に覚えています。
さて、書きデビューを果たしたI記者が、小誌に加わることになったのは、1本の電話からでした。2020年の9月のこと。彼女は、編集部に電話をかけ、「週刊文春で働きたいんです。記者を募集していませんか」と電話口に出た女性社員に告げたのです。女性社員は、「変な電話だな」と思いつつも、話した感じがよかったので、連絡先を聞いて、私にメモを持ってきました。
私は、その経歴を見て驚きました。大手メディアで働く正社員だというのです。ただ、カメラマンとしての採用で、メディアで働くうちに、どうしても記者になりたい、取材がしたいとの思いを強くしていました。ただ、その会社では、そうした異動は滅多に叶わない。そこで、ゴリゴリの取材をしている小誌で勝負したい、と直電に及んだのです。
正直、「あぶない人だったらどうしよう」との考えもよぎりました。ただ、人と会うのが、週刊誌の基本。まずはデスクに会ってもらいました。その上で、私が面接にしました。最後は「本当にいいのか」「早まるな、もう一度冷静に考えろ」。スカウトというより、半分は慰留でした。
大手メディアの正社員を辞めて、週刊誌の契約記者になる。安定や福利厚生を考えるなら、絶対に前者。親だったら、普通は反対します。「この場で返事しなくてもいい。よく考えて、それでも働きたいと言う覚悟が固まったらメールをください」と言って、その日は終わりました。彼女から返事が来たのは翌日でした。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題

キャンペーン終了まで
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春

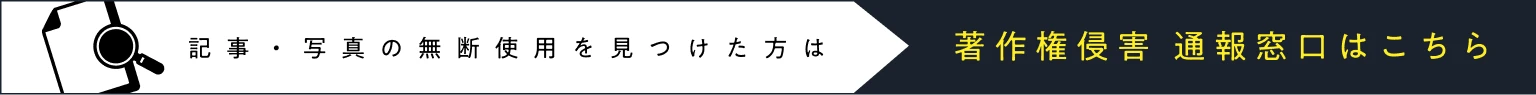
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ