読売新聞の渡邉恒雄主筆が亡くなる前日、私は少し緊張して法律事務所にいた。あることを想定して、心が身構えていたのだ。それには理由がある。
この3年間、私は「文藝春秋」誌上で毎月、「記者は天国に行けない」という連載を続けてきた。
一体、私たちは何のために、誰に向かって書いているのだろう――。そんな根源的な疑問を持ちながら、記者体験をもとに、息も絶え絶えのメディアの空気や記者の条件について書いていると、どうしても渡邉主筆が君臨した読売編集局の記事封殺や忖度幹部について触れざるを得なかった。
私は長い間、読売社会部にいて、政治家の政治資金疑惑や蓄財について記事を執筆した。そして何度も編集幹部から「この記事は掲載できない。主筆がだめと言っているんだ」と差し止めを食らった記者であった。

そして、連載で「清武の乱」と呼ばれたドン告発の実相や背景について書くときがめぐって来た。それは2011年に巨人のコーチ人事について、思い付きのように渡邉氏から横やりを入れられ、その独裁の非を記者会見で訴えたことに始まる。私は球団代表の職を解任され、「読売新聞社と全面戦争になる」という彼の言葉通りに、6年に渡って読売グループと片手に余る訴訟を戦った。
それは私や家族にとって暴風の中をよろめきながら進む苦痛の記憶だが、一介の社会部記者が心ならずも人気球団の改革に携わり、そして再び書き手に戻る行程でもあった。だから、私は進まぬ筆の重みを感じながら、書き進めてきた。
2024年11月号で、「独裁者の貌」(リード文=「俺は最後の独裁者なんだ!」。猛烈な勢いでまくしたててきた)、12月号で、「悪名は無名に勝るのか」(「文句を言うのなら、飛ばすぞ」。主筆室での面談は1時間半に及んだ)、2025年1月号で、「おかしいじゃないですか」(身を投げ出さなければ何も変わらない――その日、私はカメラの前に立っていた)。
初回登録は初月300円で
この続きが読めます。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2025年1月2日・9日号
他の記事を読む
- 「週刊文春は関東軍」「法廷で会おう!」ナベツネvs文春14年闘争史
- 緊急寄稿 清武英利「天国の門の“じいちゃん”に献ず」《渡辺恒雄 主筆の大往生》
- 渡辺恒雄 独裁者の「遺言」 大野伴睦元秘書、寵愛大臣、側近、好敵手が明かす
読み込みに失敗しました








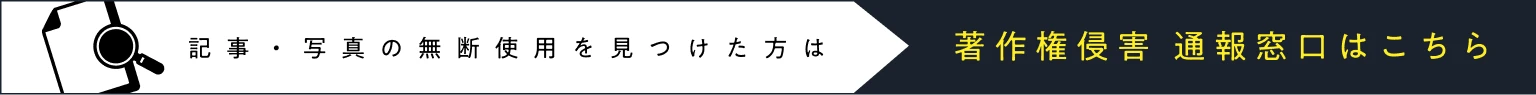
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ