「棋力の上達には良い駒を持つことだ」
かつて大山康晴十五世名人はファン向けにこう語ったという。
良い道具を持てばそれを大事にする気持ちも湧く。そこから技術の向上にもつながる。このような教えなのであろう。
手軽さ、簡単さが好まれる現代、時間を掛けて「本物」に出会うことが少なくなっている。それだけにこの言葉が心に染みるのだ。
良い将棋盤の材質は本榧(ほんかや)で、厚みは五寸(約15㎝)以上。値段も100万円を超えるものまであるが、流行り廃りがない分、一生ものである。
駒の材質はツゲの木が良いとされ、駒の生産地として有名な山形県天童市のシェアは、90%を越える。
駒師が一枚ずつ駒に文字を彫り、そこに漆を入れる。漆の重ね塗りで文字が駒より盛り上がる「盛り上げ駒」はもはや芸術である。
初回登録は初月300円で
この続きが読めます。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2022年1月27日号







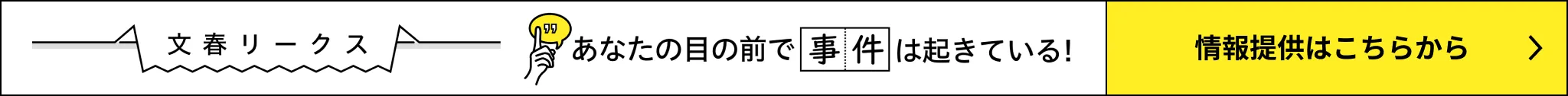
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ