真っ向勝負のオープンバレーで世界と戦う日本のエースを育てたのは、勝利至上主義の数歩先を行く「高校バレー界の異端児」だった。
(Yoshiki Ogawa 1955年10月29日、愛知県生まれ。早稲田大学在学中に成徳学園(現・下北沢成徳)のコーチに、26歳で監督に就任する。02年には「高校三冠」を達成し、荒木絵里香、大山加奈、木村沙織ら日本代表選手を多く輩出。今年度をもって、42年間の監督生活に幕を下ろす)
新春を彩る、高校バレーの全国大会。通称“春高”に、主役になると目されたチームの姿がない。
下北沢成徳――。今年度のインターハイ四強、国体4位の優勝候補。何より、全国制覇12回を成し遂げた監督・小川良樹の最後の晴れ舞台になるはずだった。しかし、成徳は春高・東京予選で涙を飲んだ。コーチ時代から48年に及んだ指導者生活は地方予選で静かに終わった。記者に囲まれた小川はこう言った。
「私らしい終わり方ですよね」
長時間練習、体罰との訣別
高校女子バレー界、いや日本のバレー界で、小川が監督として一頭地を抜くのは優勝回数ではない。
荒木絵里香、大山加奈、木村沙織、黒後愛、石川真佑……。この20年、五輪日本代表の中心選手は小川の教え子たちだった。Vリーグには30人以上の成徳OGが進んでいる。
ロンドン、東京の五輪二大会でキャプテンを務めた荒木。彼女は、一度バレーを辞めようとした。
2004年のアテネ五輪では最後に代表から外された。06年、何もかもうまく行かず、代表合宿を辞退することを決め、チームに伝えた。半端な気持ちではない。バレーを辞めるつもりだった。小川に連絡した。
恩師は「辞めるな」と引き止めはしなかった。ただ、こう言った。
「辞めるのはいいけれど、その前に絵里香が大事なものは何かを考えなさい」
荒木はこう振り返る。
「レギュラーになれない、プレーがうまくいかない。こんなんじゃ続ける意味がないと思っていました。けれど、小川先生に言われて、自分にとって何が一番大事なのかを考えた。そうしたら、それは『バレーがうまくなりたい』だった。先生の言葉で目標と目的が整理できて、行動の軸ができた。それ以降、私はどんな状況でも、常にバレーボールを楽しむことができました」
28年ぶりのメダル獲得となったロンドンの銅メダル。キャプテン荒木と共に歓喜の中心にいたエースの木村はこう明かす。
「小川先生だけはごまかせないし、すべて見透かされていた」
成徳の選手は、卒業して伸びる、選手生命が長いと言われる。
女子バレーに連綿と続いてきた長時間練習や体罰から距離を置き、選手の自主性を尊重し、トレーニングに力を入れる成徳は、高校バレー界の異端児だった。ただ、小川も早大を卒業し、1981年に監督になった当初は「勝つために練習は長く、厳しくやるもの」という考え方だった。
「選手を束縛して、俺の言うことだけ聞け、と思っていたし、うまく行かなければ手を上げたこともあります。周りの方々から『厳しくしなければ女子は勝てない』と言われるのを鵜呑みにしていたんです。強くするにはストイックに、それこそバレーボール以外の時間は削らなければダメだと思っていたので、自分の服装も常にジャージで、好きな映画も一切見ない。そういう姿勢が選手を追い込んでいることに、気づきもしませんでした」
30代半ばを過ぎた頃、併設の中学が生徒募集を再開。小中学生の頃に全国大会を経験した有望な選手たちが成徳に入ってくるようになった。
この頃、小川は体罰と訣別する。練習が近づくと、暗い表情になっていく選手たちを見て、疑問を感じ始めたのだ。そして、2000年、超高校級の大山と荒木がそろって入学してきた。
自分の言葉が選手の成長を妨げていた
「衝撃的に嫌でしたね。だって、これだけの逸材をダメにするわけにはいかない。手足を縛られたような状態でしたし、とにかく早く卒業してくれ、と思っていました」(小川)

初心者ならば「厳しく、長く」の練習も無駄ではないが、高身長で体のできてない選手に強度を上げすぎればケガにつながる。ウェイトトレーニングで筋力をつけ、ボール練習も適性を見極めながら、最低でも週に1日は練習を休みにした。選手を管理して、勝利を最優先するチームとはまさに真逆のスタイルは、当然反発も買う。しかし、結果的には春高、インターハイ、国体と三冠を成し遂げる。そこから本格的に自主性への舵が切られた。
「自分の駒のように選手を動かして、その通り行けば嬉しいです。私もそういう指導者に憧れていました。でも、むしろ私が『こうしなさい』と言ったがために、選手のプレーがうまく行かず、試合に負ける。監督の言葉は絶対的だから、と選手は従うだけで、可能性を消していたんです」
今、小川はほとんど選手に指示をしない。何もしないか、あるいはただ、問いかける、のみだ。
「コートでプレーするのは選手たち。自分で判断する力を持たないといけないのに、私の言葉が選手の成長を妨げていたんだ、と気づかされた。それならばあえてあれこれ言わないほうがいいな、と」
ある大会では“事件”も起きた。
「試合が終わって1時間半が過ぎても、インタビューから選手が戻って来ない。さすがに明日決勝だからそろそろ、と様子を見に行ったら、選手たちが私を置いて先に帰っていました(笑)」

今回、最後の春高を逃した東京予選。小川はこう考えていた。
「コートに立つ7人中3人が1年生。レベルの高い東京予選を勝ち抜く経験を積み成長できれば日本一を狙える。優勝するならばこのメンバーだ」
そして、敗れた。小川だけでなく、OGたちも「先生らしい」と言う。
“勝つ”より“成長”に力点を置く。それで何度も負けてきた。
今回、小川が「この人に話を聞いてみては」と1人だけ名前を挙げた選手がいる。
高橋昌美。Vリーグでもプレーしたが、全国的には無名の選手だ。昨年まで嘉悦大バレーボール部監督。小川が嬉しそうに語る。
「高校時代、まともにしゃべれなかった彼女が今、監督をやっている。いいチームを作っているんですよ」

その高橋が証言する。
「歴史にたとえると、小川先生は徳川家康みたいな大将軍。でもどれだけ長く続いても終わる時が来る。受け継ぐのはそのマインドを持った弟子たちです。小川先生がいないから終わり、ではなく、プラスしてもっと可能性を広げるのが、若い自分たちの役目だと思うんです」
出産を経て37歳まで現役を続け、今は早大で学ぶ荒木。絶対的エースとして活躍し、引退後の今なお、全国のバレー少女の憧れとなっている木村。子どもたちへの普及活動を続ける大山。代表選手だけでなく、Vリーグの選手、さらには指導者として多くのOGがバレーボール界に携わる。
「選手がこの場所にいて、自分の個性がのびやかに出せる。指導者が思う正解に当てはまらないからダメじゃなく、その子に合う正解はいくつもあっていいはずですよね」(小川)

自分で正解を見つけるべく、考える力を育むこと。“早すぎた名将”のバトンは、次世代に渡された。
撮影 杉山拓也
下北沢成徳から世界へ羽ばたいた選手たち(電子版限定特別カット)
荒木絵里香|03年卒業。主将だった五輪で銅メダルを獲得
初回登録は初月300円で
この続きが読めます。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2023年1月19日号







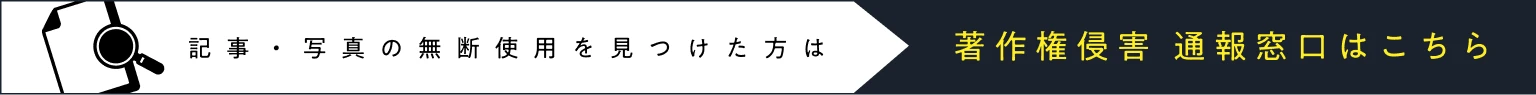
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ