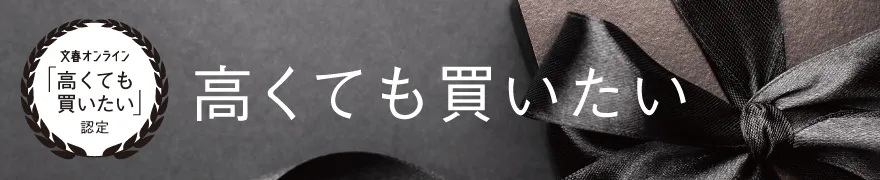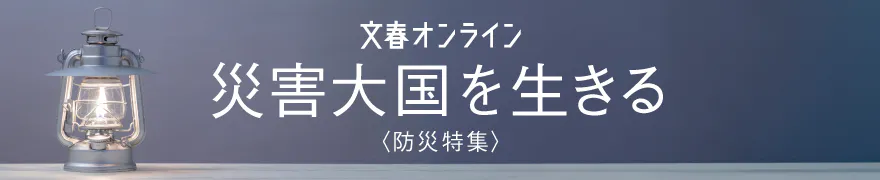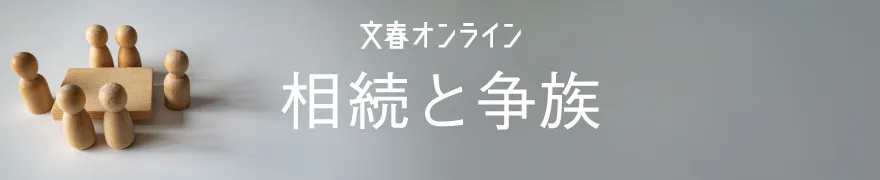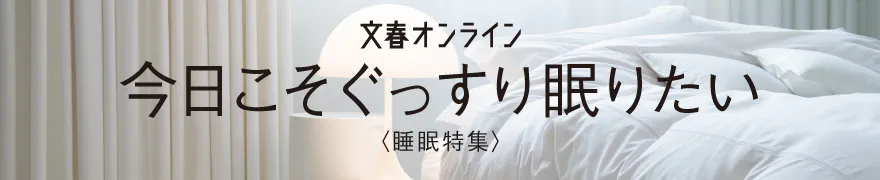黎明期に開通した鉄道。しかし当時の技術力ではトンネルを簡単に掘ることもできず…
ともあれ、こうして築いた大津という町の存在感は、近代に入っても揺るがない。1880年には京都~大津間の鉄道が開通しているが、これは新橋~横浜間に日本初の鉄道が通ってからわずか8年後のことだ。つまり、大津はその都市としての重要性からいち早く鉄道という近代のシンボルにも恵まれたのであった。
ただ、このときの大津駅の場所はいまの大津駅とはまったく違っている。というより、京都と大津を結ぶ線路が敷かれた場所そのものがいまとは別だった。
東山・逢坂山というふたつの山を越えねば京都と大津は結べない。当時の技術力ではトンネルを簡単に掘ることもできず、南に大きく迂回したルートを採っていたのだ。その線路の跡地は、名神高速道路や国道1号に転用されている(つまり大津駅の南側の山に張り付く国道は、“廃線跡”というわけだ)。
当時の線路は大津市内に入っていまの膳所駅(当時は馬場駅)でスイッチバック。琵琶湖畔に進出し、いまのびわ湖浜大津駅の場所に初代の大津駅が設けられた。開業と同時期には長浜と大津を結ぶ日本で最初の鉄道連絡船も就航している。鉄道連絡船というと津軽海峡を渡った青函連絡船などが名高いが、はじまりは琵琶湖をゆく船だった。
こうして大津に鉄道がやってきたのだが、1889年に現在のJR琵琶湖線にあたるルートが完成すると、わざわざスイッチバックをしなければならない初代大津駅の地位は低下して貨物専用に。一時旅客営業を再開するも、大正時代に入って現在の京阪石山坂本線や京津線が相次いで開業すると、初代大津駅は旅客駅としての役割を終えて、大津市街地のターミナルは京阪に譲ることになったのである。
その間の1921年に京都~大津間のルートが現在のものに改められ、いまの大津駅が開業している。このように、大津の町は古くから港町として栄えたがゆえ、鉄道をいち早く必要とした。それが結果的にターミナルの位置が定まるのが遅れることになり、いまのようにびわ湖浜大津駅と大津駅という、どっちつかずの“玄関口”を抱えることになったのである。