難病の子どもの夢を実現させる非営利団体「メイク・ア・ウィッシュ」の“伝道師”として30年間、3000人の夢に寄り添ってきた大野寿子さん(73)。がんで余命1カ月と宣告されたのは、今年6月26日のことだった。それでも彼女は最期のプロジェクトに挑む――。

細くなった腕を伸ばしてマイクを握ると、大野寿子はこう切り出した。
「すっごい楽しみにして、ここに来ました」
顔にははち切れんばかりの笑みが浮かんでいる。
白いシャツに青のカーディガンをはおり、黒いロングスカート。髪は若い頃からショートで、最近は染めなくなったため、輝くようなグレイヘアである。
7月6日。神戸・三宮近くのキリスト教施設には約60人の聴衆が詰めかけた。「夢に向かって一緒に走ろう」と題した講演だった。
笑みには理由があった。大野は末期の肝内胆管がんで、6月末には医師から「余命は1カ月ほど」と宣告されている。来られるかどうか最後まで不安だったのだ。実際、体重はかつての50キロから40キロに減り、157.5センチの身長にしてはかなり細い。衰弱は確実に進んでいる。
この日の神戸は最高気温が34度にもなった。普段は千葉県浦安市の自宅で、介護用ベッドに体を横たえている。それでも講演では、不思議と元気になる。
「アドレナリンが出るのかな。しゃきんとするのよ」
さすがに9月に予定していた講演は無理と判断した。この神戸が生涯最後の講演になりそうだった。
難病の子の夢をかなえようと米国で非営利団体「メイク・ア・ウィッシュ」が設立されたのが1980年。小児白血病の少年クリス・グレシャスは「警察官になりたい」と夢見た。それをかなえようと地元の警官がクリスに制服を着せ、白バイに乗せたのがきっかけだ。
12年後に日本支部(MAWJ)が沖縄で生まれる。事務局が東京に移った94年、大野は、地元の教会で、信者たちがMAWJについて話しているのを聞いた。「夢」という言葉に心が反応し、米国での活動に関心を持った。病気の子の夢を実現しようと、見ず知らずの人たちが応援している。素敵な活動だと思った。以後、大野はその活動に携わり、98年からは事務局長を務めた。2016年に65歳で退職後も理事として学校や大学などで講演を続け、年間200回以上になった年もある。子どもたちの姿を伝える「伝道師」役を果たし、手助けをした子どもは3000人を超えている。
病気になると子どもは夢を描くのが難しくなる。やりたいことがあっても、家族や医療者から、「病気が治ってからね」「まずは病気との闘いだ。がんばろう」と言われ、夢を封印してしまう。
しかし、大野たちはこう考えてきた。夢を見て、それを語ることが、周りを動かす力になる。難病であっても夢の実現に近づくと、苦しい顔にも笑みが浮かぶ。それが周りの者たちに伝播し、幸福が膨らんでいく。大野がやっているのは、それを伝え、笑顔の種をまく活動だ。そのため自身を、「MAWJの種まきおばさん」と称している。
◇
最後の講演で紹介した子どもの一人が、東大阪市の嘉朗君だ。
93年に生まれてすぐ、ミルクを激しく吐いた。息づかいもおかしい。体調は戻らず、母は各地の病院を回る。「こんな体に産んでしまって」と自分を責める母に、3歳の嘉朗君は言った。
「病気やからって悪いことばっかりちゃうねんで。病気やからわかることもあるんや」
「20歳になったら恩返ししたる」
母はこの言葉に、自分を責める気持ちが息子を苦しめていたと知る。
4歳で原発性免疫不全症と診断された後、間質性肺炎、再発性多発性軟骨炎など次々と難病に襲われる。学校にもあまり通えない。それでも大阪の子らしく、調子に乗っては、周りを笑わせた。
さい帯血による造血幹細胞移植手術のため9歳で東京の病院に移り、しばらくして詩を書き始めた。入院生活が2年を過ぎたころだ。疲れた母がベッド脇でうとうとしていると、パソコンに何かを書いていた嘉朗君が「後で読んで」と言って眠った。夜中にパソコンを開くと、こんな詩が書かれてあった。
〈いま、おいらにつばさがあれば/病気を治して/ママをいろんなところへつれていってあげたい。/いっつも看病してくれているママ。楽しいところへ、わくわくするところへ/つれていってあげたい。/ママ、もうちょっと待っててね。病気を治したら、絶対にしあわせにするから。/それまで待っててね。〉
子どもは病魔に襲われても他者へのいたわりを忘れない。自分のことで精いっぱいのはずなのに、周りの者を気遣う。
嘉朗君は日ごろ、母にこうも言っていた。
「20歳になったら恩返ししたるから、それまでは世話してな。ばばあになったらおしめも替えたるから」
嘉朗君の母は病院でMAWJのポスターを見て、連絡をとった。夢を聞かれた嘉朗君は「沖縄への家族旅行」「回転寿司屋を借り切っての食事会」など次々と夢を語った。しかし、免疫不全症の場合、ウイルスや細菌、病原体に細心の注意が必要だ。症状が改善しないと実現は難しい。移植をしても免疫力は回復せず、肺の感染症は悪化し、ただれた足が痛んだ。
2005年12月の暮れだった。「年明けには大阪に帰れるかも」と期待した矢先、移植経過の検査中に突然体調が悪化する。そのまま帰らぬ人となり、夢ははたせなかった。
にぎやかな空気をこよなく愛した嘉朗君の通夜には、だんじりばやしが流れ、「涙厳禁」「笑顔歓迎」と書いた紙が張られた。
12年の生涯で残した詩は35作である。大野は講演の終わりになって、その一つをゆっくりと読み上げた。透き通るような声が会場を覆う。

〈あったことのない知らない人たちが/ぼくたちのために/けん血をしてくれる。/それが/血しょうばんになったり/マップになったり/グロブリンになったりして/ぼくの体を元気にしてくれる。/あったことのないしらない人たちの税金で/ぼくたちは/治療を受けられる。/つらい時もしんどい時もくるしい時も/「もういやや」って泣きそうになった時も/あったことのないしらない人たちが支えてくれる。/ぼくは、一人じゃないっておもうことができる。/ありがとう。アリガトウ/感謝の気持ちをわすれずに/せいいっぱいがんばっていきたい。〉
会場からすすり泣く声が聞こえている。
マイクを置いて舞台を降りた大野は、すぐに椅子に腰掛けた。最後の講演が終わった。なぜか涙が零れた。
「周りに感謝する気持ちが湧いてきたんです。講演の企画者。ここまで連れてきてくれた人。話を聴いてくれた人。そして、子どもたち。ありがとうと思い、ぐっときたんです」
休憩に入ると、控え室で椅子を並べて横になった。20分ほどして講演会場に戻ると、一人の女性に声を掛けた。嘉朗君の母だった。ネット交流サービス(SNS)などで大野の体調悪化を知り、嘉朗君の7歳下の次男と一緒に駆けつけたのだ。大野に会うのは京都での講演を聞きに行って以来5年ぶりである。やせた大野を間近に見ると、涙がこみ上げてきた。

2人は何も言わずに約30秒間抱き合った。思い出、労りの気持ちが言葉を奪う。互いの肩が震えている。
嘉朗君の母が言う。
「息子を失い、一番辛かったとき、助けてくれたのが大野さんでした。嘉朗だけでなく私も救われたんです」
どうしてうちの子だけが、こんな目に合わねばならないのか。そう考えた時もあった。周りを憎む気持ちさえ湧き、気持ちが荒れてくる。息子が不憫でならなかった。せめて詩集を出版できないか。その思いを理解し、奔走してくれたのが大野だった。
MAWJは難病の子の夢を実現しようと応援する組織である。親を支援対象にしていない。大野は個人として詩集作りを手伝ったともいえる。そして、その過程で、嘉朗君の母は精神の安定を取り戻していった。
「その恩を全然返せていないのに……。息子の声が聞こえます。『大野さん、こっちに来るのは早いで。まだアカンで』と」
◇
大野は1951年2月、高松市に生まれた。日本はまだ連合国軍の占領下にあった。三姉妹の末っ子で、実家は「魚徳本店」というかまぼこ製造会社を営んでいた。父はその後、市議から市会議長も務めた。
〈手術不可のステージⅣです〉
「忙しい人で、あまり家にいませんでした。私は末っ子でやりたいことをやらせてもらっていました」
勉強はよくできたのだろう。地元の小中学校から名門・県立高松高校に入り、放送部に所属した。上智大学文学部新聞学科に進んですぐ、劇団四季の研究生になった。5期生である。
「文学座で芝居をやりたかったけど、四季の試験に合格したので、そっちに行きました。歌も踊りもできないんですけどね」
劇団での活動に明け暮れ、「大学の勉強は全然しなかった」という。公演のため長崎を訪れたのをきっかけに、佐世保出身の二村勇三と知り合い、恋に落ちる。二村は当時、商社に勤務していた。
74年10月、パレスホテルで結婚式をあげ、翌年長男太郎が生まれた。以降2年ごとに卓、達、輔と男の子4人を授かっている。
二村の転勤で87年から米カリフォルニア州に住んだ。夫のギャンブル好きが原因で91年に離婚し、子ども4人を連れて帰国する。MAWJが設立されたのはその翌年になる。
94年に大野朝男と再婚した。ともにキリスト教徒で、教会での活動を通して知り合った。朝男には交通事故で亡くした先妻との間に、幸子と健一がいて、大野の子どもは6人になった。
◇
大野がMAWJの活動に携わるようになって30年になる。今年2月中旬、みぞおち周りが硬くなっているのに気付いた。痛みはほとんどない。最初は「ヨガで筋肉が付いて来たのかな」と考えるほどのんびりしていた。かかりつけ医を訪ねたのは21日の昼前である。
触診した医師の小林澄子は、すぐにCT検査を受けた方がいいと判断し、総合病院に連絡を入れた。大野がA5判のノートに鉛筆書きで闘病日記を書き始めたのはこの日である。

〈2/21(水) 全てはこの日から始まった〉
仰々しい書き出しの割に、大野は当時さほど深刻に考えていない。
「痛みがなかったから、半分、面白がって日記を付け始めたんです。初めての事態に、これはどうなっていくのかと興味がありました」
その後、何度か検査が繰り返され、病状が判明したのは2月26日だった。肝内胆管がんのステージ4。腫瘍は約7センチに膨らんでいる。リンパ節に浸潤し、転移の可能性もある。手術や放射線治療は不可能で、抗がん剤治療を受けることになった。
大野はこの時初めて、子ども6人に病状をラインで伝えた。
〈皆さんにとんでもないお知らせをしなければならなくなりました。冗談のような話ですが、元気印の私が肝内胆管のガンです。すでに7センチを超え、手術不可のステージⅣです。(中略)あっちゃん(朝男のこと)は本当につらいと思う。支え、祈ってください〉
みんなショックだったのか、しばらく反応がなかった。その後、メッセージが入る。
〈かなりショックが激しく、なんと言えば良いのか分かりません〉
〈何か私たちにできることはありますか?〉
〈良い子にならないでどんどん出して。応援団がいっぱいいるよ〉
◇
インターネットで肝内胆管がんについて調べた。腫瘍の大きさからして、がん細胞ができ始めたのは5年ほど前ではないかと考えられる。新型コロナウイルスの感染拡大前である。
大野はこの間、痛みを感じずに生きて来られたことをラッキーだと思った。闘病日記にはこう記す。
〈神さまありがとう。(がん細胞が生まれた)あの頃わかれば、もっと混乱し、入院しても(コロナ禍のため)誰にも会えず、つらかったと思う。心が痛んじゃっていたよ〉(2月26日)
ただ、気になるのは朝男のことだった。年は大野の6つ上。身長173センチ。物静かで、声を荒らげることはない。花や野菜の栽培を好み、優しさという名の衣をまとったような男性である。大野は日ごろから、「こんな優しい人と一緒にいられて幸せ」と思い、これからの人生は、食事や麻雀をしながら仲良く暮らそうと思っていた。
〈リアリティがないから、あんまりピンときていないだろうけど、あっちゃんのことを思うとつらい。涙が出る〉(2月26日)
そして大野は「自分だけのためにお米を炊くのは寂しいですよ。それを思うとね」と言って、目の端をぬらす。
最期の大野プロジェクト
抗がん剤治療に入ると講演は無理だと考え、予定されていた分についてキャンセルの連絡をした。しかし、2月27日に医師からメールが入る。
「仕事は続けるように」
大野は驚いた。「えっ、ステージ4でも仕事ができるの?」。闘病日記にこう書いた。
〈発想がなかった。ステージⅣでも、何年も生きて、フツーに生活している人もたくさんいる。命の長さより、QOL(生活の質)だ。「今を生きる」という言葉を子どもたちから学んだではないか〉(2月27日)
がんを知った友人から次々と連絡が入った。
「絶対に信じない」
「寝られなかった」
「食事がとれない」
その度に、改めて闘病日記にこう記した。
〈私ごときのために泣いてくれる友のいる有り難さ。幸せすぎる〉(2月27日)
がんになった大野は普段の生活にさえ、幸せを見いだしている。
〈朝男さんとお出かけという日常がまぶしいくらい幸せ〉(2月29日)

〈夜、Taku Family(卓家族)と共にふぐを食べる。丁寧に心を遣ってくれるFamilyがいる。本当に幸せすぎる〉(3月2日)
3月27日からは、がん研有明病院(東京都江東区)で抗がん剤治療に入った。体力が少しずつ衰えていく。31日に教会でイースターの礼拝に出席したが、呼吸が浅く苦しくなる。
大学などで講演を続けながら、自宅ではだらだらと過ごす日が増えた。朝男から「講演を少し控えたら」と気遣われ、大野はこう思った。
「でも、私には時間がないの」
5月の大型連休を過ぎると、痛みも出てくる。
〈昨日から体調が悪い。今までの重いかたまりではなく、ズキンと痛みが走る。熱もある。足に力が入らない。がんちゃんが自己主張してるって感じ〉(5月14日)
終末期医療(緩和ケア)について医者から聞かれたのは5月15日だった。〈そういう段階に近いところにいるんだ〉。
体調は波が大きく、良好な日もある。
〈今日2000歩あるけ感謝。ごはんを食べるのが苦行ではない。お昼何を作ろうかな、なんて思えることが幸せ〉(5月20日)
〈春のなごりの花を摘み、活ける。ああ幸せな時間〉(5月21日)
子どもの夢を応援してきた大野自身が最後の夢と向き合う局面に入った。「種まきおばさん」が最後にやりたいことは何か。まずは講演、そして自著を通して、難病の子どもたちの様子を伝えることだ。
体力の限界から、講演はまもなくできなくなる。そこで浮かんだのが、自著『メイク・ア・ウィッシュ 夢の実現が人生を変えた』を希望者に無料で配ることだった。

本はすでに絶版になっている。そのため自費で500部を刷り直し、それを希望者に無料(協力してくれる人には有料)で届けることを決めた。KADOKAWAに注文すると、本が届くのは6月20日になるという。「最期の大野プロジェクト」と名付け、スタートは6月17日と決まった。
本の注文アカウントを作成し、SNSを通して知人に伝えた。
〈ネットワークをお持ちでさらに熱い思いの一言を添えて、お渡しいただけるのならお贈りしたいと思います。私の今願うところは1人でも多くの人に読んでいただくことです〉
そして祈った。
「神様いいですよね。このプラン、GOですよね。やりきる体力と気力をお与えください」
◇
プロジェクト初日。毎日新聞が報じたこともあり、本を送ってほしいとの連絡が次々と入る。家族や友人たちの力を借りて対応する。
結局、約1週間で計約3000部の注文が入った。自費で刷り直すため、資金に限界がある。ただ、ありがたいことに注文の多くが、有料での買い取りを希望していた。そのため大野は不足分2500部をKADOKAWAに発注できた。
ここで想定外の事態が発生する。KADOKAWAグループがハッカー集団のサイバー攻撃を受け、書籍の受注システムが一時、停止してしまったのだ。追加発注分がすぐには届かない。
大野はその対応に追われながら、むしろ体に精気が宿ってくるのを感じた。
「本当に、頼むよ、角川さん」
「自分が訴えてきたのはうそじゃなかった」
難病の子も、夢の実現を前にすると気力を取り戻す。食欲がなかった子も、笑顔でハンバーガーをぱくつく。その姿が周りを幸せにしていく。夢の実現が人生を変える。そう説いてきたのは間違っていなかった。自分が病になり、それを実感する。夢があると元気になり、それが周りを明るくできるのだ。
しかし、現実は残酷である。6月26日のCT検査で、さらにがんが広がり、すでにあちこちに腹水がたまり始めているのがわかった。抗がん剤は効いていない。大野はその場で、治療を中止して終末期医療に入ると決め、医師に伝えた。大野は言う。
「お医者さんに聞いたところ余命は1カ月という答えが返ってきました。医師は厳しい数字を言うはずなので、自分では2カ月弱かなと、根拠なく思っています」
在宅で緩和を目的とした終末期医療を受けることを決めた。さいわいかかりつけ医の小林は在宅での緩和に対応している。自宅に介護用ベッドが入った。
本の発送にめどが立たない中、大野はこんなことも口にした。
「2500冊の本の発送は、私にはできないかもしれないので、息子夫婦に頼みました。多くの友だちが作業を手伝うと手を挙げてくれています。せめて納品日がわかれば、作業のシフト表までは作っていくことができるのですが。本当に、頼むよ、角川さん」
深刻な話も大野にかかれば、どこか明るい。
7月6日、神戸で最後の講演をやり切った大野は、帰りの新幹線で吐き気に襲われた。車内では何とかがまんできたが、降車直後に吐いた。
2日後の8日も夜には発熱し、3回吐いた。9日に訪問診療した医師の小林から「どんどん楽しいことをやってください。お酒も大丈夫ですよ」と励まされ、「先生、もう一生分飲みましたから」と笑顔で応じた。
時折、背部の左側に痛みを感じるという。小林は静かに言った。
「がんの影響かもしれません」
がん細胞は確実に大きくなっている。
大野は今、朝男と孫のこころ(健一の長女)の3人で暮らしている。こころは大学を休学し9月には、NPOのインターンとしてケニアに行ってしまう。
小林による診察後、リビングにいた朝男は「寿子ちゃんは1カ月、ここちゃんは2カ月でいなくなってしまうんだな」と言って、笑みを浮かべた。ベランダから強い日の光が差し込んでいる。淋しさが作る笑みもあるのだ。
「最期の大野プロジェクト」の追加発注分が届くのは7月27日ごろになりそうだった。医師から言われた通りなら、ちょうど大野の命の火が消えるころになる。
(一部敬称略、つづく)
(おぐらたかやす/1964年滋賀県生まれ。現在毎日新聞論説委員(国際問題担当)。『柔の恩人「女子柔道の母」ラスティ・カノコギが夢見た世界』(小学館)で小学館ノンフィクション大賞とミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞。近著に『35年目のラブレター』(講談社)。)
source : 週刊文春 2024年7月25日号







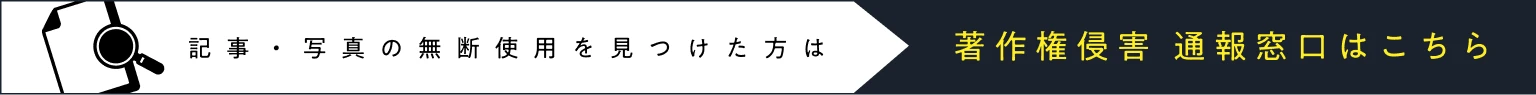
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ