僕の父・三木谷良一は経済学者だった。29歳の時にフルブライト奨学金を受けてハーバード大学に留学し、オックスフォード大学でも学んだ後、日本では神戸大学で長く教鞭を執った人だ。
その父は2013年にガンでこの世を去った。それからもう9年近くが経つけれど、今でも実家には大量の蔵書が捨てずに置かれている。父は本を読むだけでなく、毎日のように日記も書いていた。その日記をふと読み返してみると、僕の幼い頃の話なんかも時々出てくる。亡き父の言葉に触れていると、何とも言えずしんみりとした気持ちになるものだ。
長男、長女、次男の僕という3人の子どもの中で、父は僕の教育に関してはとりわけ放任主義だったように思う。何しろ兄と姉はとても勉強ができたので、二人が盾になって僕はずいぶん自由にさせてもらった。実際、父から「勉強をしろ」といった類のことを言われた記憶がない。
一方で、子どもの頃も大人になってからも、自らの専門分野である経済に関して色々な話をしてくれた。もちろん、相手は経済学の教授だから、僕には学者のようなアカデミックな議論はできない。ただ、その中で父が噛んで含むように教えてくれた経済学の基本は、今でも自分の中に染みつくように残っている。
「この学問は大きく分けると3つしかないんだよ」
父はよくそう言っていた。
マルクス経済学とマクロ経済学、ミクロ経済学の3つだ。その中でも父の専門は、マクロ経済学の「均衡論」だった。均衡論とは、簡単に言えば、経済における需要と供給は必ず均衡していくというケインズ経済学の理論。それに対して、「創造的破壊が企業を成長させる」と言ったのが、以前にもこの連載で触れたジョゼフ・シュンペーターだった。
初回登録は初月300円で
この続きが読めます。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2022年5月26日号







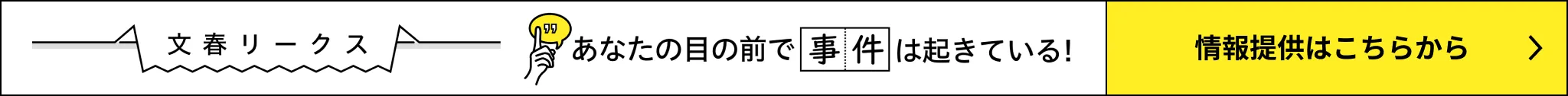
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ