谷川は、時代を塗り替えてゆく羽生との対局に倦んでいた。なぜこの男と戦うと終盤の閃きが鈍るのか……。

第四章 夜明けの一手 其の四
対局時に用いられる記録用紙には棋士の名前の横に段位などを記す欄がある。谷川浩司の場合、この10年近く名人や王将など何らかの冠がついていたが、今、そこに見慣れない肩書きがあった。「九段」。対局場で用紙を目にするたび、自分が無冠となった事実を突きつけられた。
1996年の夏、谷川はいまだ迷いの闇の中にいた。
8月7日、谷川は王座戦挑戦者決定トーナメントの決勝で同い年の島朗と対局し、敗れた。羽生への挑戦権をつかめなかった。将棋会館の対局室が落胆の色に染まる。あの山口県豊浦町で羽生善治に七冠制覇を許してから半年が経とうとしていた。もう、このままタイトル戦に挑戦することさえできないのかもしれない……。かつて味わったことのない感情がよぎった。ライバルとして時代を並走してきた羽生との差が決定的となった事実は、34歳になった谷川の自信を根底から揺るがしていた。
あと10年遅く生まれてくれれば……。羽生に対してそんな屈折した思いを抱いた瞬間もあった。1970年代から1980年代初めにかけて一時代を築いた中原誠は、「名人20年説」を説いている。将棋界で最も伝統のある名人戦は1935年に家元制から実力制への移行を決めたが、それ以降、獲得5期の条件を満たして永世名人の称号を手にしたのは木村義雄と大山康晴、中原誠の3人だけだった。三者の間の年齢差は18歳と24歳。つまり、時代を築く棋士は20年に1人現れ、そうなろうとするならば、前後10歳の相手には力関係の上で負けてはならないという言説であった。
谷川はまだデビューしたばかりの頃、大山を見ていてあることに気がついた。大山と対局する年下の棋士たちの腕が縮こまっているように見えるのだ。大山と対峙した途端、普段の力が発揮できなくなる。将棋がまだ人間と人間の決闘という匂いを残していた時代、大山は盤外での心理戦も含めてあらゆる方法で下の世代を徹底的に叩いたという。勝負師としてトップに君臨し続けるためにはそういう要素も必要なのだと谷川は聞いたことがあった。
初回登録は初月300円で
この続きが読めます。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2023年8月3日号






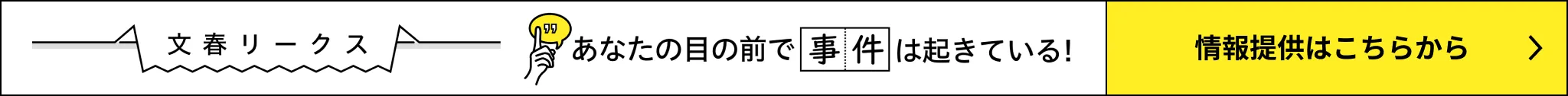
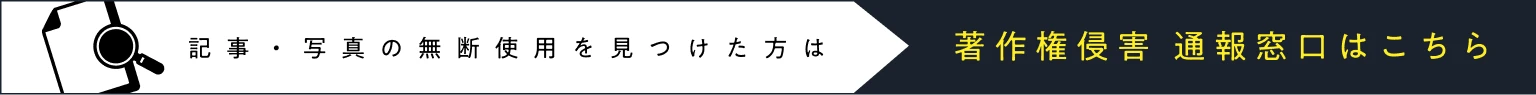
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ