勝負あり――中原や米長ら百戦錬磨の棋士が森内の勝利を確信するなか、羽生だけは回生の手を見出していた。

第五章 王将の座 其の二
タイトル戦中の本部控室には様々な棋士がやってくる。立会人や解説者はもちろんのこと、研究のために訪れる者もいる。棋士たちは常に独りの戦いに身を置いているためか、たいていはニュートラルな空気が保たれるが、そんな本部室が時としてどちらかの対局者に傾いた雰囲気に包まれることがある。第54期名人戦、第4局がそれだった。
1996年5月21日、大阪・難波にそびえ立つ南海サウスタワーホテルの対局室では2日目が始まっていた。七冠王の羽生善治に、10歳の頃から競い合ってきた同期の森内俊之が挑戦することで話題になった七番勝負は開幕局から名人が3連勝した。森内にはもう後がなかったが、その将棋自体は力を失っていなかった。第1局からの内容はすべて紙一重であり、序中盤はむしろ森内のものだった。この第4局でも飛車を振った羽生に対し、真っ向から受けて立った。深い読みに裏打ちされた重厚な指し手は名人を押していた。
今の羽生にこれほど肉薄できる棋士がどれだけいるだろうか……。
対局を見つめる関係者たちには現在の棋界において、森内の力がトップクラスだということが分かっていた。七冠を独占する羽生王朝がいつまで続くのかという危惧も相俟ってか、本部控室の空気は挑戦者を後押しする空気に満ちていたのだ。そして、毎日新聞社学芸部の山村英樹もその中にいた。
「将棋記者にとってのスクープとは、自社主催のタイトル戦で名局が生まれることだ――」
初回登録は初月300円で
この続きが読めます。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2023年8月17日・24日号







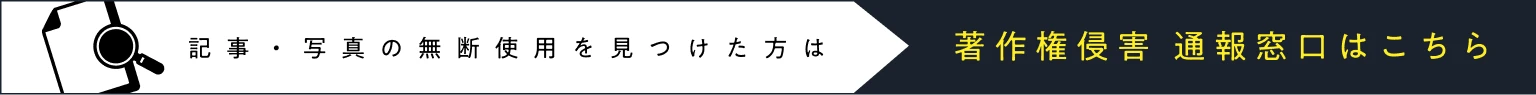
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ