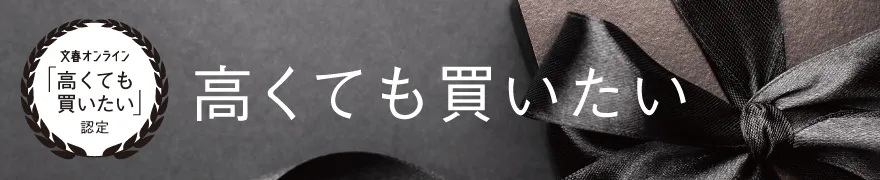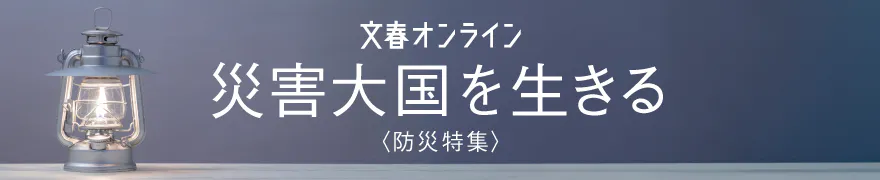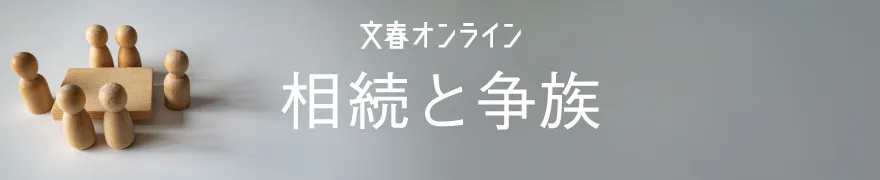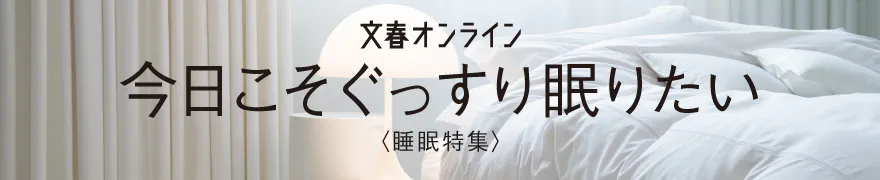道兼が死去した3日後の5月11日には、権大納言で大臣になっていなかった道長を、内覧(天皇に奏上する文書を事前に見る役割で、職務は関白に近い)にする宣旨が下った。さらに、6月19日に道長は右大臣になり、太政官の首班にもなって、公卿の会議を主催するようになった。
こうして道長の世が訪れたことは、結果として、為時に幸いした。長徳2年(996)正月25日、道長が中心になって行われた最初の除目(大臣以外の官職を任命する朝廷の儀式)で、為時はまさに10年ぶりに官を得ることができたのである。
突然「下国」→「大国」に変更
このときの人事の記録である「大間書」が残っていて、そこには越前守に「従四位上源朝臣国盛」、淡路守に「従五位下藤原朝臣為時」と書かれている。
諸国の長官である国守になるためには、一般には、少なくとも従五位より上位である必要があった。為時はずっと六位だったが、正月6日に行われた叙位で、従五位下に叙爵(貴族の爵位に叙せられること)されていたと考えられる。
ただし、日本国内の諸国は、その数が時代によっても異なるが、当時は68カ国ほどあり、国力によって「大国」「上国」「中国」「下国」に分かれていた。越前国は当時、13カ国あった「大国」のひとつで、生産力が高く、京都からも近いので、国守になることを希望する人が多かったのに対し、為時の赴任先とされた淡路国は「下国」だった。
倉本一宏氏は「受領の任官は申文を提出して、そのなかから選ばれるが、十年間も無官で五位に叙されたばかりの為時としては、下国の淡路守くらいが適当だと判断したのであろうか」と書く(『紫式部と藤原道長』講談社現代新書)。
事実、「下国」の場合、従六位下でも国守になる場合があった。すでに従五位下になっていた為時にとっては、淡路守への任命は、降格とさえいえる人事だったのである。
ところが、除目の3日後の1月28日、大きな変化があった。『日本略紀』には「右大臣(道長)参内、俄停越前守国盛、以淡路守為時任之」と書かれている。すなわち、道長の主導で、源国盛を越前守にする人事は急遽停止され、代わりに為時が任命されたという。赴任先が「下国」から一転、指折りの大国に変更になったのである。