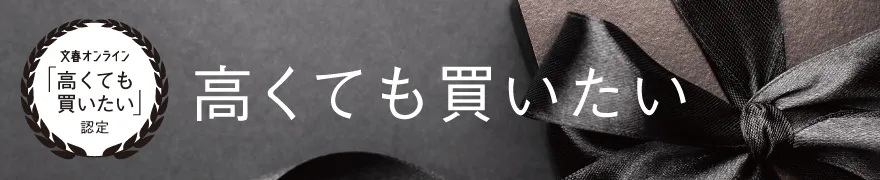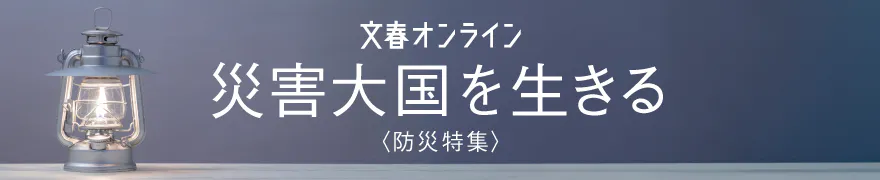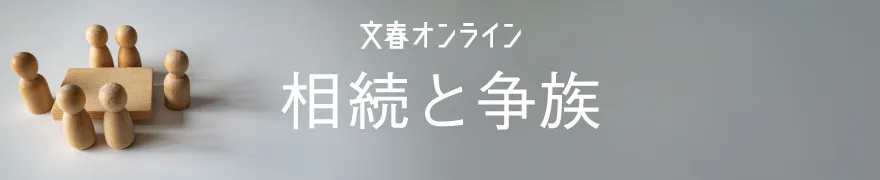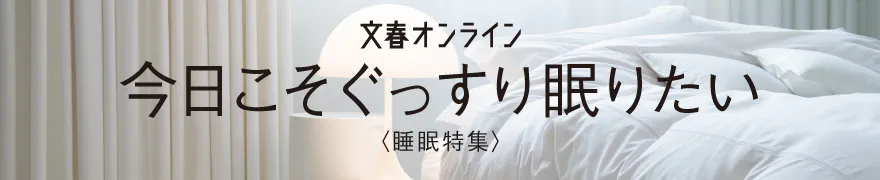漢詩文の能力が奏功した
為時の越前守任官については、『今昔物語集』や『今鏡』などに、説話が載せられている。それらは概ね同じ内容で、『今鏡』に記されている内容を簡単に紹介すると、ざっと次のようになる。
除目で下国の淡路守に任じられた為時は、嘆いて以下の詩を書いた。「苦学の寒夜 紅涙襟をうるほす 除目の後朝 蒼天眼に在り(厳しく寒い夜も学問にはげみ、血の涙で襟を濡らしてきたが、除目の結果を知った翌朝、目には青空が映るだけだ)」。その詩を天皇に見てもらいたくて女房に託すと、一条天皇はすばらしさに感涙し、食事も摂らないほどだった。それを聞き知った道長は、為時を越前守にした――。
むろん説話の内容であり、そのまま史実とはいえないが、為時の漢詩の力が任官につながったことを示唆している。伊井春樹氏は「為時は文才によって越前守を射止めたことになり、学問の重要さがあらためて確認される」と記す(『紫式部の実像』朝日選書)。
また、前出の倉本氏は次のように書く。「この除目の直物(除目の訂正)において二人の任国が交換されたのは史実であるが、実際にはこのような事情で国替えがおこなわれたわけではなく、前年九月に来著して交易を求めていた朱仁聡・林庭幹ら宗国人七十余人(『権記』『日本略紀』)との折衝にあたらせるために、漢詩文に堪能な為時を越前守に任じたものとされる」(前掲書)。
やはり決め手は漢詩文だったことになる。
道長が紫式部に対して好意をもっていたからではない
『本朝文粋』には、「去年(長徳2年)正月の除目」について、「参河守藤原挙直、越前守同為時、各所望の国に任ず」と記されている。つまり、為時は最初から申文には、越前守を希望する旨を明記していたことになる。
為時はこの10年、仕事がなにもなかったわけではない。宮中の儀式に参列し、詔書等を収めるといった記録はあるが、それだけで満足していたはずはない。国守として任地に赴きたいと思っていたのだろう。