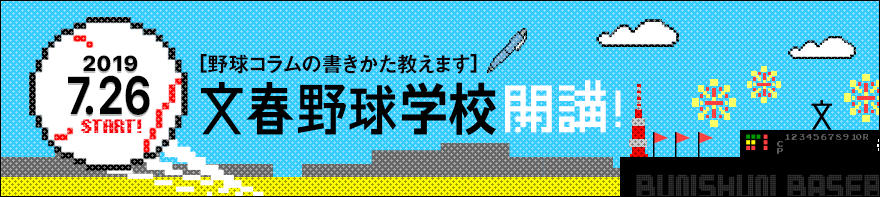「負けねーよ、野球好きさは」と高津は叫んだ
2010(平成22)年12月、年の瀬も押し迫ったある日のこと。窓から差し込む柔らかな冬の日差し、暖房の利いた部屋。東京・新宿の古い小学校をリノベーションして作られた吉本興業の会議室の長机に座っていたのは、当時42歳を迎えていた高津臣吾だった。
つい数週間前に台湾・興農ブルズからの契約解除を告げられたばかりだった。翌11年の去就が定まらぬ中で行われたロングインタビュー。編集部からは、「高津の野球人生を振り返る」というざっくりとしたテーマを与えられていた。聞くべきことを整理した上で臨んだこの日のインタビューは、広島で過ごした幼少時代。当時カープのリリーフエースだった江夏豊に憧れ、初めて彼と対面したときの思い出話から始まり、2番手投手だった広島工業高校時代、小池秀郎という絶対的エースの陰に隠れた亜細亜大学時代について話を聞いた。
そして、野村克也監督率いるヤクルト時代を経て、シカゴ・ホワイトソックス、ニューヨーク・メッツに在籍しメジャーリーガーとして過ごした日々。06年のヤクルト復帰、そして07年オフの突然の退団。その後の韓国、台湾時代について、駆け足に振り返ってもらった。高津はこの1カ月後に独立リーグの新潟アルビレックスBCに入団することになるのだが、取材時点ではまだ去就は決定していなかった。
長きにわたったインタビューが終わって、雑談が始まる。編集者が持参していた見本誌を手に取る高津。すると彼はしばらくの間、それを熱心に読み耽っていた。そして、他球団の選手がどのように評価されているのか、ライバルチームの翌シーズンの展望について、編集者や僕に意見を求めたのだった。ふと、編集者がこんなひと言を口にした。
「ここまで熱心に読んでいただけたのは、阪神の藤川球児選手以来です」
すると、高津はおどけた調子で叫んだ。
「負けねーよ、野球好きさは(笑)」
以来、僕は「高津臣吾」という名前を見るたびに、聞くたびに、この日の彼の言葉を思い出し、「高津臣吾=野球好き」という等式が頭を駆け巡るようになった。そして、2020年シーズン、ついに「野球好き」を自任する男がヤクルトを率いることになった。二軍監督を経て、満を持しての一軍監督就任だった。
高津監督就任は「野村野球復活」ののろしなのか?
先にも述べたように、アマチュア時代は「不動のエース」の地位を得ていたわけではなかった。「エースで四番」ばかりが集うプロ野球選手の中にあって、「控え選手のメンタリティー」を、身をもって体感しているのは強みになるだろう。また、日本のNPBだけではなく、アメリカ・MLB、韓国・KBO、台湾・CPBL、さらに独立リーグ・BCLと、各国、各地域、さまざまなレベルの野球を体験しているのは誰にも負けない、彼ならではの強力な武器でもある。
僕の手元には3冊の本がある。いずれも著者は「高津臣吾」自身だ。1冊は『ナンバー2の男』(ぴあ)、2冊目は『必殺シンカー 変幻自在の投球術』(ベースボール・マガジン社)、そして3冊目が昨年発売されたばかりの『二軍監督の仕事 育てるためなら負けてもいい』(光文社新書)だ。
この3冊はカラーが異なっていて、いずれも面白く読んだ。1冊目は彼の生い立ちが丁寧に描かれている。2冊目は代名詞となった「シンカー」を中心に技術論が詳細に解説されている。そして3冊目は彼の指導者としての資質、哲学が余すところなく述べられている。特に、『二軍監督の仕事』は、「高津監督」の今後を占う意味で重要な示唆に富んでいる。例えば、こんな一節がある。
〈日本・アメリカ・韓国・台湾でプレーしたが、戦略・戦術的な発想という意味では、「野村野球」が根っこにある。ヤクルトのスタッフの中にも、野村イズムに触れた指導者が多いので、話が通じるのが早いし、他球団で経験を積んだ指導者と話すと、考え方の違いが際立って面白い〉
さらに、「僕は『野村野球』がすごく好きだ」と宣言した後に、次のような文章が続く。
〈なぜなら、野村監督は野球の奥深さをとことん追求していたからである。「そこまで考えなくても、ええんちゃう?」と思うようなことも中にはあったが、あらゆる要素を考えて野球をするのが、僕には楽しかった〉
そして、「あまりにいい加減なミーティング」だったアメリカ時代のエピソードを披露した後に、こう言っている。
〈こうした経験を通じて、僕は野村野球が世界に通じるものだと感じるようになった。アメリカの選手や指導者から見たら、「そこまで考えなくても、野球はシンプルでいいんじゃないか」と言われそうではあるが、日本の野球が外国に対して勝つためには、こうしたこだわりが必要なのだ〉
当然、高津監督もまたノムさんの教えを実践することだろう。つまり、「高津監督就任」とはすなわち、「野村野球の復活」の幕開けでもあるのだ。