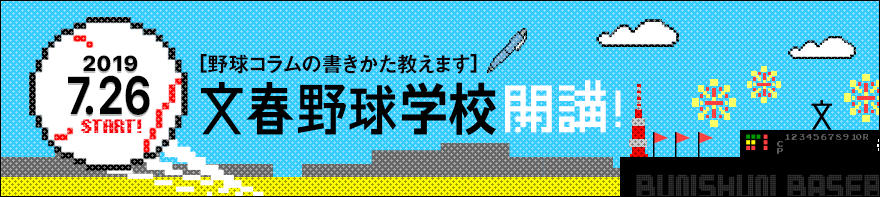諸事情でボツにしたが、削除できなかった原稿がパソコンの中に眠っている。6年前、巨人時代の内海哲也について書いたものだ。
2010年、私は野球専門誌の西武担当として地元・所沢でプロ野球の取材を始めた。それから4年後の2014年、クライアントの要請を受けて巨人担当に配置変えになった。
正社員として雇用されたサラリーマンではなく、あくまで1年ごとの契約ライターだったため、断るという選択肢もあった。本心では西武の取材を継続したく、そう交渉すれば良かった。しかし巨人担当になればギャラが上がることと、フリーランスにとって決して簡単ではないプロ野球の取材証を取得し続けるため、同誌の要請を受け入れた。
担当記者の数が限られる西武には、いい意味で牧歌的な環境がある。プロ野球取材を始めた当時、ヘッド兼打撃コーチだった土井正博さんから何度も聞かせてもらった話は、野球を書き続ける上でかけがえのない財産になっている。
一方、各社が複数の担当記者を送る巨人の環境は、180度異なる。エース記者たちが火花を散らし、新顔にとって決して容易な取材現場ではない。そんな状況に加え、私は同誌との契約以外で忙しくなってきたフリーランスの仕事を優先し、日々のプロ野球取材を完全に疎かにした。クライアントから求められる最低限の仕事しかせず、プラスアルファを生み出せるような働き方をしなかったのだ。
求められることをこなすだけでは、フリーランスとして働く意味は薄い。プロ野球の現場に身を置くのは、極端に言えば時間の無駄だ。来年から、どうやって身を振るべきだろうか。
そう逡巡しながら東京ドームに通った2014年シーズン終盤。情けない私の目を覚ましてくれたのが、内海のピッチングだった。
捕手の意図を、あえてくまなかった1球
前年まで4年連続で二桁勝利を飾った内海だが、2014年シーズンは序盤から苦しんだ。開幕から勝ち星が9試合つかず、左肩の違和感もあって7月までわずか1勝。巨人が3連覇に向けて突き進むなか、左腕は一人取り残されていた。
しかし、8月以降は9試合で6勝2敗と盛り返す。そしてチームがマジック8で迎えた9月19日のヤクルト戦。4回裏に捕手・加藤健のレフト前タイムリーと自身のスクイズで2点を先行すると、勝利投手の権利がかかった5回、内海は真骨頂を見せた。140km/hに満たない速球で左右の打者の内角を果敢に突き、外角へのチェンジアップやツーシームで仕留めていく。ストライクゾーンを幅広く使う投球術と制球力、何より打者に向かっていく姿勢で、この回を三者凡退に抑えたのだ。
とりわけ5回2死、8番・谷内亮太に対して1ボール、2ストライクから内角に速球を投げ込み、見逃し三振に仕留めた1球は見事だった。相手打者にバットさえ振らせず、勝利投手の権利を得て威風堂々とベンチに引き上げていく。その様子を記者席から眺めていると、この1球に込めた意図をどうしても聞きたくなった。
「加藤さんはボールになるゾーンの要求でしたけど、『この球で勝負しよう』と。いい流れでしたからね」
マウンド上と同じく、冷静沈着に内海は言った。捕手のサインにうなずきながら、あえて要求された意図とは違うボールを投げ込み、これ以上ない結果を残した。これぞ内海、という1球だった。
一流のプロ野球選手たちは、一つひとつのプレーに深い意図を込めているものだ。試合の勝敗を分ける1球を掘り下げようという私の取材スタイルは、この日、内海の投じた速球に大きな影響を受けている。