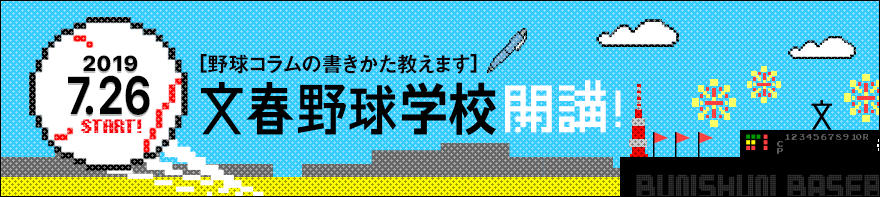1月17日に一周忌を迎えた“ミスタードラゴンズ”こと高木守道。26日には「お別れの会」が催された。
ただ、ある世代以下のドラゴンズファンにとっては、どうしても監督時代の印象が強く、現役時代の印象は薄れつつあるようだ。追悼試合では「10.8」のスコアボードが再現されていたし、昨年、とある野球サイトで行われたアンケート企画「夢のベストナイン・中日編」にも高木守道の名はなかった(二塁手部門で2位)。現在48歳の筆者もそれほど長い期間、高木守道のプレーをこの目で見ていたわけではない。
しかし、このままではあまりにももったいない。現役時代は「プロ野球史上最高の二塁手」の呼び声も高い、走攻守すべてに卓越した名選手中の名選手であることに間違いないのだ。そこで、ここでは選手としての守道さん(あえてこう書かせていただく)の凄さ、素晴らしさを再確認してみようと思う。オールドファンにとっては常識のようなエピソードも、若いファンにとっては新鮮に響くんじゃないだろうか。
ドラゴンズが誇る背番号1の“スペシャル・ワン”高木守道の世界へ、いざ。
プロ野球史上最高の二塁手
守道さんが県岐商からドラゴンズに入団したのは1960年。すでに守備は完成の域に達しており、春季キャンプで守道さんを見た杉下茂監督と天知俊一ヘッドコーチは「あれが高校生のやるプレーか」と驚嘆したという。デビュー戦はその年の5月。二軍戦の後にパチンコ屋で時間をつぶしていたら、主力選手の体調不良で急遽球場へ呼び出された。守道さんは代走で出場して初盗塁を決め、初打席でホームランを打つ離れ業をやってのける。レギュラーの座をしっかり掴んだのは4年目のことだった。
現役生活21年間で守備機会1万1477は二塁手としてNPB歴代1位。試合出場数、刺殺数、補殺数、失策数、併殺数も二塁手として歴代1位。ベストナインは二塁手最多の7回受賞、ダイヤモンドグローブ賞(現・ゴールデングローブ賞)は3回受賞、盗塁王3回、野球殿堂入りも果たした。
ドラゴンズで引退試合を行ったのは永久欠番の西沢道夫、服部受弘についで3人目。名鉄は引退を記念して特急「サヨナラもりみち号」を走らせた。引退して特急列車が走ったプロ野球選手が他にいただろうか。あの星野仙一をして「誰が日本で一番守備がうまいかと言えば、間違いなく高木さんだ。申し訳ないが、他の名手とは次元が違う」と言わしめた。やっぱり守道さんはプロ野球史上最高の二塁手なのである。
こだわりぬいた「バックトス」
守道さんの代名詞が「バックトス」。走者一塁で、ゴロをさばいた二塁手が二塁ベースカバーへ送球するとき、身体を反転させず、右手で正確に押し出すように送球する。努力を重ね、マスターには4年を要した。習得した理由は「かっこいいし、理屈的にも速い」。
試合でミスをしたとき、名将・水原茂監督に「若造があんな生意気なプレーをするな」と叱責されたこともあるが、逆に腹を立てた守道さんは無視してバックトスをやり続けた。守道さんは信念の人だった。
「普通だったらヒットになっている当たりなのに、いつの間にか、そこにいるんだよ。あの人が……」。これはヤクルトの安打製造機・若松勉の嘆き。守道さんはそれぐらい守備範囲が広かった。捕手のサイン、構えたコース、打者の傾向から判断してインパクトの前に一歩目を踏み出していたからだ。ベースカバーにも徹底的にこだわり、一塁へのベースカバーは投手よりも早かった。二塁けん制のベースカバーは「殺意」があったと星野仙一が振り返っている。
打撃も勝負強かった守道さん
守備だけではない。打撃もパンチ力があり、勝負強かった。中日球場のポールにとりつけられたネオン広告に最初にぶちあてたのは守道さん(1967年)。1977年には4打席連続ホームランを放って中日スポーツに「竜の守り神」と書かれた。
勝負強さを遺憾なく発揮したのが優勝した1974年だ。2度の死球による低迷を乗り越えた守道さんは、前半の天王山だった6月28日の阪神戦で逆転サヨナラ3ランを放つ。シーズン大詰めとなった10月11日のヤクルト戦では9回に執念の同点打を放ってマジック2にこぎつけた。9回裏に登板した星野仙一の足が震えるほどの重圧がかかる試合だった。
最終試合ではダメ押しのホームランを放ち、ゲーム差0、わずか1厘差で巨人のV10を阻止してみせた。ナゴヤ球場でファンに胴上げされながら、寡黙な守道さんは初めて声をあげて泣いたという。