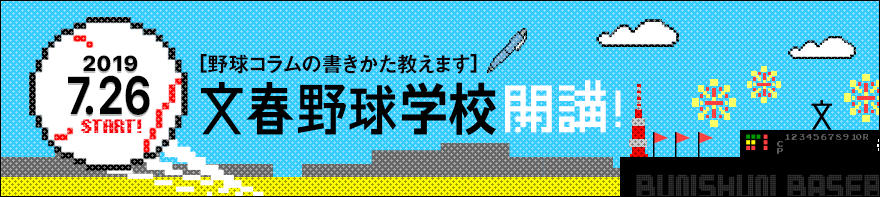「呼ばれてもいないのに海を渡った野球人」の連載最終回は、横浜国立大出身にして最もぶっ飛んだ「海外押しかけエピソード」を持つ清水広貴を紹介する。
学生時代のあだ名は「プロ注」
昭和53年に横浜市で生まれた清水は小学4年生から友人の誘いで野球を始めた。地元の公立校で小中高を過ごし、高校最後の夏は神奈川大会2回戦で敗れた。そこで清水は「プロ野球選手になろう」と考えるようになった。あまりにあっけなく高校野球を終え「誰よりも真面目にやるという感じではなかった」というそれまでの姿勢を強く後悔した。そして「本気でやる=プロ野球選手になる」とすぐイコールで結びつけられる貪欲さが清水のその後の野球人生を突き動かしていくことになる。
一浪を経て入学した横浜国立大では同期に北川智規(元オリックス)がいたこともあり、4年間をレベルの高い神奈川大学野球1部リーグでプレーすることができた。当時のあだ名は「プロ注」。入学前から「凄い奴が入るらしい」と噂になっていた北川と違い、実績皆無の清水が入部当初から一貫して「プロになる」と公言して憚らなかったのは、周囲から見ればおかしく見えたのかもしれない。
本気になった清水はジムと契約して毎日ウェイトトレーニングを行うと「チームの中で北川と僕だけがどんどんムキムキになりました(笑)」とパワーアップ。2年春はオーバーワークがたたり左肩を痛めてしまったが、2年秋には4番を務めて本塁打を放つまでになった。しかし3年春から4年春にかけてまったく結果が出なかった。
「これではどうしようもない……」。そう感じた清水。通常の人間であれば一般の就職活動を始めるか勉学を深めるために大学院に進むなどが大方の行動だろう。だが清水が取った行動は台湾に行くことだった。
4月に台湾プロ野球の全球団へ「お金は要りません。まずは練習生でいいから雇ってください」と手紙を書き、6月に全球団の事務所に直接押しかけた。
なぜ台湾だったのか?
「当時、日本人選手のドキュメント番組か何かで台湾プロ野球のことをやっていたんです。こんなところがあるなら行きたいな、できるかなと思ったんです」
そんなこともあり、横浜中華街で働いたり、中国人留学生のチューター(世話役)をして中国語を覚えていた。実際に台湾に行ってみると言葉は通じず、結局は拙い英語で交渉をした。
「僕の働いていた中華街のお店は福建語だったので意味は無かったです(笑)。でも中国語圏の雰囲気は分かってから行ったんで良かったですよ」
この細かいことは気にしない大らかさも清水の武器だ。「中に“入れた”というより“入っていきました”(笑)」という名も無き日本人選手の突然の押しかけに対して、当然門前払いの連続。台北、台中、台南、高雄と台湾中を回ったが、何の収穫も無く帰国した。
練習参加を求めて署名活動
「どうやったらプロに行けるかしか考えていませんでした」と振り返るように、それで挫けるような清水ではない。復調してある程度の成績を残せた秋季リーグの後に再び全球団に手紙を出した。すると2つの球団から返事はあったが「雇いません」、他球団は「無視」だった。だがCPBL(中華職業棒球大聯盟)のコミッショナーにも手紙を出したところ副コミッショナーが「中信ホエールズに日本人通訳がいるから彼に相談してみたらどうだ?」と返事をくれた。そうした流れから、なんとか練習生契約を勝ち取った。
卒業式も参加することなく1月から台湾へ。練習生とはいえ無給で基本的には打撃練習の際の投手や捕手、ボール拾いといった雑用がメインだった。昼食の際やチームバスで選手たちが帰った後にひたすら打ち込み、徒歩で帰った。そんな姿を見た監督が「それだけ練習するなら試合に出してやる」と言ってくれて、社会人や大学のチームも混じった教育リーグ15試合に出場し首位打者と盗塁王になった。
そこで「契約は無理だとしてもみんなで一緒に練習をさせてくれ」と監督に懇願。監督が「練習生のお前が練習すると他の選手が嫌がる」と言うので、選手全員の「練習をしてもよい」という署名を集めた。だが提出する前にその動きがバレてクビになった。
「心が折れないというか……そういうことを繰り返していただけですから。諦めるという選択肢がまったく無かっただけですよ」