
私はかつて、とある中堅どころの出版社で雑誌の編集者をしていた。
社名も、当時携わっていた雑誌の名前も伏せる。ただ、低俗なことで名を馳せたゴシップ誌や、「お菓子系」などと呼ばれていた男性向け雑誌、老舗アダルトゲーム誌を刊行する出版社だったことは明かしてもいいだろう。編集部員は概ね「インテリ」「不良」「オタク」の3種類に大別されたが(厳密には「不良」と「オタク」の間にはグラデーションがある)、私はそのどれでもない半端者だった。だからこそ、今はこうして小説家などという浮草稼業で糊口を凌いでいるのかもしれない。編集部の体質や雰囲気は出版社ごとに異なるものだが、私が勤めていたところは激務ながらユルかった。終電や泊まりの勤務が常態化していたが咎めるものは管理職にもおらず、場所は限られていたが煙草も吸えた。「資料」と精算書に記せば大抵の本やDVDを経費で落とせた。
自社ビルはオンボロだった。編集部は散らかっていた。会社で寝る時はワーキングチェアを並べてその上で寝るか、隅で段ボール箱を畳んで敷き、タオルケットに包まって寝る。仮眠室のベッドはいつも埋まっていて、しかも不潔だったからだ。出版不況もあってか新規採用はアルバイトすら年々減り、一方で業界に見切りを付けて辞める人間は後を絶たず、慢性的な人手不足に喘いでいる。そんな世界だった。
以下はそうした編集部オフィスで私が体験した、ある深夜の出来事を、できるだけ記憶に忠実に書き起こしたものである。およそ十七、八年前、2000年代後半のことだ。
※ ※
午前1時。雨が降っていた。
私はパソコンに向かって、自分の担当ページの原稿を書いていた。よくも悪くもDIYが推奨される社風で、ライターに出す意義のない文章は編集者が書くのが当たり前だった。あと1時間くらいで書き終わるかな、と思ったところで、声を掛けられた。隣の編集部の先輩、山重さんだった。一緒に仕事をしたことはないが、給湯室で喫煙しながら雑談する程度には親交があった。
初回登録は初月300円で
この続きが読めます。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2024年8月15日・22日号








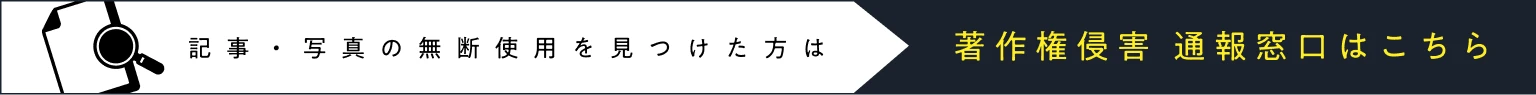
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ