京都というのは本当に不思議な土地だなあと訪れる度に思う。歴史ある神社仏閣が徒歩圏内にごろごろと鎮座し、御所の石を踏めばその音は千年前から変わらぬよう。その一方で、河原町の商店街はあっという間に店並びが変わり、学生たちは後ろ髪を引かれながら順番に旅立っていく。変わらないようでどんどん変わりゆくその街は、いつしか思い出の中とはどこか決定的に違うものになってしまった。変わらぬものなどないのだと、無情にも無常を突きつけてくるようなその街だからこそ、ローズの心をこんなにも揺り動かしたのだろう。『薔薇が咲くとき』には、そんな京都の風情が、諦観が、美しさがぎゅっと詰まっている。
精神的に病んだ母は自殺し、可愛がってくれた祖母が他界してからは死んだように生きてきた40代のフランス人女性・ローズの元に、生前一度も会うことのなかった父の訃報が届いた。相続の手続きのためしぶしぶ京都に向かったローズは、美術商だった父のアシスタントのベルギー人男性・ポールと共に父の指定した寺をめぐることになる。
京都に住んだこともあるフランス人小説家ミュリエル・バルベリの『京都に咲く一輪の薔薇』のコミカライズである本作。大判で左開きの作りはいかにもバンド・デシネのようで、フルカラーで描かれる京都の情景がうっとりするほど美しく、ページの端々から空気や匂い、湿度といったその土地の持つ情緒までもが漂ってくるよう。マンガを担当した高浜寛の雰囲気ある画風はどこか物悲しさのようなものを湛えていて、異邦人たるローズの眼差しも相まって京都案内のようなマンガとは異なる印象を与える。
龍安寺の石庭の壁の色をローズが黄金色と表現し、「あの壁がこの庭を作っているのね」と話す様子に、ただはげた土壁の色だと気にも留めず、自分が当たり前に見落としていた美しさにハッとさせられた。一方で石庭を巨大なネコのトイレみたいという素直すぎる表現にはこらえきれず笑ってしまった。これ以降、龍安寺を訪れる度にその言葉がちらついてしまう気がするなあ。
思春期か?と思わず戸惑ってしまうほどにキリキリと己の不機嫌を隠す気もないローズの様子はどうしたって空気を重んじる日本人のキャラクターには見られないもの。ひねくれていながら感情表現の素直な様子には好感すら覚えた。もっとも、彼女に京都を案内したいかと問われたら別だけれど……。ローズは「感じ悪い女。そんな風に描いてね」という原作者からの言葉があったと知って思わず納得した。
それぞれの寺の由来や思想を学びながら、この世という地獄をどうやって生きていくべきかと思案するローズ。父を知り、他者と会話し、異国で己を見直すことで停滞していた空気がだんだんと浄化され、やがて新しい道へと進む勇気を得るまでの様子が丁寧に描かれる。己の哲学的な考えをしっかりと言語化する登場人物たちのセリフひとつひとつに芯があり、噛みしめたくなるものばかりであった。
ああ、なんだか京都に帰りたくなってきた。京都で学生時代を過ごした私の魂の欠片は、多分鴨川の底にある。きっとこの先必ず訪れるであろう喪失や絶望と対面した時に、迷わず京都に帰ろう、そしてその時にこの本が手元にあれば、きっと助けになってくれる気がした。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題

キャンペーン終了まで
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2024年10月24日号








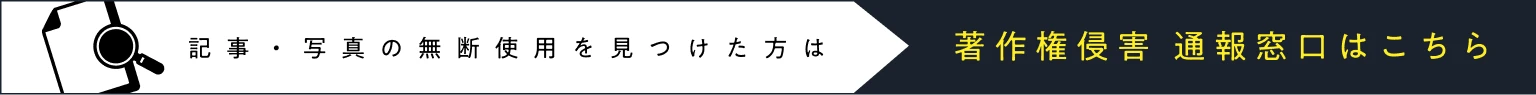
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ