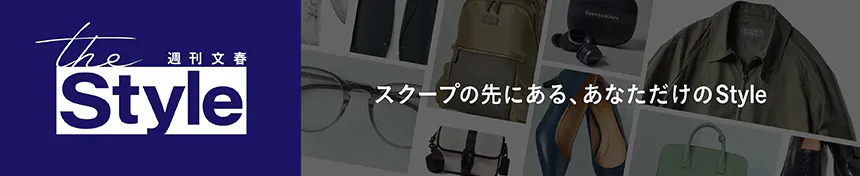どうやら生命体であろうことは見て取れるのだ。目があり口があって、手足らしきものも確認できるので。ただ、これらがどこからやって来たものなのかは、さっぱりわからない。
「太古の遺跡から発掘されたばかりの代物である」、そんな触れ込みで紹介されればもちろん信じてしまうだろう。または、「じつはタイムマシンで未来から送られてきたのだ……」と言われても、すんなり納得してしまいそう。
そんな不思議な存在と出逢えるのが、原美術館での「加藤泉―LIKE A ROLLING SNOWBALL」。
不気味、でも、ちょっとかわいいかも?
加藤泉は1990年代から画家としてのキャリアをスタートさせ、のちには彫刻も手がけるようになった。絵画、彫刻とも作風は変わらない。多くの場合、不思議な生命体がモチーフとなって、ドンと作品の中心に存在するのだ。
ことしに入って制作したものばかりという今展出品作も、不思議な生命体の姿ばかり。それらは意思が通じるのかどうかも定かでない外観をしているけれど、対面してとくと眺めると、意外にかわいらしい表情とポーズをしていることに気づく。会場をひと通り観て回ると、すっかり愛着が湧いて、離れるに忍びない気分にさせられてしまうのだった。
そうしてすっかり目が慣れたあとも、やっぱり疑問は残る。この生命体たちはいったい何なのか、と。全69点におよぶ絵画、彫刻に現れている姿を改めて眺め渡し気づくのは、いつもそこに「幼なさ」が含まれていることだ。何かを一心に見ているのか、または何も見ていないのかわからないその眼には、赤ん坊の眼を覗き込んだときに感じるのと同じ純真さが宿っている。
また、細部まで描き込んだり彫り込んであるわけではない素朴な表現ゆえ、そこには「ものをつくる原点」が詰まっているのも感じる。先史時代の洞窟壁画や、縄文時代の土偶などに触れたときに伝わってくる、湧き上がるような力強さを思い起こさせる。