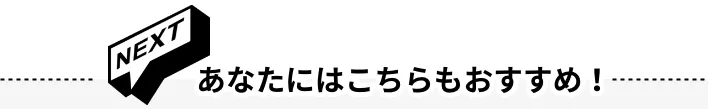これで本当に清原和博という人物を表現したことになるのだろうか
夏が来るたび、清原さんは高校時代を過ごした1980年代へと戻っているようだった。誰しも、10代の頃の葛藤や郷愁を胸に宿しているのかもしれないが、清原さんほど生々しく、今現在に影響を及ぼしている人がどれくらいいるだろうか。私はそこに、ある種の極端な無垢さと危うさを見ていた。それが大人になってからの清原さんと社会とを隔てているものかもしれない、とも感じた。
書き手として清原さんの取材を始めたのは、覚せい剤取締法違反で逮捕された直後の2016年だった。以来、輝かしいホームランの過去を書いたことも、闇から這いあがろうとする本人の独白を綴ったこともあった。だが、どれも一寸、どこかに違和感があった。
これで本当に清原和博という人物を表現したことになるのだろうか……。
その末に、人間としての弱さや矛盾、巨大な揺れを書くことが答えではないかと思うに至った。言葉にするなら「虚空」のようなその部分にこそ清原さんの引力があると感じたからだ。
清原さんとの“別れの書”に込めた願い
今年の夏も清原さんから唐突に音信があった。7月終わりの暑い日、携帯電話に1枚の写真が送られてきた。そこには清原さんが写っていた。高校1年の夏に甲子園で対戦した、ある投手と肩を並べていた。40年ぶりの再会。清原さんはこの夏もまた、あの頃に戻っているようだった。それは微かな前進のようであり、停滞のようでもあった。人間は必ずしも前に進み続けなくてもいいのではないか。正しくなくてもいいのではないか。獲得ばかりでなく、喪失があってもいいのではないか。清原さんの写真を見ながら、そんなことを思った。
今まで、何らかの社会的使命感があって清原さんを書いてきたわけではない。むしろ、私自身の弱さや卑屈さを包み込んでもらうためだったのかもしれない。
いわば別れの書に込めた願いがあるとすれば一つ。清原さんがこれから生きていく社会に、強さや正しさばかりを求めない寛容さがありますように。