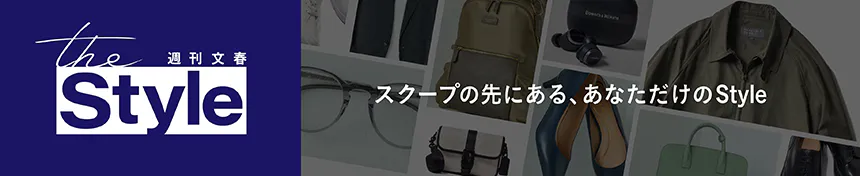江戸時代の“大都会”長崎で行われた「裁き」を記録した「犯科帳」。長崎奉行所が行った200年分の刑罰の申し渡し、不処罰の申し渡しが記されている貴重な資料である。
ここでは、そんな「犯科帳」を読み解く『江戸の犯罪録 長崎奉行「犯科帳」を読む』(講談社現代新書)から一部を抜粋。夫を殺された女性が犯人の助命を嘆願した。現代の常識からはなかなか考えられない事態だが、実は江戸時代から今に繋がる社会問題が関わっていた――。(全4回の4回目/続きを読む)
◆◆◆
現代とは異なる夫婦間の責任
男と女の関係としては夫婦もある。現代と「犯科帳」の時代とでは、この関係についての認識にも異なる面があった。
常吉と「みつ」という夫婦がいた。夫の常吉は精神を病んでいて療養していた(「気分不揃躰ニ有之療用手当いたし」)が、天保11(1840)年3月21日夜、妻「みつ」が常吉の薬を取りに出かけた留守中に剃刀で自殺した。
現代の社会では、「みつ」が咎められることはないだろう。しかし、常吉を一人にしたことが咎められ、「みつ」は「心づけ不行き届き」として奉行所に𠮟責(「急度𠮟」)されている(森永種夫編『長崎奉行所判決記録 犯科帳』第8巻388頁)。
病人に常時つきっきりでいることは、どの時代でも無理だろう。ましてやこの事例では、夫の薬を取りに行くために夫を一人にせざるを得なかったのだった。しかしながら、そのような致し方のない理由があったにもかかわらず、「急度𠮟」といった程度のものではあるとしても、甘んじて罰を受けなければならなかったのだ。
貝原益軒の『女大学』に「婦人は、別に主君なし、夫を主人と思ひ、敬い慎みて事(つかう)べし。軽しめ侮るべからず」とあることをふまえると、いかなる場合にも妻は夫に従うべき、いかなる事情があったとしても妻は夫の身を護るべき、というのが社会の「モラル」とされていたと考えるべきだろう。