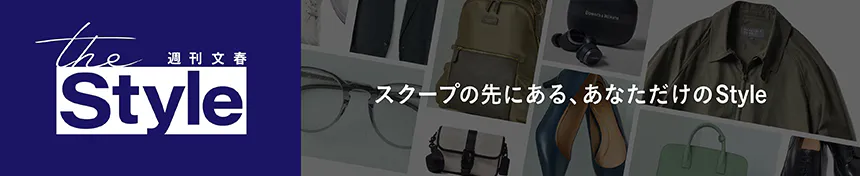忘れられない体験がある。昨年6月の東京都議選を現場で見たら、排外主義的な演説が多いことにギョッとしたのだ。その「流行」は直後の参院選にも引き継がれ、しかも語られている内容には事実と異なるものが少なくなかった。
公的な場で政治家や候補者が、ヘイトのような言葉を平然と口にする。すると「そうか、言ってよいのだ」とスイッチを押された人が出てきても不思議ではない。8月のホームタウン騒動は記憶に新しい。今回の衆院選でも「移民受け入れ反対」を掲げる党や候補者がいた。私が現場で耳にしたのは、「ヨーロッパのような移民政策はダメだ」という大声だった。
しかし、欧米との比較はナンセンスなのである。本書『ニッポンの移民』は、これをはっきり否定する。ヨーロッパで永住型移民に占める家族移民の割合が高いのは、たとえば旧植民地からの移住が多く、その多くが家族呼び寄せによるものだからだ。一方、日本で中心なのは永住型の労働移民である。構造がそもそも違うのだ。
にもかかわらず「同じことが日本でも起きる」という言説だけが独り歩きする。本書は、日本がすでにリベラルで開放的な移民政策を採ってきたことを統計と国際比較で示す。その一方で、「移民政策の不在」というイメージと、「着実な定住化」という現実との間に大きな乖離があることを指摘する。そのパラドクスに向き合うのが本書なのである。
ただ、リベラルな移民政策とはいえ、技能実習制度は単純労働者の受け入れを禁止するタテマエを維持するための、いわば方便だった。結果的にこれがロースキル人材を永住に向けたルートに載せるという、《国際的に見ても極めて稀な「意図せざる結果」を生むことになった》というくだりには考えさせられる。
終章「吹き荒れる排外主義の中で」には強い切迫感が漂う。かつて人権を基調とした議論が主流だったOECDの会議で、著者が参加した場では受け入れ抑制が中心テーマになっていたという。さらに、あとがきの追記では、日本政府が「総量規制」や外国人の「管理と排除」を前面に押し出し始めたことにも言及する。
著者が警鐘を鳴らすのは、こうした主張の前提にある事実認識がいかに現実から乖離しているかという点だ。不安という感情と、事実がそうであることは別だ。その区別を曖昧にした「主張」は、選挙向きではあっても政策にはならないのではないか。
日本はすでに移民国家である。その現実を直視せず、わかりやすい物語に身を委ねたとき、本当に得られるのは安心なのか。本書は、ぼんやりとしたイメージでしか語られてこなかった「日本社会における移民」を知るための格好の一冊である。政治家にこそ読んでほしい。
これかわゆう/1978年、青森県生まれ。国立社会保障・人口問題研究所国際関係部部長。東京大学大学院人文社会系研究科修了。OECD移民政策会合メンバー。著書に『移民受け入れと社会的統合のリアリティ』など。
ぷちかしま/1970年生まれ。長野県出身。お笑い芸人。著書に『お笑い公文書2025 裏ガネ地獄変』など。