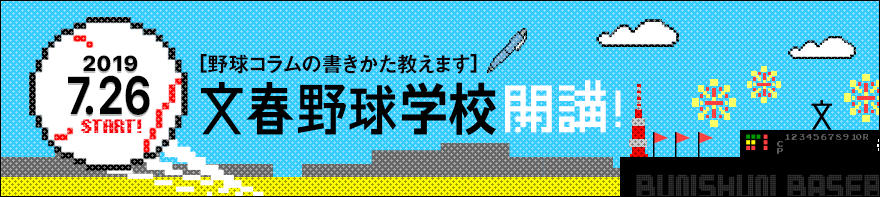プロ野球にとって、かつてない長い長い“冬”が終わりを告げ、待ちに待った2020年シーズンが間もなく幕を開けようとしている。高津臣吾新監督を迎え、意気揚々と船出しようとしたところで足止めを食らっていた新生・スワローズも、例年よりも短い120試合の航海にようやく出発する。
筆者はヤクルトの取材を始めて今年で11年目になる。毎年、シーズン前に願うのが「選手が1人もケガをしませんように」ということだ。もちろん優勝してほしいのはやまやまだが、まずはどの選手も大きなケガだけはせず、悔いのないようにプレーしてほしいという思いがある。キレイごとに聞こえるかもしれないが、その思いはヤクルトのどの選手に対しても変わらない。ただし、今年に関していえばその思い入れが少しだけ強い選手がいる。
プロ18年目、来月で36歳になる坂口智隆だ。
左手親指骨折という思いもよらぬ悪夢
坂口がオリックスから移籍してきたのは15年オフ。間近で見るようになって、これほどプロ意識の強い選手もなかなかいないと思った。とにかく試合を休まない。ヤクルトに来てからの3年間で、登録抹消はインフルエンザによる1度だけ。移籍1年目の16年シーズン終盤は、体に痛みを抱えながら出場
そのシーズン、故障者が相次いでほぼ控え組で戦わざるを得なくなった時期には「『東京』って名乗れるほどの花形はいない。『下町スワローズ』の魂を見せてやろうぜ!」と、若手を鼓舞したこともある。18年には青木宣親の復帰で外野のレギュラー候補が4人になると、「中学生以来」という一塁での起用を受け入れ、これをそつなくこなして8年ぶりの打率3割をマークしてみせた。見た目もそうだが、やることなすことカッコいいのである。
その坂口を昨シーズン、思いもよらぬ悪夢が襲う。開幕3戦目に死球を受け、左手親指を骨折したことが始まりだった。リハビリを経て、ファームで7試合に出場して打率.375を残し、満を持して5月17日に1軍復帰。ところが、バットからはなかなか快音が響かない。左手親指の骨折はバットマンの繊細な感覚を狂わせ、それを元に戻すのは我々が思っている以上に困難なことだったのだ。
復帰後の19試合で54打数5安打、シーズンの打率が.125まで落ちると、小川淳司監督(現GM)は坂口の2軍再調整を決断。記者に囲まれ「責任感が強いし、苦しかったと思う」と話す指揮官の表情には、苦渋の色がにじんでいた。
「若い時のケガのようにポジティブに受け入れるっていうのは難しかったですね。ましてや1軍に上げてもらったのに、結果がまったく付いてこなかったっていうのは、すごく自分の中でもネガティブな要素で、折れそうになるところだったと思います。ケガをしたことよりも、自分の状態に対するもどかしさというか歯がゆさがありますね」
坂口からそんな話を聞いたのは、2軍降格から1カ月半近くが経った頃のこと。その時点で、ファームでも打率.217と苦しんでいた。そこで、あらためて彼が2軍で取り組んでいたのはバッティングを「元に戻す」ことではなく、新たに「一からつくり上げる」ことだと知り、愕然とした。
「もう(ケガをする)前には戻れないんで、腹を括っていろいろ試しながらやるしかないッス。今の(ケガをした後の)体でどうやったら打てるのかを地道に、丁寧にというか、ブレずにやっていくしかないですね。これだけバッティングのことを四六時中考えたこともないし、もう一度見つめ直すいい機会と思って、どれだけ時間がかかってももう一回結果が出るようにやりたいなと思います」
表情はいつもと変わらなくとも、苦悩していることは一目瞭然。それでも「故障してなくてもこうなっていたかもしれないし、故障があったから得た変われるきっかけでもある。残り何年かの野球人生の中で、新しい自分をつくるチャンスでもあると思うんで、なかなかポジティブな結果にはならないですけど、信じてやるしかないです」と前向きに語る姿は救いだった。