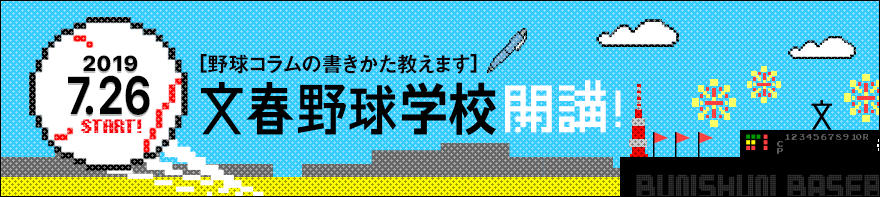恩師だからこそ、内面の変化に気が付いた。昨年末、広島・小園海斗内野手が挨拶のために母校の報徳学園を訪れた日のことだ。例年通り、年末に母校で体を動かす姿を眺めていた大角健二監督は、ひそかに感心していた。「小園、変わったな」。技術の話ではない。集中力に驚いていたのだ。
小園はグラウンドの端で一人黙々と打撃練習に励んでいた。オフの間であれば許されるであろう、リラックスして打撃を楽しむような姿には見えなかった。スイングの軌道、タイミングの取り方、体重移動、トップの位置――。一球一球を無駄にせず、高い意識を持って練習に取り組んでいることは、その真剣な眼差しから伝わった。
チーム内で絶対的な存在だった小園をベンチに下げた日
プロ野球選手になって4度目のオフを迎えた。これまでのオフに母校を訪問した際は、練習相手の元同僚とともに明るい雰囲気の中で体を動かすことが多かった。どちらが正解という話ではない。ただ、例年と異なる雰囲気を身にまとっていたという事実が確かにそこにはあった。一方で休憩時間に見せる無邪気な笑顔は、高校生の頃と何ら変わっていなかったのもまた事実だった。
大角監督は、教え子が高校を旅立った日が遠い昔のように感じてしまう。「1年目のオフに学校に来たときは、同学年の選手と一緒に戯れていたから、その輪の中のどこにプロ野球選手がいるのか分からなかったのにね」。いまでは、小園がどこにいるか一目瞭然だ。「もう打球音がすさまじいことになっていた」。練習姿勢が変わると、打撃も変わった。
精神面の成長は、恩師を喜ばせているに違いない。高校時代は凡退が2、3打席続くだけで集中力を欠いた。ベンチで声を出さず、自分一人の世界に閉じこもってしまうこともあった。高校3年時の練習試合では、ベンチ内で下を向く姿を心配した主将の神頭勇介から声を掛けられて、「ほっといてくれ」と思わず反発してしまったことがあった。そして、小園と中学時代から同僚だった主将は監督に進言した。「小園を代えましょう」。監督はその意見を認めて、チーム内で絶対的な存在だった小園をベンチに下げたこともあった。
プロでは下を向いている暇すらない。1年目の19年、敗戦に直結する適時失策を犯した試合後にベンチ裏で悔し涙を流した。その姿を見かねた緒方孝市監督から伝えられた。「明日があるのだから切り替えなさい。落ち込むのではなくて、明日のための対策をしたり、どうすればチームに貢献できるかを考えなさい」。目先の結果に一喜一憂していた若さに、少しばかり大人の一面が加わった。それから毎年のように好不調の波の大きさに悩まされながらも、どん底に陥る度に懸命にはい上がってきたのだ。