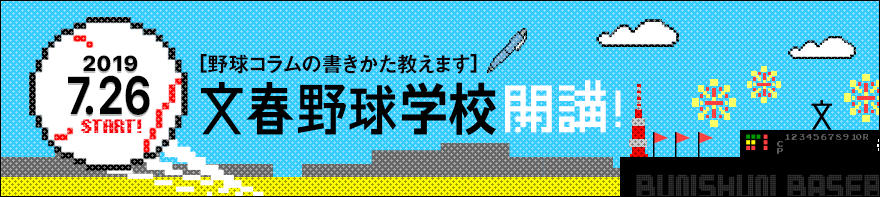みなさん、こんにちは! 埼玉西武ライオンズOBの米野智人です(ヤクルト→西武→日本ハム)。
ライオンズの本拠地ベルーナドームのライトスタンド後方にピンク色のお店「BACKYARD BUTCHERS」を出店し営業しております。いつもご来店くださっている皆さま、誠にありがとうございます。
一昨年の2021年から始めたお店も今シーズンで3年目を迎えることができました。これも皆さまのお陰です。心から感謝しています。
6月に入り、梅雨入りして雨の日も多くなってきた。野球をプレーする選手にとっても、観戦するファンにとっても、スタジアムグルメを楽しむためにお店に並ぶ方々にも……少し不快指数が高まる時期だ(笑)。
交流戦ではペナントレース制覇に向けてとても大事な試合が続くので、選手、そしてファンが一つになって戦っていくことが大切になる。
5月の月間成績は7勝16敗1分けとなかなか波に乗れていなかったライオンズだが、交流戦の開幕カードでセ・リーグ首位の阪神タイガースに勝ち越すなど、少しずつ本来の姿に戻ってきたように感じる。
渡部健人、長谷川信哉など期待の若手選手の活躍もとても嬉しいが、まだまだ経験を積んでいる時期なので、シーズンを通してずっと安定して活躍するのは難しい。やはり一軍で打席を重ねて初めて見えてくることがあるので、“元選手”としては温かい目で見守ってほしいと思ってしまう(笑)。
そんなライオンズだからこそ、やっぱりこの男がチームにいてくれたら……という思いが強くある。
今年、プロ10年目の岡田雅利。
ライオンズファンならご存知の明るいキャラクターで、いるだけでチームの雰囲気が明るくなるムードメーカーだ。
キャッチャーの過酷さ
岡田は今年3月、左膝関節にかかる荷重位置を修正する大腿骨・脛骨骨切り術という大きな手術をして、来シーズンからの復帰を目指して現在はリハビリに奮闘している。戦線から離れて一人でリハビリをするのは、周囲が思っている以上に辛いものがある。
経験者だからわかるが、キャッチャーは過酷なポジションだ。プロ野球という世界でキャッチャーとしてパフォーマンスを発揮するには、まず身体が頑丈でなければ通用しない。
さらには頭も使い、精神的にもタフでなければ一軍のプレッシャーに押し潰されてしまう。
僕はヤクルト時代の2006年、古田敦也兼任監督の下でキャッチャーとして116試合に出場した。プロ野球という世界で1シーズン戦い抜くことは初めての経験で、体力、精神力ともに想像以上にキツかった。休みの日でも長距離移動があり、次の試合のことを考えて気が休まることはなかった。
相手チームのデータや味方の投手のデータや調子を整理し、次の試合の準備をする。それはキャッチャーという責任のあるポジションの宿命でもある。
なんで俺はキャッチャーになってしまったんだろう……。
正直、そう思うこともあった。
守備時は常にプレーに関わっていて、試合開始から終了まで集中力を保たなければ、思いもよらないミスでチームの敗戦に直結するポジションだ。
僕はライオンズに移籍して2年目の2011年秋、外野手にコンバートされた。
初めて外野手をやってみて、守備機会が少ない中で安定した守りを続けることと、打撃で結果が出ないとすぐに出場機会を失うという難しさを経験した。
それでも、キャッチャーに比べると、負担ははるかに少なかった。
試合前の準備が、キャッチャーと比べてこんなにも少なくていいのか!
そう思うほど、楽に感じられたものだ。
2006年にキャッチャーとして1シーズン出場した時は、8月頃から身体と精神のバランスが狂い、成績もガタッと落ちて、焦る気持ちをコントロールすることは当時まだ未熟だった僕にはできなかった。
キャッチャーは身体にかかる負担も大きい。岡田が膝に負った怪我は、キャッチャーとして“致命的”とも思えるようなものだ。
それでも岡田はメスを入れ、1年以上のリハビリをしてまで、キャッチャーとしての復帰を目指している。常識的に考えれば、無謀な挑戦かもしれない。
しかしキャッチャーというポジションには、経験した人にしか分からない喜びがある。たとえ自分が4打数0安打に終わっても、チームが勝利してマウンドで勝利の輪ができた瞬間、キャッチャーは最高に嬉しく感じられる。
だからこそ、キャッチャーはやめられないのだ!
もちろん岡田も、おそらくその他のキャッチャーもそう思っているだろう。のちに外野手にコンバートされた僕は、キャッチャーの気持ちをふと思い出すことがあった。
おそらく岡田はキャッチャーとして充実した時間を長くすごしてきたので、再びあの時の感覚を味わいたいのだろう。
またチームと、ライオンズファンのみんなと、喜びを分かち合いたいと――。