「この子、すごいよ……」アマチュア五段を唸らせた少年は、早見えの才でその名を奨励会に轟かせていく。

第2章 土曜日の少年 其の2
東京・千駄ヶ谷の将棋会館には普段より青くて切実な空気が漂う朝がある。月に2度、奨励会員たちが対局する例会の日である。
15畳ほどの広さの対局室には厚さ2寸、約6センチの将棋盤がずらりと並ぶ。タイトル戦で使用されるものよりも薄く、素材も榧(かや)ではなく桂、駒はプラスチック製である。あぐらをかけば隣の者と膝がぶつかるほどの距離にひしめいた若者たちが午前9時、一斉に指し始める。
観戦記者の片山良三は部屋の一隅から対局の様子を眺めていた。日本将棋連盟が発行する専門雑誌に「関東奨励会報告」という欄があり、その担当者として例会の日になると取材に訪れていた。すべての奨励会員の前には上っていくべき階段が存在した。6級から三段へ上がり、三段で規定の成績を残せば四段昇段――晴れてプロ棋士となる。彼らにとっては例会の一局一局が人生を左右する勝負だった。
そんな1983年のある日、例会がいつになくオープンな盛り上がりを見せていた。何事かと片山が覗いてみると、余興として賞金10万円をかけた早指しトーナメントが行われていた。奨励会員が無報酬だと聞いた愛棋家から寄付金が届いたのだという。そういうことは年に何度かあった。例会の公式戦とは異なるため、場は開放的な雰囲気に包まれる。奨励会員たちの表情も幾分リラックスしている。ただ、それが将棋である以上、彼らが勝負の手を緩めることはなかった。
即席のトーナメント表がつくられ、部屋の至るところで対局が始まった。ルールは10分切れ負け。初手からの合算で持ち時間10分が経過すれば敗北である。その中でひと際、目を引く指し手がいた。羽生善治という13歳の少年だった。奨励会の仲間内では「ハブゼン」と呼ばれており、そのため片山は彼の名を「ハブ・ゼンジ」というのだろうと思っていた。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題

キャンペーン終了まで
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2023年6月15日号







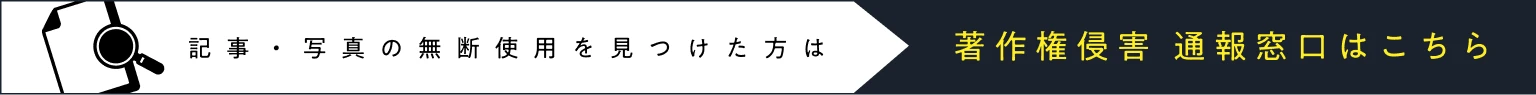
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ