七冠制覇を目指す羽生を止められるのは――。谷川はその重圧を感じながらなお、理想の棋士であり続けた。

第四章 夜明けの一手 其の二
史上初の七冠制覇がかかった第45期王将戦第4局、1日目が終わったのは午後6時12分だった。挑戦者の羽生善治が32手目を封じた。日本海を眼前に見る山口県豊浦町のホテルの「王将の間」には15台のテレビカメラと、その倍はあろうかというスチールカメラが並び、封じ手が立会人に渡される様を追っていた。谷川浩司はその異様な光景の中、じっと王将としての佇まいを守っていた。
その後、谷川は夕食を取ってから自室に戻った。全身を包んでいた緊張感が解けていく。響灘(ひびきなだ)を見下ろす角部屋は無数の視線から逃れられる唯一の場所だった。前日から、ホテルを出入りすれば必ずと言っていいほど報道陣とすれ違った。普段は見かけることのないテレビ局のクルーやキャスターの姿もあった。そのすべてが羽生の七冠制覇を報じるために集まっている。谷川はその中で最後の砦としてタイトルを守らなければならなかった。
0勝3敗、もう後がない状況で迎えた第4局。1日目は悪くない展開だった。急戦になり得る横歩取りを仕掛けてきた羽生に対し、谷川も大駒が飛び交う空中戦で応じた。いつ激しい戦いに突入してもおかしくない緊迫した睨み合いが続き、対局はスローペースで進んでいた。その中で、どちらかと言えば羽生の方に考え込む場面が目立ち、その分、持ち時間を費やしていた。
羽生が風邪を引いたという情報は前日から耳にしていたが、状態は想像していたよりも悪そうだった。一夜明けたこの日も僅かに発した声がかれており、対局中はしきりに鼻をかんでいた。微かな指しづらさとともにそんな状態の相手に負けるわけにはいかないという思いもあった。だが、そうした使命感の一方で、谷川の心には晴れない部分があった。厭世観とも言えるものだった。谷川はしばらく前から羽生と戦うことに重たさを感じるようになっていた。
1992年から1994年までの2年間、谷川はタイトル戦において羽生に7連敗を喫していた。それをようやく止めたのが七冠独占を阻止した1年前の王将戦であった。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題

キャンペーン終了まで
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2023年7月20日号







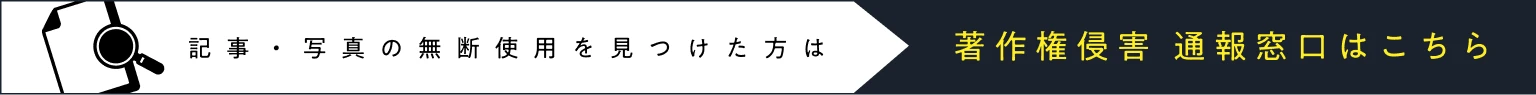
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ