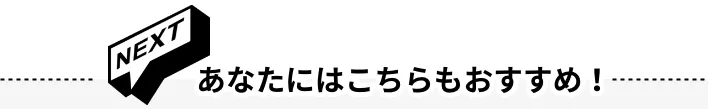二日目以降は、ジャックとともにカルガリーの中学に通った。ライ麦パンのサンドウィッチをランチとして持たされたときは、「スヌーピーとかで見たことあるやつやあ!」とひとりテンションぶち上げ状態だった。カルガリーの中学に通うことができたのはたった数日間のみだったが、日本の中学校とのカルチャーショックは激しく、ただひたすら刺激的な時間だった。
英語で繰り広げられるフランス語の授業に対して「完全に降参で〜す」という表情をしていたら一人だけ教室の掲示物の貼り換えという軽作業を託されたりと、なんだかんだ私はカルガリーでの日々に馴染んでいった。ジャックはいつも私を助けてくれたし、彼の友達も明るくて気持ちのいい子たちばかりでありがたかった。ジャックの母による食事もおいしく、靴のまま家の中をウロウロすることにも慣れ、鶴放棄事件により疎遠になっていた妹さんとの距離も再度縮まり、異国での生活に少し余裕が出てきてはいたが、私はひとつだけ、どうしても慣れないことがあった。
お風呂だ。
北米の人はまず湯船に湯を溜めない、ほぼシャワーで済ませる、という話は聞いていたが、加えてウィリアムズ家はシャワーでさえ毎日浴びないようだった。髪も肌もわりと脂っぽかった十四歳の私はそれが割とキツく、三日目あたりについに『私、シャワー、使いたい、すごく』と嘆願した。
オールオッケ〜みたいなざっくりとした返事をもらい、いざ全身を洗い流したときの気持ちよさは凄まじかった。長らく使われていないだろう白い湯船を見て、初めて日本が恋しくなったものだ。毎日たっぷりの湯に浸かることができたあの日々はなんて尊いものだったのだろうか……後ろ髪引かれる思いで脱衣所に立ち、ふわふわのタオルを目の前にして、私はハッとした。
すっかり忘れていたのだが、私はそのとき、いんきんたむしを患っていたのである。
私の通っていた中学校では、冬、剣道の授業があった。その際、剣道部も使用している防具を身に着けるのだが、とにかくそれらの匂いがひどかった。中には黴が生えているものもあり、私はまさに黴だらけの防具に身を包み一冬を過ごしてしまったのだ。あっというまに股間が痒かゆくなり、恥を忍んで病院に行ったら即、町一番のいんきんたむし野郎の刻印を押されたのである。私の股間が黴だらけだという事実は一瞬で朝井家を駆け巡り、使用するタオルなどが厳しく管理されることとなった。これが日本を発つ一週間ほど前の出来事だ。
ぽた、ぽた、と、私の体から水が滴る。
きょろきょろと、周囲を見渡す。もちろん、誰もいない。
私はゴクリと唾を飲み込んだ。
そして、白くてやわらかくて清潔なタオルを、いんきんたむしの巣窟に擦り付けた。
私は「ごめんなさいごめんなさい」と小声で繰り返しながら丁寧に股間を拭いた。家庭内で誰にもうつさないようにうつさないようにと気をつけていた菌を、まさか国を越えてバラまくことになろうとは全く思っていなかった。あんなにお世話になったウィリアムズ家に、股間から始まるパンデミックをお見舞いしたのである。恩を仇で返すとは聞いたことがあるが、私は恩をいんきんたむしで返したのだ。当時の私に鶴なんて折れなくたっていいから股間に黴だけは生やすなと言いたい。
さて、ステイ期間中、ウィリアムズ家は私といんきんたむしを色んな所に連れて行ってくれた。ジャックは地元のアイスホッケーチームに所属しており、その練習を見学しにアイスリンクにも行った。カナダでのアイスホッケー人気は凄まじく、一度スタジアムにも感染、漢字変換にもいんきんたむしの影響が出ていてつらい、観戦しに行ったのだが、かなり大きな会場がものすごい人で賑わっていた。選手のユニフォームやグッズもたくさん売られており、日本でいうプロ野球といったところだろうか。
そんなウィリアムズ家は、最後の日が近づいてきたある日、親戚中が集まるらしきホームパーティに私を連れて行ってくれた。『楽しい人がいっぱいだし、おいしい料理もたくさんよ!』だかなんだか、魔法のような誘い文句は大変甘美に響いた。